漢詩紹介
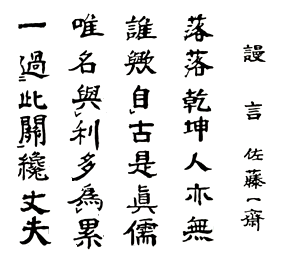
吟者:松尾佳恵
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 謾 言 <佐藤 一斉>
- 落落たる乾坤 人も亦無し
- 誰ぞ歟古自り 是真儒
- 唯名と 利と 多くは 累を為す
- 一たび此の関を過ぐれば 纔かに丈夫
- まんげん <さとう いっさい>
- らくらくたるけんこん ひともまたなし
- たれぞやいにしえより これしんじゅ
- ただなと りと おおくは るいをなす
- ひとたびこのかんをすぐれば わずかにじょうふ
詩の意味
広い世の中には人はたくさんいるけれども、本当の「人物」はいないものだ。はたして誰を昔からまことの学者と称賛できるだろうか。
ただ多くの学者は名誉と利欲とが心の災いとなって真の道に進むことができない。だから、この名利の関門を超越した人こそ、初めて大人物と言えるのである。
語句の意味
-
- 謾 言
- とりとめもなく言う言葉
-
- 落 落
- 広大なさま
-
- 乾 坤
- 天と地 世の中
-
- 真 儒
- まことの学者 「儒」は学者
-
- 累
- 重なること 煩わしいこと
-
- 丈 夫
- 立派な男子
-
- 関
- 関所 ここでは関門
鑑賞
真の学者がいないことを嘆き続ける佐藤一斉
教育者らしい佐藤一斉の教訓詩である。作者は幕府公認の学者として登用された大学者であるが、それにしても豪語したものである。「この世に真の学者はいない」「名利を超越しなければ大人物とはいえない」と。もしそうなら、同時代の大学者といわれる緒方洪庵、佐久間象山、頼山陽などはどうなるのか。ただここではそういう評価の争いではなく、当時の学問といえば儒教だからその儒学、特に朱子学を真剣に学びまた実践する人の少ないことを嘆いているのである。強烈な個性の持ち主だが筋が通っていて頼もしい。
参考
①昌平坂学問所は魯の孔子塾の分校ともいえる
作者は晩年になって江戸湯島にある「昌平坂学問所」通称「昌平黌(こう)」の教官になった。この学校はもと名門林家の私塾であった「湯島聖堂」を、元禄3年(1690)に五代将軍徳川綱吉が幕府高官の教育機関として設置し、日本初の官立学問所となった。そこでは孔子が祭られ、儒教の中でも最も孔子や孟子の思想に近い朱子学が講義された。この「昌平黌」の名だが、孔子の生誕地が山東省曲阜県昌平村であることに由来する。昌平黌が後の東京帝国大学につながっていく。
②佐藤一斉の著書の中から名言を一つ
「少にして学べば、則ち壮にして為す有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず」 (「言志晩録(げんしばんろく)」60条)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声七虞(ぐ)韻の無、儒、夫の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
佐藤一斉 1772~1859
江戸後期の儒学者・教育者
安永元年10月、江戸浜町(はまちょう)の美濃(岐阜県南部)岩村藩邸に生まれる。名は坦(たん、たいら)、字は大道(たいどう)、一斉は号である。代々美濃の岩村藩に仕えた上級藩士で、坦少年は学問、武芸に頭角を現した。後、藩籍を離れ大阪、京都で学んだ。中井竹山からは陽明学への道を開かれた。江戸に帰り林家の門に入り儒者として身を立てた。晩年は昌平黌の儒官(教授)となり、安政6年10月没す。享年88。麻布(あざぶ)の深広寺に葬る。
