漢詩紹介
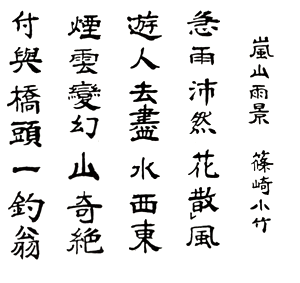
吟者:原 江龍
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 嵐山雨景 <篠崎 小竹>
- 急雨沛然として 花風に散り
- 遊人去り尽くす 水の西東
- 煙雲変幻して 山奇絶
- 付与す 橋頭の 一釣翁
- らんざんうけい <しのざき しょうちく>
- きゅううはいぜんとして はなかぜにちり
- ゆうじんさりつくす みずのせいとう
- えんうんへんげんして やまきぜつ
- ふよす きょうとうの いちちょうおう
詩の意味
にわか雨が盛んに降ってきて、花は風のために散ってしまい、花見客たちも川の東西に逃げ去ってしまった。
煙のように立ちこめる雨雲は変幻の妙を描き出し、山の景色はまことに素晴らしい。加えて、橋のほとりで釣り糸を垂れている一人の老人の姿が一層の風情を添えている。
語句の意味
-
- 嵐 山
- 京都市西部にある山桜と紅葉の名所
-
- 急 雨
- にわか雨
-
- 沛 然
- 雨の盛んに降るさま
-
- 遊 人
- ここでは花見客
-
- 変 幻
- 変化が速やかで計り知れない
-
- 奇 絶
- 普通とは違って素晴らしい
-
- 付 与
- 付け加えて
-
- 橋 頭
- 橋のほとり
鑑賞
花の嵐山もよいが、春嵐の風情も捨てがたい
京都嵐山といえば春の山桜と秋の紅葉を愛(め)でる景勝地である。にもかかわらずあえて春嵐の川辺に風情を見出したのは作者の風狂趣味だろうか。彼は詩において蘇東坡に傾倒している。その「湖上に飲す」という詩の前二句「水光瀲灔(れんえん)として晴れ偏(ひとえ)に好く、山色空濛(くうもう)として雨もまた奇なり」とある。西湖の眺めは晴天に限ると詠わず、あえて雨の西湖もまた格別だという。風物の鑑賞において師の蘇東坡を倣(なら)ったのかもしれない。夕立による空模様の急変は蘇東坡の「望湖楼」を思わせる。また川に釣り舟の構図も、杜牧の「漢江」の結句「夕陽(せきよう)長く送る釣船の帰るを」、柳宗元の「江雪」の「独り寒江の雪に釣る」などを借用したのであろう。雨中の釣り舟が嵐山に似合うかどうかは作者のみぞ知るところだろう。
参考
奇抜な景観に感じる前に、やはり日本さくら百選に選ばれた嵐山の風景を頼山陽の詩で味わってみたい。小竹の詩と対照的に鑑賞すれば嵐山の魅力は一層高まるのではないか。
遊嵐山 頼山陽
清渓一曲水迢迢 夾水桜花影亦嬌
桂楫誰家貴公子 落紅深処坐吹簫
(意解)青く澄んだ大堰(おおい)川が曲がって流れて、その水を挟んで咲く桜の姿はまことに美しい。
桂(かつら)の櫂(かい)をこいで舟遊びをしているのはどちらの貴公子であろうか。紅の花びらが
しきりに積もるあたりに座って美しい音色の簫の笛を吹いている。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声一東(とう)韻の風、東、翁の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
篠崎小竹 1781~1851
江戸後期の儒学者、教育者
豊後(ぶんご=大分県)の医師 加藤吉翁の次男として天明元年大阪に生まれる。幼名を金吾、字を承弼(しょうひつ)、通称は長左衛門、小竹、南豊(なんほう)、退庵(たいあん)などと号す。9歳で篠崎三島(さんとう)の門に入り、のち養子となる。江戸で尾藤二洲(びとうにしゅう)や古賀精里(せいり)に学ぶ。28歳で大阪に帰り、養父三島の跡を継いで子弟を教え、名声は四方に聞こえた。諸侯にも教えを乞うものが多かった。笛、書などにも通じ、蔵書は万巻に上るという。嘉永4年5月没す。享年71。
