漢詩紹介
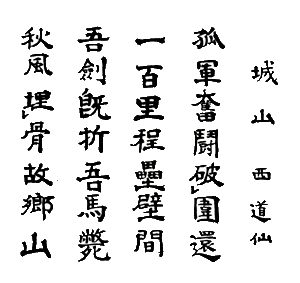
吟者:小坂永舟
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 城 山 <西 道仙>
- 孤軍奮闘 囲みを破って還る
- 一百の里程 塁壁の間
- 吾が剣は既に折れ 吾が馬は斃る
- 秋風 骨を埋む 故郷の山
- しろやま <にし どうせん>
- こぐんふんとう かこみをやぶってかえる
- いっぴゃくのりてい るいへきのあいだ
- わがけんはすでにおれ わがうまはたおる
- しゅうふう ほねをうずむ こきょうのやま
詩の意味
孤立無援の軍勢で奮い闘って、官軍の重囲を突破し、故郷の城山に帰りつくことができた。百里もあろうかと思える道のりを敵の砦(とりで)の間を抜いて脱出して来たのである。
やっと帰ってきたが、たび重なる戦いでわが剣はすでに折れ、わが馬も倒れて死んでしまった。もはやこれまでである。今は秋風の中、懐かしい故郷の城山でわが骨を埋める身となった。
語句の意味
-
- 孤 軍
- 孤立した軍隊
-
- 里 程
- 道のり
-
- 塁 壁
- 砦の城壁
-
- 故郷山
- 城山 鹿児島市の北部にある高さ100mの丘 裏の岩崎谷には隆盛が最後の5日間起居した洞窟がある。
鑑賞
明治維新の英傑西郷隆盛の終焉
同じ九州人である作者が、隆盛の敗死したことを新聞で知り、隆盛の心を自分の心として同情し、その死を深く嘆いて作った詩である。
鹿児島で挙兵し、九州鎮台(ちんだい)を攻めたあたりまでは良かったが、政府軍は5万の部隊と近代兵器で西郷軍を寄せ付けない。その後、田原坂の敗戦から始まって吉次峠、人吉、高鍋、延岡、宮崎、長井と南東九州を一巡するほどの長い行軍であった。維新の英傑の最期とは思えない悲惨な末路である。足に砲弾を受けて、前進できない隆盛の苦痛と、城山で自害せざるを得なかった無念さを読み取りたい。
備考
この詩の本題は「西郷隆盛を詠ず」であるが、本会では「城山」と簡略にした。西南戦争は明治10年2月に始まり9月に終焉する、薩摩藩と明治新政府との争いである。
参考
西南戦争はなぜ始まったのか
隆盛は征韓論で敗れ、明治新政府を見限って下野し、俗事をはなれ故郷の山野で自然に親しみ楽しんで暮らしていた。そこで起こった二つの事件。一つは東京から密偵が遣わされ、それによると隆盛暗殺計画が実行されるということ。二つめは政府が鹿児島にある陸軍火薬庫の弾薬をひそかに運び出したこと。隆盛の率いる私学校派に奪われることを恐れてのことであるという。これを知った私学校派の生徒が逆に弾薬を奪ってしまった。事態収拾が隆盛に委ねられた。この情報に不平士族たちが隆盛のもとに結集したのである。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十五刪(さん)韻の還、間、山の字が使われている。平仄は詩の定形からすれば転句と結句の平仄が原則に合っていないので完全とはいえない。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
西 道仙 1836~1913
江戸末期から明治初期の医師・儒学者
天保7年熊本県天草に生まれる。名は喜大(きだい)、号は琴石(きんせき)、字は道仙(道遷もある)。明治5年学制頒布以来多数の子弟を擁して教学の道に挺身し、また明治25年には長崎文庫を開き長崎郷土史に寄与すること大きく、長崎区会議長、衛生委員会幹事長、医師会副会頭などを歴任し、大正2年7月没す。享年78。寛斉と号し医師の儒者として世に知られている。
