漢詩紹介
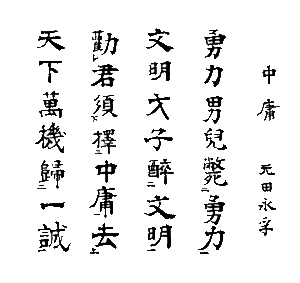
吟者:中島 菖豊
2005年8月掲載
読み方
- 中 庸 <元田 永孚>
- 勇力の男児は 勇力に斃れ
- 文明の才子は 文明に酔う
- 君に勧む 須く 中庸を択び 去るべし
- 天下の万機は 一誠に帰す
- ちゅうよう <もとだ えいふ>
- ゆうりょくのだんじは ゆうりょくにたおれ
- ぶんめいのさいしは ぶんめいによオ
- きみにすすむ すべからく ちゅうようをえらび さるべし
- てんかのばんきは いっせいにきす
詩の意味
あまりに勇気を頼み、腕力のみにたよる男は、かえって自分の力で自分が倒れるものである。また、あまりに文明かぶれして自分の才能に溺れる者は、世の中の華美に酔うて、事を誤ることが多い。
だから皆さんにお勧めしたいことは、右にも左にも偏らず、常に中道を選んで進んで行かれることである。そして世の中のことは何事にも誠心誠意でやれば、間違いはないのである。
語句の意味
-
- 中 庸
- 行き過ぎも不足もなくほどよいこと すなわち右にも左にも偏らず中道であること
-
- 勇 力
- ここでは野蛮な勇気
-
- 文 明
- 人知が発達し世の中が開けること
-
- 才 子
- 知能が優れた人 気が利いて抜け目がない人
-
- 天下万機
- 世の中のことは何事でも
-
- 帰一誠
- 誠心誠意 誠の一字に尽きる
鑑賞
人生はつまるところ誠心誠意あるのみ
わかり易い言い回しで、しかも結句に述べたいことが凝縮されている。「誠の一字」で行動せよと訴えている。
自己の勇力に任せて粗暴過激に走る人がおり、それがわざわいし、一身を亡ぼすのみならず、社会、国家に大きな害を及ぼすであろうと思われる人への戒めと、政治する者への警告とみるべきであろう。
承句は、明治維新の動乱が収まって新時代を迎え、文明開化の時代となり、西洋の風習をとりすぎ、これを新の勇力と心得る者達が多く出始めたので、それを忠告したものである。つまり世の中は力だけでもなく、また才だけでもない。要は右にも左にも偏らず中庸の道を守り、誠の一字をもって万事を貫くべきことと説いている。その論旨は明快でありながら、詩の調子が穏やかで、なだらかなのは謹直温厚で和気あいあいたるその人柄の発露によるものと思われる。
参考
思想書「中庸」について
儒教の中心的書物である四書(論語、孟子、大学、中庸)の一つ。孔子の孫の子思(しし)の著ともいわれている経典(けいてん)である「中庸」の「中」とは偏りのないこと、「庸」とは永久不変のこと。天下の正しく変わることのない道理を説く書という意味である。21章からなり、実践する根源は一つであると言っている。それが「誠」であることを強調し、さらに「誠」は天の道であり、これを実行するのが人の道であるとして、「誠」こそ人間性の本質であり、同時に天道の本質であると説くものである。
備考
作者永孚は、復古と維新のいずれにも偏せず、中道を以て明治の新時代を開いた思想家である。単に保守的で大局のつかめない朱子学者ではなく、時勢を大観し、物事の内部にある弊害を矯正して、明治天皇の教育に尽くし、「誠」の一字を以て生涯を貫いた人と言える。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の明、誠の字が使われている。起句は踏み落とし。起句と承句は対句になっている。斃・勇・力は仄字が3字連なっており、下三連を忌むという規則に反している。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
元田永孚 1818~1891
江戸末期・明治初期の漢学者
文政元年熊本市に生まれる。字は子中(しちゅう)、伝之丞と称し、東野(とうや)と号す。幼にして学を好み13歳にして詩を作り、進んで修身治国の学に志す。明治4年宮中に入り、累進(るいしん)して明治天皇の侍講(じこう)となる。人に接するときは春風のように和気靄然(あいぜん)とし、天皇の恩遇も厚く、時々ともに吟詠を楽しんだ。帝国憲法、皇室典範、教育勅語の草案起草にも加わり、「幼学綱要」の編纂(へんさん)にもあたった。明治24年、特旨(とくし)により男爵を授けられた。同年1月没す。享年74。著書に「東野詩集」がある。
