漢詩紹介
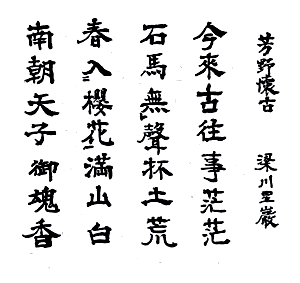
吟者:稲田 菖胤
2005年4月掲載
読み方
- 芳野懐古 <梁川星巌>
- 今来古往 事 茫茫
- 石馬声無く 抔土荒る
- 春は桜花に入って 満山白く
- 南朝の天子 御魂香し
- よしのかいこ <やながわせいがん>
- こんらいこおう こと ぼうぼう
- せきばこえなく ほうどある
- はるはおうかにいって まんざんしろく
- なんちょうのてんし ぎょこんかんばし
詩の意味
吉野に来て南朝の昔の事柄を尋ねてみても、当時から既に長い年月を経ているので、何の事かぼんやりとしていてはっきりしない。御陵の前の狛犬(こまいぬ)は何一つ語ろうとしないし、御陵(ごりょう)も荒れるに任せている。
ただ春は桜の花にも及んで、昔ながらに咲き乱れ、山全体を白く飾っていてまことに美しい。それはまるで南朝の天子の御魂(みたま)が芳しいことを、我々に伝えているかのように感じられる。
語句の意味
-
- 芳 野
- 吉野と同じ 詩文では風雅をこめて芳野と表記
-
- 今來古往
- 昔から今まで 古往今来も同じ
-
- 石 馬
- 中国では帝王や貴族の墓の前に立つ石造りの馬 一般的に社前に見られる石造りの狛犬
-
- 抔 土
- 墓 「抔」は手ですくう ここでは御陵
-
- 南朝天子
- 後醍醐天皇をはじめ南朝の天皇
鑑賞
勤王家にとって南朝時代は忘れるに忘れられない
あまりに歳月を経たので南朝時代のことは茫然として記憶の外にあると断りつつ、結句では南朝の天子の魂が桜の香りを借りてよみがえり、改めて天皇の遺徳が称えられているように生き生きと表現されている。やはり作者の南朝を思う心は鮮明に残っていたのである。勤王家らしさを見ることができる。
「石馬声無く」も、うまい表現である。後醍醐帝の御陵には石馬は無い。中国の皇帝陵とダブらせているところに広がりを感じさせる詩的効果を考えたのであろう。もちろんお墓の守り犬の石像だから、石が啼くわけがない、と言ってしまえば無粋である。見る人によって吠えたり黙ったりするのである。ここでは、あたりが静まり返って、神の使いの犬として常に御陵をお守りし続けていることを象徴している。
備考
南朝時代
1333 後醍醐天皇が隠岐の島を脱出
鎌倉幕府滅亡
朝廷による政治、建武(けんむ)の新政始まる
1335 足利尊氏が建武の新政に反旗をかかげる
1336 湊川の戦いで楠正成が死す
後醍醐天皇が吉野に隠れる
1338 足利尊氏が室町幕府を開く
1339 後醍醐天皇が死去
1348 四条畷で正成の子供正行(まさつら)が戦死
1368 足利義満三代将軍となる
1392 南朝の後亀山天皇が神器を北朝の後小松天皇に譲渡 南北朝合一
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声七陽(よう)韻の茫、荒、香の字が使われている。転句は二六同になっていない。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
梁川星巌 1789~1858
江戸後期の儒学者・詩人
美濃(みの=岐阜県)に生まれる。名は孟緯(もうい)、字は星巌、号は天谷(てんこく)。妻紅蘭(こうらん)と共に詩を善くし、天下を漫遊すること20年。天保5年に江戸に出て、玉池(ぎょくち)吟社を興し、江戸詩壇の盟主として名声が高まった。当時の詩人菅茶山(ちゃざん)、広瀬淡窓、菊池五山などことごとくその詩友である。常に尊皇愛国の志が厚く、七言律詩に多くこれを託している。安政5年に没す。享年70。著書に「星巌詩集」がある。
