漢詩紹介
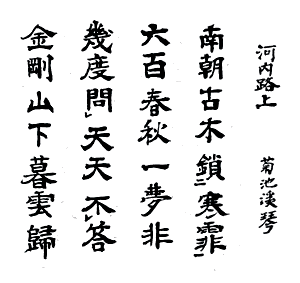
吟者:鈴木 永山
2005年4月掲載
読み方
- 河内路上 <菊池 渓琴>
- 南朝の古木 寒霏に鎖さる
- 六百の春秋 一夢非なり
- 幾度か天に問えども 天は答えず
- 金剛山下 暮雲帰る
- かわちろじょう <きくち けいきん>
- なんちょうのこぼく かんぴにとざさる
- ろっぴゃくのしゅんじゅう いちむひなり
- いくたびかてんにとえども てんはこたえず
- こんごうさんか ぼうんかえる
詩の意味
遠く南朝のころからの古木は冷たい靄(もや)に閉ざされ、600年の歳月を隔てて、楠公の事跡もむなしく一場の夢と化してしまった。
このことを幾度か天に向かって尋ねてみたが、天はいっこうに答えてくれるはずもなく、ただ金剛山の麓に、寂しく夕暮れの雲が帰っていくのが見えるばかりである。
語句の意味
-
- 河内路上
- 河内(大阪)の金剛山の麓にある楠木正成の遺跡を訪ね行く途上の歌に題す
-
- 寒 霏
- 冷たい靄
-
- 一夢非
- 一場の夢と化してすべてが昔と変わってしまった 「非」は昔日に非ず(非昔日)など補ってみるとよい
-
- 金剛山
- 奈良県と大阪府にまたがる山系の主峰 麓(中腹)には赤坂、千早という正成挙兵の陣(城)があった。
鑑賞
楠正成の無念はまた作者の憤怒(ふんぬ)
この詩はすこぶる立体的である。各句の上と下が対照的になっているからである。「南朝古木」と「鎖寒霏」は歴史の重みと現在の状況の対照。楠正成と足利尊氏といってもよい。「六百春秋」と「一夢非」は長い歳月と一瞬。「幾度問天」と「天不答」は仰ぐ姿とうなだれる姿。「金剛山」と「暮雲帰」は高い嶺とふもとの風情。しかも全句が感情語や理屈を挟まず叙景のみであるところに読者は作者の感懐をさぐりたくなる。50歳以降の作となっているが、円熟度の高い作品である。また「天に問う」とあるが、おそらく屈原の楚辞「天問」編に見ると屈原が続けざまに心に満ちた憤りを述べて、その疑問を天に問うているという件(くだり)にひびかせていると思われる。
参考
赤坂城について
鎌倉時代末期に楠正成が築いた山城で大阪府南河内郡千早赤阪村に在る。元弘元年(1331)正成が後醍醐天皇の勅命を受け挙兵したときの下赤坂城跡で北条氏の攻撃によって同年10月に落城した。また翌年、正成が千早城に立て籠って幕府軍と戦ったさい、武将平野将監(しょうげん)に守らせた上赤坂城址は、翌3年開城した。その後南北朝時代にも正成が立て籠って足利軍と戦った際、ここに築いた砦は小さいながら堅固で、この砦に籠城した正成の知略ある戦法によって大軍なる敵を大いに苦しめた。
現在も赤坂城跡には堀切などの遺跡があり、上下併せて史跡に指定されている。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声五微(び)韻の霏、非、帰の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
菊池渓琴 1799~1881
江戸末期・明治初期の豪農・漢学者
紀州(和歌山県)有田郡栖原(すはら)村に生まれる。名は保定(やすさだ)、字は士固(しこ)とか孫介(まごすけ)。渓琴はその号。大窪詩仏に学び、詩を善くし、佐藤一斉、頼山陽、広瀬旭荘、安積艮斉(あさかごんさい)、梁川星巌、藤田東湖、佐久間象山など一流の士と親交があった。名節を尊び、武芸を好み、海防の急務を建言した。明治24年東京で没す。享年83。著書に「秀餐(しゅうさん)楼集」「渓琴山房集」「海荘集」などがある。
