漢詩紹介
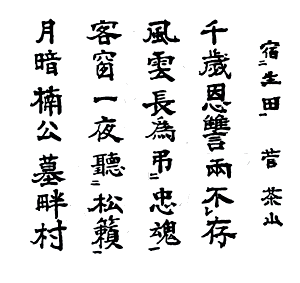
読み方
- 生田に宿す <菅 茶山>
- 千歳の恩讐 両つながら存せず
- 風雲長えに為に 忠魂を弔う
- 客窓一夜 松籟を聴く
- 月は暗し 楠公 墓畔の村
- いくたにしゅくす <かん ちゃざん>
- せんざいのおんしゅう ふたつながらそんせず
- ふううんとこしえにために ちゅうこんをとむろオ
- かくそういちや しょうらいをきく
- つきはくらし なんこう ぼはんのむら
詩の意味
千年を経た今では、かつて敵味方となって戦ったというが、今は跡形もなく消えてしまった。ただ風や雲ばかりがこの地を訪れ、永久に楠公の忠魂を弔(とむら)っているかのように見える。
私は旅の一夜をこの生田に過ごし、松風の音に耳を傾けながら昔をしのんだ。眠れぬままに窓の外を見ると、月もほの暗く、楠公の墓のあるこの村は、なんとも寂しい限りであった。
語句の意味
-
- 生 田
- 神戸市生田区(現中央区) その西に楠正成が自害した古戦場湊川がある
-
- 恩 讐
- 味方と敵 ここでは南朝と北朝
-
- 弔忠魂
- 忠義の人である楠正成の魂を慰める
-
- 客 窓
- 宿屋の窓
-
- 松 籟
- 松風の音
-
- 墓畔村
- (楠正成の)墓のほとりの村 現在の湊川神社あたり
鑑賞
訪れる人のいない大楠公の墓
この詩は、茶山48歳3月22日に舞子浜、須磨を経て生田にいたった時に賦したものである。この当時は未だ開けておらず、寂しい農村の片すみに楠公の石碑が立っているのみであった。茶山は、墓畔の淋しい情景の中で曽つてのドラマに思いをめぐらせ、単なる写実におちいらず、むしろ切実な情感を述べようとした詩と思いたい。楠公を詠う詩は重く暗い。この詩も「風雲」「月暗」「松籟」などの語が続き、やはり重苦しい。「松籟」は詩語として定着しているが、ただ松風の音というのではなく、すさまじさを伴ったさみしい風情を持っている松風の音であって、この詩のように何もない夜中の描写によく用いられている。
楠公が亡くなって約400年。徳川光圀(みつくに)が「嗚呼忠臣楠子之墓」を湊川に建立して約100年。茶山の時代は元禄太平の世で、世人は楠公の業績を忘れたのか、この史跡を訪れる人がいない。茶山は特別な勤皇派ではないが、ただ雲と風だけが訪れるというのでは、あまりに寂しい。しかもこの寂しさがこれからも続くと読みとれる。沈黙したまま思索にふける作者が目に浮かぶ。頼山陽も激賞している名作である。
備考
因みに吉田松陰も嘉永4年(1852)3月、兵学研究のため江戸へ向かう途中、湊川の楠正成の墓を拝し、その墓前で一詩を賦した。松陰はこの時「嗚呼忠臣楠子之墓」と朱舜水の撰した碑陰の銘の石刷りを求めている。松陰が語るこの詩は正成の忠節をたたえ、「建武中興」の際、正成の役割がいかに大きなものであったかを述べ、楠公は死んでも、その精神は湊川の水のように脈々と後世に伝えられると述べている。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十三元(げん)韻の存、魂、村の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
菅 茶山 1748~1827
江戸時代中期から後期の学者・漢詩人
寛延元年、備後神辺(びんごかんなべ=広島県福山市)に生まれる。生家は裕福な農家で造酒業も営んでいた。名は晋帥(しんすい)、字は礼卿(れいきょう)、茶山(さざんともいう)はその号。京都に遊学し、のち郷里に塾を開き、生涯を子弟の教育に捧げた。その塾を「廉塾(れんじゅく)」といい、住居を「黄葉夕陽村舎」と名づけた。詩名高く子弟は多い。福山候の援助もいただけるほど評価も高まり、頼山陽、梁川星巌夫妻、広瀬旭荘など著名人が訪れている。著書に「黄葉夕陽村舎詩」前後編その他多数ある。文政10年8月没す。享年80。
