漢詩紹介
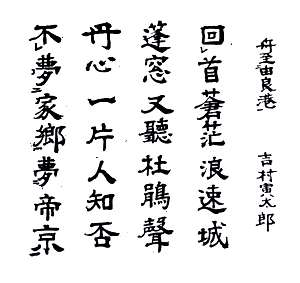
吟者:松野春秀
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 舟由良港に至る <吉村 寅太郎>
- 首を回らせば蒼茫たり 浪速の城
- 篷窓又聴く 杜鵑の声
- 丹心一片 人知るや否や
- 家郷を夢みず 帝京を夢む
- ふねゆらこうにいたる <よしむら とらたろう>
- こうべをめぐらせばそうぼうたり なにわのしろ
- ほうそうまたきく とけんのこえ
- たんしんいっぺん ひとしるやいなや
- かきょうをゆめみず ていきょうをゆめむ
詩の意味
振り返ってみると大阪城は青々として、遠くかすんではっきりとは見えない。折しも、とま船の窓で血を吐くようなホトトギスの声を聞いた。(そうでなくても悲痛無念の極みであるのに)
いったい今の世で、誰が、わが胸中の真心を知ってくれるであろうか。とても他人にはわかるまい。今夜もこの舟の中で見る夢は、故郷のことではなく、天皇のおられる京のことなのである。
語句の意味
-
- 由良港
- 淡路島の東岸にある港
-
- 蒼 茫
- 青々としてはるかなさま
-
- 浪速城
- 大阪城
-
- 篷 窓
- 「篷(とま)」は苫 竹やかやなどを編んで船を覆うもの とま船の窓
-
- 丹 心
- 真心
-
- 帝 京
- 天子の都 京都
鑑賞
母を思う以上に強烈な回天の大義
この詩は作者が寺田屋事件の同志として捕らえられ、土佐藩に引き渡されたあと、大阪から土佐に護送される途中、由良港に寄港した時の作である。まだ26歳の若さであった。
起・承句は穏やかな歌いぶり。ただ承句の「杜鵑の声」は鋭く血を吐くような声といわれているから、いささか不気味さを感じる。その声の先には、許しがたい幕府の開国政策と先の見えない日本がある。これからの日本は朝廷による政治、つまり尊王政治でなければならない。それに回帰するためには身をも捨てるという、強烈な信念がうかがえる。このあたりが「丹心」の中身だろう。死の前年に坂下門外の変を知り、故郷土佐藩を脱藩して京に向かう折、母から告げられた歌「四方に名をあげつつ帰れ帰らずば遅れざりしと母に知らせよ」が胸中に蘇(よみがえ)ったのではないか。「家郷を夢見ず」というのは、単に故郷のことを思わないというのでなく、先立つかもしれない不孝を母に対してわびつつ、それ以上に皇室復興に身を捧げる自分を許してほしいという心を歌っている。一代の英雄といわれる所以(ゆえん)である。
参考
寺田屋事件
文久2年(1862)薩摩藩の尊王攘夷派が京都伏見の船宿「寺田屋」で鎮圧された事件。同藩の尊王攘夷派30名は、藩兵一千人を率いて上洛していた公武合体論者の島津久光が自重を求めたのに応ぜず、事件になった。思想を異にする同藩同志の斬り合いとなった。寅太郎は翌日薩摩に捕らわれ土佐藩に引き渡された。
辞世の句
「芳野山 風に乱るるもみじ葉は 我打つ太刀の 血煙(ちけむり)とみよ」
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の城、声、京の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
吉村寅太郎 1837~1863
江戸末期の土佐藩士・志士
名を重郷(しげさと)といい、通称寅太郎。黄庵(こうあん)と号す。土佐(高知)高岡郡の庄屋太平(たへい)の長男として生まれ、幼少より俊敏、郷里では習うべき人なしと城下に遊学。12歳で父に代わって庄屋(名主=なぬし・村長=むらおさ)となり実績を上げたという。文久2年、家を脱して京都に至り、平野国臣(くにおみ)らとともに勤皇の大義を唱え、同志の決起を促し、武市半平太と謀(はか)って回天の策を巡らし、さらに翌年、奈良の五条で天誅(てんちゅう)組の兵を挙げたが敗死する。享年27。
