漢詩紹介
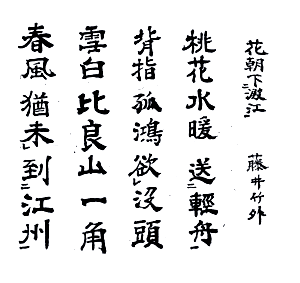
吟者:池田菖黎
2017年8月掲載
読み方
- 花朝澱江を下る <藤井 竹外>
- 桃花水暖かにして 軽舟を送る
- 背指す孤鴻 没せんと欲する頭
- 雪は白し 比良山の一角
- 春風猶未だ 江州に到らず
- かちょうでんこうをくだる <ふじい ちくがい>
- とうかみずあたたかにして けいしゅうをおくる
- はいしすここう ぼっせんとほっするほとり
- ゆきはしろし ひらさんのいっかく
- しゅんぷうなおいまだ ごうしゅうにいたらず
詩の意味
やっと春に水もぬるんで(水かさも増して)わが乗るはやぶねを㔟いよく押し流してくれる。後を振り向くと、今しも一羽の水鳥が天空の彼方(かなた)に消え去ろうとするのが見えた。
ちょうどその辺りに比良山が高く聳(そび)え、その一角には残雪が白く輝いている。さて、こちらの温暖に似ず、江州にはまだ春風が訪れていないらしい。
語句の意味
-
- 花 朝
- 陰暦2月15日 陽暦の3月の末ごろ
-
- 澱 江
- 淀川 「澱」は「淀」に同じ 木津川、桂川、加茂川を集めて大阪湾にそそぐ
-
- 軽 舟
- はやぶねのこと
-
- 背 指
- 後を振り返ってみる
-
- 孤 鴻
- 「孤」は1羽 「鴻」は雁に似た大きい水鳥
-
- 比良山
- 琵琶湖の西に高く聳える山
-
- 江 州
- 近江の国 今の滋賀県
鑑賞
春を待ちわびる澱江下り
この詩は、作者が26歳の時、伏見から淀川を下って大阪へ向かう時に詠んだものである。桃花が咲き水暖かなる淀川の近景と、雪が白く残る比良山の遠景とを対称に、季節の違和感を覚えながら淀川に春の訪れたことをひそかに喜んでいるものである。承句の意図は何だろうか。単なる風景描写とは思えない。早春のことで摂津の国でもまだ珍しい鴻(おおとり)が確かに目に留まったのだろうが、その消えゆく先に比良山が聳えている。この鴻はそうした近景から遠景に読者を自然に誘導する効果を持つ巧みな表現である。有名な詩だけに批判も多い。伏見にいても淀、八幡あたりからにしても比良山は現実には目に入らないというものだ。しかし詩は必ずしも実写のみに限らないもので、その場の印象を想像を膨(ふく)らませながら歌ったものと解釈して差し支えない。なお四句目の発想は王之渙(しかん)の「涼州詞」の結句「春光度(わた)らず玉門関」からヒントを得たものかもしれない。
参考
近江の国は東山道
江戸時代の日本全土を表す名称に「一畿八道」がある。すなわち➀畿内(きない=山城・大和・河内・和泉=いずみ・摂津)②北海道③東山道④東海道⑤北陸道⑥山陽道⑦南海道⑧山陰道⑨西海道である。この詩に出てくる江州は近江の国で、今の滋賀県に当たる。東海道の一部かと思われるが、実は東山道の一つだった。つまり今の青森県・岩手県・秋田県などと同じ東山道の一部に数えられていた。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の舟、頭、州の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
藤井竹外 1807~1866
江戸末期の漢詩人
文化4年摂津高槻藩(大阪府高槻市)の名家に生まれる。名を啓(けい)、字は士開(しかい)、号は竹外または雨香仙史(うこうせんし)という。頼山陽に学び、梁川星巌、広瀬淡窓などと交わる。絶句に秀で「絶句竹外」の称あり。生涯酒と詩を好んだ。多くの詩篇を遺す。吉野の如意輪寺に「芳野」の真筆がある。慶応2年没す。享年60。
