漢詩紹介
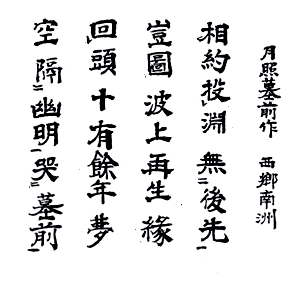
読み方
- 月照墓前の作 <西郷 南洲>
- 相約して淵に投ず 後先無し
- 豈図らんや 波上 再生の縁
- 頭を回らせば 十有余年の夢
- 空しく幽明を隔てて 墓前に哭す
- げっしょうぼぜんのさく <さいごう なんしゅう>
- あいやくしてふちにとうず こうせんなし
- あにはからんや はじょう さいせいのえん
- こうべをめぐらせば じゅうゆうよねんのゆめ
- むなしくゆうめいをへだてて ぼぜんにこくす
詩の意味
月照と西郷が互いに手を取り合って薩摩の海に身を投じたが、自分だけが生き残ってしまった。いかに運命であるとはいえ思いもよらぬことであった。
思い起こせばあれから早十余年の歳月が過ぎ去り、まるで夢のようである。今ここにあの世とこの世に住む所を異にして、たがいに相語り相見(まみ)ゆることが出来ないのは何としても残念で、悲しさに堪えず、墓前で嘆き叫ぶのである。
語句の意味
-
- 月 照
- 名は忍向(にんこう) 京都清水(きょみず)寺成就(じょうじゅ)院の住職
-
- 投 淵
- 薩摩の海に身を投ずる
-
- 豈 図
- どうしたことであろうか 思いもかけず
-
- 幽 明
- 「幽」は冥土(めいど) 「明」はこの世
-
- 哭
- 嘆き叫ぶ 声をあげて泣き悲しむ
鑑賞
亡き月照に生あるわが身を愧(は)ず
朝廷の高官、近衛忠熙(ただひろ)公からの、月照を守護せよという付託も果たせず、月照と死を誓ったのに、自分一人、生き残ったことは、責任感の強い南洲にとって、このうえなく気恥ずかしく自責の念がいつまでも残っていたのである。後年、とある人に対して「婦女子のするが如き真似をし、しかも自分のみ生き残りるたるは面目無き次第。あの折、刀を用いたならば、よもや不覚をとること無かりしに」と語ったと言う。この詩はそうした南洲の人柄を考えて読むべきではないか。墓前に額(ぬか)づいている維新の勇者が大声で泣き叫んでいる姿は胸を打つ。亡き人への涙ともいえるし、せっかくの天皇親政政府も藩閥の色が濃く思うようにいかず、憂国の涙ともいえる。
備考
本題は「亡友月照十七回忌辰作」というが、本会では「月照墓前作」と略述した。
僧月照は京都清水寺の分院の住職であった。島津藩の朝廷工作に尽力し、南洲とは盟友で、慷慨(こうがい)勤皇の志が篤く、そのため江戸幕府からにらまれていた。南洲は朝廷からの依頼で月照を守り、京都から薩摩に入ったが、島津藩では幕府の追跡を恐れ、月照を日向(ひゅうが)に送ると称して国境で切り捨てる決断をした。もはやこれまでと思い、両人は護送の途中錦江(きんこう)湾に相次いで海に投じた。安政5年11月11日夜のことで、隆盛は漁師に救われて蘇生し、月照は死んだ。時に46歳。月照の辞世の歌「大君のためには何か惜しからん薩摩の瀬戸に身を沈むとも」がある。この漢詩は月照十七回忌に作られたものである。
参考
南洲の「敬天愛人」
西郷南洲の思想として「敬天愛人」の言葉が引き合いに出されるが「敬愛」の2字は彼の信条であり、天をおそれ敬い人をいつくしみ愛するのが南洲の生涯であったといえよう。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の先、縁、前の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
西郷南洲 1827~1877
江戸末期から明治初期の政治家
薩摩藩士。文政10年に鹿児島市下加治屋町に生まれる。名は吉之助(きちのすけ)、通称は隆盛(たかもり)、南洲は号である。安政元年(1854)薩摩藩主島津斉彬(なりあきら)の側近に抜擢(ばってき)された。水戸藩の学者藤田東湖に師事した。維新後政府高官となり征韓論を唱えたが容(い)れられず退官し故郷に戻った。明治7年私学校党を結成し、同10年いわゆる西南戦争で新政府に対し挙兵したが、敗れて城山で自決した。 享年51。
