漢詩紹介
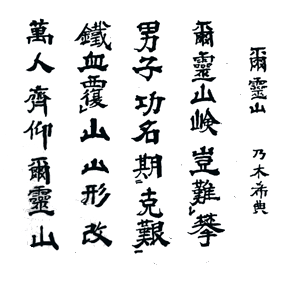
GD④収録 吟者:浅図鳳仙
2016年1月掲載
読み方
- 爾霊山 <乃木 希典>
- 爾霊山は𡸴なれども 豈攀じ難からんや
- 男子功名 克艱を期す
- 鉄血山を覆うて 山形改まる
- 万人斉しく仰ぐ 爾霊山
- にれいざん <のぎ まれすけ>
- にれいざんはけんなれども あによじがたからんや
- だんしこうみょう こっかんをきす
- てっけつやまをおおオて さんけいあらたまる
- ばんじんひとしくあおぐ にれいざん
詩の意味
二〇三高地はいかに険しくとも、どうして攀じ登れないことがあろうか。男子たるもの、功名を立てようとするならば、艱難辛苦に打ち克とうという覚悟が肝要である。
その決意のもとに激戦し、ついに砲弾の鉄片と将兵の尊い血が山を覆うて山の形さえ変わってしまった。誰しも皆この地を仰ぎ見るとき、嗚呼(ああ)爾(なんじ)の霊の山と、等しく仰ぎ慰めるであろう。
語句の意味
-
- 爾霊山
- 旅順の二〇三高地 乃木将軍によりその名を得た
-
- 克 艱
- 艱難辛苦に打ち克つ
-
- 鉄 血
- 砲弾の鉄片と将兵の尊い血
鑑賞
爾霊山(二〇三高地)は幾万の英霊の籠(こ)もれる山よ
二〇三高地攻防戦の激しさを思い、勇敢に戦った兵士をたたえ、又、若くして散った英霊を弔いこの詩を詠じた。膨大な死者を出した自責の念を歌ったもの。「凱旋」「金州城」と共に乃木三絶の1つに数えられる。いかに難攻不落の要塞(ようさい)とはいえ、その犠牲はあまりにも大きかった。天皇陛下に「微臣(びしん)の罪、まさに万死に当たる。仰ぎ願わくは臣に死を賜りますよう」と奏上した。無論陛下はそれを許すことはなかった。一読して堂々とした詩に思われるが、絶句の法を無視して、起句と結句に「爾霊山」を2回用いているのは、この3字に無限なる痛切の心情が込められているに他ならない。乃木の悲壮な心情を思い、よくよく味わうべきである。
備考
日露戦争では日本軍の攻撃は70余日であった。彼我(ひが)の死傷者は各々(おのおの)万を超え未曾有(みぞう)の惨烈を極める。現在の山の高さは200メートル。往時の激戦で3メートル低くなったといわれる。山の頂上には英霊を弔う希典の碑があり、中腹には次男保典(やすすけ)少尉の戦死の碑がある。
参考
日露戦争とは
日清戦争後、欧米列国が清国(中国)を支配下に置く状況が続き、清国は6ヵ国に分割支配されていた。日本も朝鮮半島に加えて北中国を視野に入れていた。しかしロシアも中国北東部に進出しつつあり、日本との利害が衝突した。明治35年、日本は日英同盟を結んでロシアと対決する道を選んだ。ロシアが韓国北部に軍事施設を作り始めたと報じられると、国内にも対ロシア戦を肯定する動きが高まっていった。明治37年に日本海軍が旅順軍港を奇襲攻撃して日露戦争が始まった。多大の犠牲を払いながら翌年、ロシア軍を撤退させ朝鮮半島を占領下に置いた。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十五刪(さん)韻の攀、艱、山の字が使われている。転句は二六同になっていない。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
乃木希典 1849~1912
明治時代の陸軍軍人
長州藩(山口県)江戸屋敷に生まれる。幼少期に吉田松陰の叔父玉木文之進に学問を学び、剣を栗栖(くりす)又助に学んだ。また詩歌にも優れ、石林子(せきりんし)、石樵(せきしょう)と号した。歩兵第14連隊長心得として西南戦争に出征し、連隊旗を西郷軍に奪われる屈辱を嘗(な)めたが、日清戦争では第1旅団長として旅順を占領した。日露戦争では第3軍司令官に任命された。明治37年大将となる。明治天皇の御大葬当日静子夫人とともに殉死した。享年64。
