漢詩紹介
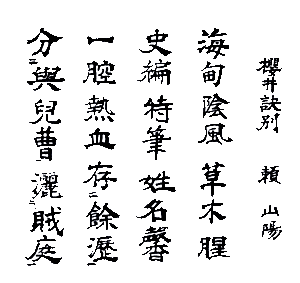
吟者:原 江龍
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 桜井訣別 <頼 山陽>
- 海甸の陰風 草木腥し
- 史編特筆 姓名馨し
- 一腔の熱血 余瀝を存し
- 児曹に分与して 賊庭に灑がしむ
- さくらいけつべつ <らい さんよう>
- かいでんのいんぷう そうもくなまぐさし
- しへんとくひつ せいめいかんばし
- いっこうのねっけつ よれきをそんし
- じそうにぶんよして ぞくていにそそがしむ
詩の意味
海辺の町はずれの湊川から吹いてくる雨雲の風は、あたりの草木までも生臭い感じにさせる。しかし大楠公の忠誠は歴史上でも特に明記されて、その名は永遠に芳しく伝えられている。
正成はこの桜井の駅に来て、体中に満ちたあふれる後醍醐天皇に対する忠誠の熱血の余滴を子供の正行(まさつら)に分け与えて、将来賊を倒し天皇に忠誠を尽くすように訓話して河内に帰した。
語句の意味
-
- 海 甸
- 海辺の町はずれ ここでは湊川(今の神戸市)の海岸 正成が敗死した場所
-
- 陰 風
- 雨雲の風 陰気な風
-
- 一 腔
- 体中に満ちあふれる
-
- 余 瀝
- 余った滴(しずく)
-
- 児 曹
- 子供たち
-
- 賊 庭
- 「賊」は足利軍 「庭」は屋敷 ここでは陣中
鑑賞
正成の決意と子への期待
起・承句では、湊川における戦いを懐古し、むざむざの死を覚悟に散った賢才武略の勇士として正成を誉め讃えている。
転・結句では、子正行が父訓を奉じての玉砕を暗に示し、その忠誠の跡が歴史に澟として輝いている。直接、子に訣(わか)れるという字句はないけれども、その意は28字に託して的確に表現せしめている。正成の決意と我に続けと子の将来に対する期待が全句に極めて詩的に綴られ、その感動を強く読む者をして胸に訴えている。
備考
この詩は、作者頼山陽35歳の作。楠公父子が桜井に於いて、陣幕の中で、その親子が今生の別れの儀式を行っている図を見て賦したもので本題は「題楠公別子図」であるが、本会では「桜井訣別」と題した。
西では楠正成が、また東では新田義貞が立ち上がり、鎌倉幕府を滅ぼし、後醍醐天皇により親政が始まる、則ち建武の中興である。しかし、建武の中興後九州へ敗走した足利尊氏は、再び勢力を盛り返し10万の大軍を率いて京都へと迫った。正成は帝に和睦を進言するが受け入れられず、多勢に無㔟、勝算のない戦と知りながら決戦場湊川に向かう。途中桜井の駅(大阪府三島郡島本町)で嫡男正行を呼び「父なき後も帝のために身命を尽くすように」と告げ、帝より賜った短刀を正行に授け河内へと帰らせた。これが「桜井の別れ」である。その後父正成は湊川で戦死。子正行は12年後成人し四条畷の戦で戦死する。この親子2代の忠誠の情が、歴史に澟として輝いているのである。
「弔小楠公墓」の詩を参考にされたい。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声九青(せい)韻の腥、馨、庭の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
頼 山陽 1780~1832
江戸後期の儒者・漢詩人・教育者
広島県竹原市の人で、安芸藩儒者・春水の長男として生まれた。名は襄(のぼる)、字は子成、号は山陽。18歳で江戸の昌平黌(しょうへいこう)学問所で学んだ。ただ素行に常軌を逸脱することが多く、最初の結婚は長く続かず家族を悩ませた。21歳で京都に走ったため、脱藩の罪で4年間自邸に幽閉された。しかしこの間読書にふけり、後の「日本外史」の案がなったといわれる。32歳のころから京都に定住し「山紫水明処」という塾を開き子弟の育成と自分の学問に励んだ。子供に安政の大獄で処刑された三樹三郎がいる。享年53。
