漢詩紹介
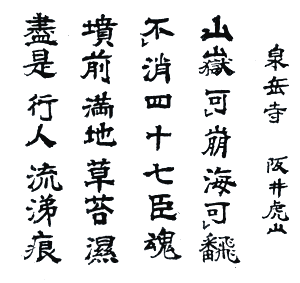
吟者:松野 春秀
2009年9月掲載
読み方
- 泉岳寺 <阪井 虎山>
- 山岳崩る可く 海翻る可し
- 消せず 四十七臣の魂
- 墳前満地 草苔湿う
- 尽く是 行人 流涕の痕
- せんがくじ <さかい こざん>
- さんがくくずるべく うみひるがえるべし
- しょうせず しじゅうしちしんのたましい
- ふんぜんまんち そうたいうるおオ
- ことごとくこれ こうじん りゅうていのあと
詩の意味
山は崩れて無くなることもあり、海がひっくり返って陸となることもあるが、赤穂浪士47人の忠誠の魂は消えて無くなることはない。
今、泉岳寺に来てみると、墓の前やそのあたりの一面は、草や苔が青々と生えて、しっとりと湿っている。定めしこれは、この墓に詣でる人や前を通る人々が、その忠誠に感激して流した涙の痕であろう。
語句の意味
-
- 泉岳寺
- 赤穂浪士の菩提寺 東京都港区高輪(たかなわ)にある名刹(めいさつ)
-
- 四十七臣
- 赤穂浪士の大石良雄(よしたか=内蔵助)ら47人の家臣たち
-
- 満 地
- あたり一面
-
- 行 人
- 往来する人 ここでは参拝する人
-
- 流 涕
- 感激して涙を流す
鑑賞
永久に滅せず四十七士の魂
忠臣蔵で名高い赤穂四十七士の墓が並ぶのが泉岳寺である。作者はこの墓を訪れ当時を懐古して一詩を賦した。
起句の「山岳可崩海可翻」は、かつて鎌倉幕府の三代将軍源実朝が朝廷に忠誠を誓った「山は裂け海はあせなん世なりとも君にふた心わがあらめやも」への意識があったものと思われる。主君滅亡後1年10ヵ月、同志達を統率し武士道の義を貫いた大石内蔵助をはじめ四十七士の魂が今尚人々の心に生き続けていることを作者は実感したに違いない。
事件後300年の歳月が過ぎた今日なお、この泉岳寺の義士の墓に香華の煙が絶えることはないという。
備考
討ち入り後の世相において忠臣蔵なる芝居が大流行した。当時の人々はきっとこの忠義なる四十七士が本懐を遂げた義士に感動し、満たされない自分たちの夢を見つけ、拍手喝采を送ったのであろう。
なぜこれほど、この忠臣蔵の話が日本人に人気を博すのかは、徳川300年間に大名の取り壊しは300ほどあって、皆泣き寝入りしたのに、赤穂藩だけが、無念なる主君の仇を討ったからである。
参考
内蔵助が主君の仇を晴らすのにこだわったのは、日頃の教育の賜物と言える。林羅山に朱子学を学んだ儒者であり兵法家である山鹿素行が10年間赤穂に身を置いていたとき、藩主から依頼を受けて藩士に兵学を教え、内蔵助もその薫陶を受け、その思想に洗脳されたものと思われる。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十三元(げん)韻の翻、魂、痕の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
阪井虎山 1798~1850
江戸後期の儒学者
広島に生まれる。名は華(ひかる)、字は公実、通称は百太郎、虎山と号した。頼春水に学び、春水は彼の 才能の奇抜であることに感心し、将来国を動かす人になるだろうと期待した。文政8年(1825)藩校教授にあるかたわら、一時江戸藩邸に滞在し、松崎慊堂(こうどう)、佐藤一斉等と親交を持った。史論、文章にたけ、家塾「百千堂」には500人の門人を数えた。憂国の志が厚く、善行がたいそう多かった。嘉永3年没す。享年53。著書に「杞憂(きゆう)策」「論語講義」等がある。
