漢詩紹介
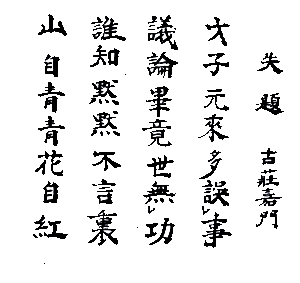
吟者:幡地 滄月
2009年10月掲載
読み方
- 失題 <古荘 嘉門>
- 才子元来 多く事を誤る
- 議論畢竟 世に功無し
- 誰か知らん 黙黙 不言の裏
- 山は自ずから青青 花は自ずから紅なり
- しつだい <ふるしょう かもん>
- さいしがんらい おおくことをあやまる
- ぎろんひっきょう よにこうなし
- たれかしらん もくもく ふげんのうち
- やまはおのずからせいせい はなはおのずからくれないなり
詩の意味
才子といわれている人は昔から物事をやり損なうことが多く、才能にまかせた議論を好む結果、議論倒れになってしまい、結局は世の中に何の利益ももたらさない。
だれが気づいているだろうか、いや誰も気づかない。自然は無言の中に運行し、春ともなれば山々は青々と茂り、花も時を違えずに紅く咲くということを。
語句の意味
-
- 失 題
- 特に題を定めない
-
- 才 子
- 才能豊かで如才ない人
-
- 畢 竟
- つまり 結局
-
- 誰 知
- だれが気づいているだろうか いや誰も気づいていないだろう(反語形)
-
- 不 言
- 無言に同じ
鑑賞
物言わずとも山は青、花は紅
この詩は、才を自負し空しい議論をたたかわせる無念と不言実行を説いている。
起句と承句は、その句だけでは意味が完成せず、二句が対になって初めてその意味が成り立つ、流水対を形成している。
西南戦争で武力による闘争を断念した自由民権論者が再び議論を展開し始めたことに対する、皮肉とも解される。作者自身は、国権党を旗揚げしたほどの国粋主義者で、天皇を中心とする強力な日本を作ることを是としていた。そこで保守派の言う徳育中心の教育論を、議論するだけで実行の伴わない才子の議論だと切り捨てたのであろう。
転句と結句では、天は物言わずして、しかも四季の移りゆくに任せて、山は必ず青々と茂らせ、花は必ず紅く咲かせているではないかと不言実行を説いている。
備考
読み込んだ「論語」の精神
三・四句は「論語」(微子=びし=編)の「天、何をか言わんや、四時行われ百物生ず、天、何をか言わんや」に基づく。また同じ「論語」に「君子は言に訥(とつ)にして行いに敏(びん)ならんと欲す」とある。「不言実行」の難しさは昔からあるのである。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声一東(とう)韻の功、紅の字が使われている。起句は踏み落とし。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
古荘嘉門 1840~1915
明治時代の官僚・政治家
名は惟正(これまさ)、号は火海(かかい)、嘉門は通称である。肥後(熊本県)の藩医の子として熊本城下に生まれる。16歳で木下犀潭(さいたん)の塾に入り、優秀で木門(きもん)の四天王の一人に数えられた。維新直後は佐幕派であったので、しばらく新政府から謹慎を命ぜられたこともある。40歳過ぎには国粋主義者となり自由民権論者に対抗した。政府から信任厚く、明治21年、森有礼(ありのり)文部大臣から第一高等中学校の校長に抜擢された。その後、国会議員、知事、貴族院議員などを歴任し、大正4年没す。享年76。
