漢詩紹介
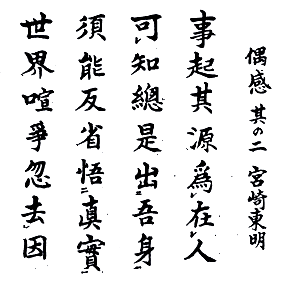
吟者:埜辺 旭洲
2010年3月掲載
読み方
- 偶感(其の二) <宮崎 東明>
- 事起これば其の源 人に在りと為す
- 知る可し総て是 吾が身より出ずと
- 須らく能く反省して 真実を悟らば
- 世界の喧争 忽ち因を去るべし
- ぐうかん(そのに) <みやざき とうめい>
- ことおこればそのみなもと ひとにありとなす
- しるべしすべてこれ わがみよりいずと
- すべからくよくはんせいして しんじつをさとらば
- せかいのけんそう たちまちいんをさるべし
詩の意味
人はいつも、争い事があれば、その原因は相手にあると思いがちである。だがこれは、すべて自分がそのもとをなしていると知らねばならない。
従って、争い事が起きた場合には、常に自分の行いをよく省みて、物事の真の姿を悟るべきである。このようにすれば国と国との争い事などもたちまち解決するはずだ。
語句の意味
-
- 須
- 本来は再読文字の読み方として「須=すべか=らく……因を去るべし」と読み「ぜひとも……しなければならない」 ここでは流水対という形で転句・結句の二句を以てその意を成立させている
-
- 喧 争
- やかましい争い
-
- 忽
- すぐに
鑑賞
自己反省から世界が救える
東明先生の詩には自然の風物や身近な歴史を歌うものが多いが、この詩のように人間のあるべき姿を歌う人生訓めいた詩もある。この詩は、すべての争い事の責任は自分にあるのだという自己反省を重ねていけば、世界の戦争はなくなると明察しておられる。世界のことはともかくとして、処世上の確執で、「相手が悪い」で始まると解決が遠くなることは、多くの人が経験済みであろう。まず自分に落ち度はないかで始まることの大切さを教示されている。まさに至言である。
「反省」の尊さは「論語」学而編にもある。「曾子曰く『吾日に吾が身を三省す。人の為に謀りて忠ならざるか。朋友と交わりて信ならざるか。習わざるを伝えたるか』と」。自分が絶対正しいという思い込み。それがある以上、世界における戦争も繰り返され、終結を望むことは難しい。論語の「過ちは則ち改むるに憚(はばか)るなかれ」に言う、自分が間違っていると思えばまず自己反省することの大切さを学びたい。
備考
この詩は「宮崎東明詩集」第六巻に「偶感其の九十六」として掲載されているが、本会では「偶感 其の二」とした。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の人、身、因の字が使われている。転句は挟み平になっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治・大正・昭和の医者・漢詩家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤澤黄坡(こうは)、書を臼田(うすだ)岳洲、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(すいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会を設立し発展に寄与する。初代会長藤澤黄坡先生没後二代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年82。
