漢詩紹介
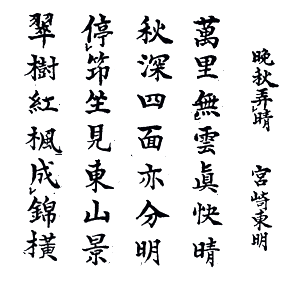
吟者:稲田 菖胤
2010年4月掲載
読み方
- 晩秋晴を弄す <宮崎 東明>
- 万里雲無く 真に快晴
- 秋深くして 四面 亦分明
- 筇を停めて坐ろに見る 東山の景
- 翠樹紅楓 錦を成して横たわる
- ばんしゅうはれをろうす <みやざき とうめい>
- ばんりくもなく しんにかいせい
- あきふかくして しめん またぶんめい
- つえをとどめてそぞろにみる とうざんのけい
- すいじゅこうふう にしきをなしてよこたわる
詩の意味
見渡す空には一点の雲もなく晴れわたり、実によい天気である。秋の気配が深まって、あたりの景色もはっきり見える。
しばらく杖を止めて東山の景色を眺めていると、翠(みどり)の樹々は紅葉を織りまぜて、まるで錦を見ているようである。
語句の意味
-
- 弄 晴
- 「弄」はもてあそぶ ここでは晴れを楽しむ
-
- 亦
- これもまた
-
- 分 明
- はっきりとした
-
- 坐 見
- なんとなしに漠然と見る
-
- 成 錦
- 錦のようになって
鑑賞
生駒山系の紅葉の大壁画
東明先生午後の散歩の折の詩であろう。一読するや、杜牧の「山行」の転句「車を停めて坐に愛す楓林の晩」が連想される。いずこの国も時代も、紅葉は心を慰めるものである。晩秋の快晴の山並は生駒山系だろう。そこに色づいた樹々の美しさはまさに大壁画を見るようである。
転句の「見る」に少しこだわってみたい。この字は「自然に目に入る」というのがもとの意味である。現在はあらゆる場面で多種の意味を伴って使われているので詮索する必要もないのだが、やはりこの詩の「見る」は見逃せない。つまり東明先生は秋空か秋の空気を楽しみにお出かけになった。いくらか歩いて一休みした時、ふと頭を挙げ腰を伸ばすと、生駒山がなんとなく目に入ったという場面である。そこに色づいた樹々の、予想外の美しさに驚き、詩興を感じられたのであろう。
漢詩の小知識
「見る」のいろいろ
見る 目に入る 何となく見る
看る 手をかざして遠くを見る
視る 気をつけて見る
観る 細かに見る
鑑る 芸術作品などを味わい見る
診る 健康具合を見る
以上の説明は一応原則である。また「みる」の漢字は他にもいくつかある。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の晴、明、横の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治・大正・昭和の医者・漢詩家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤澤黄坡(こうは)、書を臼田(うすだ)岳洲、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(すいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会を設立し発展に寄与する。初代会長藤澤黄坡先生没後二代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年82。
