漢詩紹介
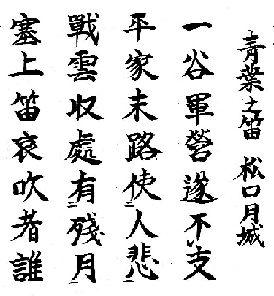
吟者:辰巳快水
2017年9月掲載
読み方
- 青葉之笛<松口月城>
- 一の谷の軍営 遂に支えず
- 平家の末路 人をして悲しましむ
- 戦雲収まる処 残月有り
- 塞上笛は哀し 吹きし者は誰ぞ
- あおばのふえ<まつぐちげつじょう>
- いちのたにのぐんえい ついにささえず
- へいけのまつろ ひとをしてかなしましむ
- せんうんおさまるところ ざんげつあり
- さいじょうふえはかなし ふきしものはたれぞ
詩の意味
一の谷の合戦で平家は奮戦したもののついに支えきれず、その後の平家一族の哀れな最後は聞く人を悲しませる。
その一の谷の戦いが源氏の勝利のうちに終息したころ、明け方の空には残月がかかっていて、平家の陣営のあたりから聞こえてくる笛の音がある。こんな折、哀愁を誘う見事な笛を吹くものはいったい誰なのであろう。
語句の意味
-
- 青葉之笛
- 平敦盛(たいらのあつもり)の持っていた笛の名前 竹製の横笛
-
- 一 谷
- 兵庫県神戸市の鉄拐山(てっかいざん)が海に迫(せ)り出した所
-
- 塞 上
- 「塞」はとりで ここでは平家の陣営 「上」はほとり
-
- 末 路
- 一族が滅びゆく哀れな最後
鑑賞
戦場に流れる笛の音が敵味方なく涙を誘う
寿永3年(1184)2月、源氏と平家の一の谷の合戦において、平家劣勢の戦況のなかでただ一人逃げ遅れ敵軍に捕えられたのは17歳の若武者であった。彼の笛の音が夜明けの浜に流れて敵味方の心に響くものがあったという。敦盛悲話伝説として今に語り継がれている。
二句目には平家が壇の浦に全滅する末路にまで触れて一層悲しみを増幅させている。最後に「誰ぞ」とその名をわざとぼかしたところに、戦場に立つ多くの兵士が笛の主を知らないまま身動きもせずその哀調に聞き入っている姿が想像され、読者を含めて深い物思いに駆られる。
参考
「平家物語」巻九の「敦盛の最期(さいご)」から再現
「源氏軍の熊谷次郎直実(くまがいじろうなおざね)は、平家の逃げ遅れた大将軍と思われる公達(平敦盛)を捕えて切ろうとすると、我が子と同じ年頃の16・7歳の少年ではないか。殺すに忍びないとためらいつつも、手柄を追う源氏の者の手にかかるより、成仏の供養を続けられるのは自分であると涙を流しながら手にかけた。首を包もうとしたらこの若い公達は笛を腰に差していた。そういえば明け方に敵陣から聞こえた優雅な笛の主はこの人であったのか、と思いつつ、首を義経(よしつね)に差し出したところ、義経も周囲の人もだれ一人泣かないものはいなかった。その後、直実は武士を捨て出家した。」因みに、京都長岡の地に法然浄土宗西山派本山として建立された光明寺は、直実の尽力によるものである。
唱歌「青葉の笛」 大和田建樹
一の谷の 軍(いくさ)敗れ
討たれし平家の 公達あわれ
暁寒き 須磨の嵐に
聞こえしはこれか 青葉の笛
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声四支(し)韻の支(し)・悲(ひ)・誰(すい)の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
松口月城 1887-1981
明治から昭和の医師・吟詠家・作詩家・書家
明治20年福岡市有田に生まれる。名は栄太、14歳で松口家の養子となる。18歳で熊本医学専門学校を卒業し、医師の資格を得、世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、書・画の道にも優れ、多くの作品は今もなお郷里の「松口月城記念館」に展示されている。全国規模の詩吟連盟の役員を長く歴任され、昭和49年に吟詠普及振興に尽くした功績により文部大臣表彰を受けた。本会の顧問も長く務められた。享年95歳。
