漢詩紹介
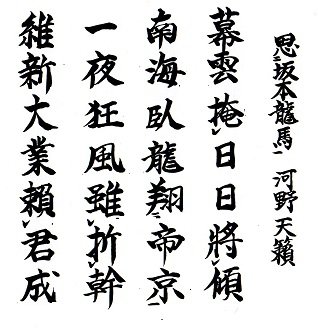
吟者:藤本曙冽
2017年10月掲載
読み方
- 坂本龍馬を思う<河野天籟>
- 幕雲日を掩うて 日 将に傾かんとす
- 南海の臥龍 帝京に翔る
- 一夜狂風 幹を折ると雖も
- 維新の大業 君に頼って成る
- さかもとりょうまをおもう(オ)<こうのてんらい>
- ばくうんひをおおう(オ)て ひ まさにかたむかんとす
- なんかいのがりょう ていきょうにかける
- いちやきょうふう みきをおるといえども
- いしんのたいぎょう きみによってなる
詩の意味
幕府の力も落ちて今にも国運が傾こうとしているとき、土佐の風雲児、坂本龍馬が立ち上がり、新しい国づくりのため、大政奉還を推進すべく京都を駆け巡った。
だがある夜、荒れ狂う風が大樹を吹き折るように、龍馬は明治維新を見ることなく凶刃(きょうじん)に倒れたが、その後、維新の大業が成ったのは、ひとえに龍馬の命を賭(と)しての働きがあったおかげである。
語句の意味
-
- 幕 雲
- 幕府の衰え 作者の造語
-
- 南 海
- 四国の総称 ここでは土佐の国
-
- 臥 龍
- 伏している龍(りゅう) 「三国志」に「諸葛孔明(しょかつこうめい)は臥龍なり」とある 龍馬を孔明になぞらえている まだ世に知られていない大人物 風雲児
-
- 帝 京
- 天子のいる都 京都
-
- 維 新
- 政治の体制が一新され改まる
鑑賞
国民的英雄 坂本龍馬
龍馬は国民的英雄である。志半ばにして凶刃に倒れたことに同情を寄せ、併せて維新の大業に尽くした業績を称えた詩である。比喩を多く用いて詩情に奥深さを表出しているのも魅力になっている。すなわち「幕雲」は幕府の力の下降、「日」は日本、「臥龍」は三国時代の孔明に匹敵する龍馬、「狂風」は近江屋で襲いかかった刺客、「幹を折る」は大人物が倒れる、など。龍馬の豪放な性格や大人物らしさが表出され、同時に作者の龍馬に対する尊敬や親愛の情がうかがわれる。
備考
維新の演出者
本龍馬の生涯は幕末の変動とともにある。郷士(ごうし)という低い身分でありながら、勝海舟を師とし、海外に目を向け海援隊を創設した。後、薩長同盟を実現させて、維新の大業を完遂させる道を開いた。西郷隆盛をして「天下に有志あり。余多く交わる。然(しか)れども度量の大、龍馬に如(し)く者、未だかつて見ず。龍馬の度量や到底測るべからず」と言わしめたほどの人物である。国家構想の「船中八策」はとくに有名で、土佐藩主山内容堂(やまのうちようどう)を動かし大政奉還に導いたといわれる。京都の醤油屋「近江屋」で刺客によって暗殺された。33歳であった。
参考
誰よりも遠望できた「船中八策」の建議
平易に、現代語で列挙する。
1、政権を朝廷に戻すこと。
2、議会を設け、議員たちに議論させて国法を決めること。
3、有能な公卿(くぎょう)や諸侯や武士たちを新政府に迎え、官位や爵位(しゃくい)を与え、既存の有名無実の役人を排除すること。
4、外国との交際は規約を作って当たること。
5、古来の律令(りつりょう)を鑑(かんが)みながら、新しく憲法を制定すること。
6、海軍を拡張すること。
7、親兵を選び、京都を守衛すること。
8、物価は外国と均衡が保てるような法律を設けること。
この八策の精神が明治維新の「五カ条の御誓文(ごせいもん)」に取り入れられた。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の傾(けい)・京(けい)・成(せい)の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
河野天籟 1862-1941
明治後期の教育者・漢詩人
熊本県玉名市に細川藩医河野通伸(みちのぶ)の三男として生まれる。本名は通雄(みちお)といい、天籟は号。明治10年の西南戦争に西郷軍に味方して参戦したが、大腿部に銃弾を受け戦場を退いた。その後、熊本師範学校を卒業した。小学校教員のかたわら作詩に志すこと40年。詩風は自由自在で、漢詩百余編を集録した「孟浪餘滴(もうろうよてき)」を著す。昭和16年5月没す。享年80歳。
