漢詩紹介
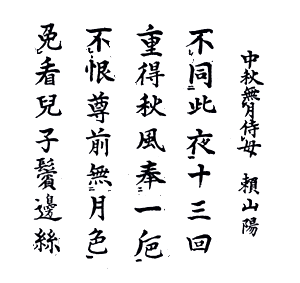
吟者:松尾 佳恵
2010年4月掲載
読み方
- 中秋月無く母に侍す <頼 山陽>
- 此の夜を同じゅうせざること 十三回
- 重ねて得たり秋風 一卮を奉ずるを
- 恨みず尊前 月色無きを
- 看るを免る 児子 鬢辺の糸
- ちゅうしゅうつきなくははにじす <らい さんよう>
- このよをおなじゅうせざること じゅうさんかい
- かさねてえたりしゅうふう いっしをほうずるを
- うらみずそんぜん げっしょくなきを
- みるをまぬかる じし びんへんのいと
詩の意味
母とともに中秋の月見をしなくなってもう13年もたってしまった。今宵は涼しい秋風のもと、ふたたび母を迎えて一杯の酒を差し上げることができた。
(残念なことに天気が悪く)月を見ることができないが、そのために母上の前で、自分の鬢(びん)のあたりの白髪を見られることもなかったのがせめてもの救いであった。
語句の意味
-
- 中 秋
- 「仲秋」と同じ 旧暦8月15日の月見の晩
-
- 侍 母
- 母のおそばに仕える
-
- 重 得
- ふたたび…することができた
-
- 一 卮
- 一つの杯 「卮」の俗字は「巵」
-
- 尊 前
- 尊ぶ人の前 母の前 または酒樽の前
-
- 鬢 辺
- 鬢のあたり(頭の左右側面の髪)
鑑賞
母に心配をかけまいとする孝行息子
山陽は10代20代にずいぶん両親に心配をかけた。彼が母に孝養を尽くすようになったのは父の春水が死んでからである。この詩は山陽の45歳の文政7年(1824)の中秋の夕べ、おりから上京していた母を交え、塾生を集め小宴を開いていた時の作である。40歳のころから山陽は母を京都に招き、吉野や京都の名所を案内しているし、広島にもたびたび帰っているから、この13回というのは、母の膝下(しっか)を離れて以来、母とともには月見の宴をしなくなって満13年経たとみるのが良い。
母を思う詩として流布(るふ)している「送母路上短歌」や「侍輿(じよ)歌」などにもあるように表現が具体的で分かり易い特色がある。「鶏(とり)を聞いて即ち足を裹(つつ)み輿(こし)に侍して足槃跚(はんさん)たり」「輿行けば吾も亦行き 輿止れば吾も亦止る」がそれ。そしてこの詩の後ろの二句など、親に心配をかけまいとする山陽の孝行心と情愛が手に取るように伝わり、実に温かいものを感じる。
参考
母親像の紹介と遺(のこ)した歌二首
母は名を静子と言い、大坂の裕福な儒医の娘として育った。都会育ちのためか快活で大らかで社交を好んだ。香川景樹(かげき)に師事し、国学や和歌を学んだ。そのおかげか和文に巧みで、84歳で死ぬまで58年間を「梅颸(ばいし)(静子の号)日記」として残している。これは今に山陽を知る貴重な資料となっている。このようにたいそう聡明な婦人で、またいたって健康長寿の人でもあった。
命こみ うれしかりけり 老いてのち
再び見つる みよしのの花
不二の根も 近江のうみも 及びなき
君と父との 恵み忘るな
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の回と、上平声四支(し)韻の卮、絲の字が通韻して使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
頼山陽 1780~1832
江戸後期の儒者・漢詩人・教育者
広島県竹原市の人で、安芸藩儒者、春水の長男として生まれた。名は襄(のぼる)、字は子成、号は山陽。18歳で江戸の昌平黌(しょうへいこう)学問所で学んだ。ただ素行に常軌を逸脱することが多く、最初の結婚は長く続かず家族を悩ませた。21歳で京都に走ったため、脱藩の罪で4年間自宅に幽閉された。しかしこの間読書にふけり、後の「日本外史」の案がなったといわれる。32歳のころから京都に定住し「山紫水明処(どころ)」という塾を開き子弟の育成と自分の学問に励んだ。子供に安政の大獄で処刑された鴨厓(おうがい=三樹三郎)がいる。享年53。
