漢詩紹介
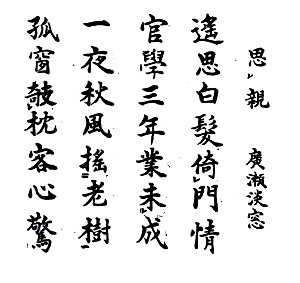
吟者:松野春秀
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 親を思う <広瀬 淡窓>
- 遥かに思う白髪 門に倚るの情
- 官学三年 業未だ成らず
- 一夜秋風 老樹を揺かす
- 孤窓 枕を敧てて 客心驚く
- おやをおもう <ひろせ たんそう>
- はるかにおもオはくはつ もんによるのじょう
- かんがくさんねん ぎょういまだならず
- いちやしゅうふう ろうじゅをうごかす
- こそう まくらをそばだてて かくしんおどろく
詩の意味
遠い故郷では白髪になった両親が門によりかかって自分の帰りを待っていることだろう。藩命によって遊学し、はや3年になってしまったが、学業はまだまだ十分ではない。
ある夜、秋風が吹き荒れ、窓の外の老樹を動かしている。その風の音に耳をすましていると、他国に学ぶ者の心には、はっとするものがあり、一人寂しく眠ろうとしても眠ることができない。
語句の意味
-
- 白 髪
- ここでは自分の老親を指す
-
- 倚門情
- 郷里の村の門によりかかっての両親の思い 出郷の人を待ち望む思い
-
- 官 学
- 藩命によって遊学する
-
- 孤 窓
- 孤独でいる部屋
-
- 客 心
- 旅人の情 ここでは作者自身を指す
鑑賞
学業と「風樹(ふうじゅ)の嘆(たん)」
他郷に遊学しても学業はなかなか成就(じょうじゅ)しない。そうなれば故郷に錦を飾ることもできない。両親はどんどん老いていく。そんなことを心に秘めつつ机に向かう。淡窓自身の懐古ともとれるが、桂林荘の書生たちへの励ましの詩ともとれる。むしろこの2者は融合して区別がなくなっていると解するのが自然である。いずれにしても思いは千々に乱れつつも未来に向かう青年像を知ることができる。
またこの詩には故事や名句を多く引用して詩意の広がりを見せている。つまり「倚門情(きもんじょう)」は「戦国策」に「王孫賈(そんか)の母、(子供の)賈に謂(い)って曰く、汝朝に出でて暮れに帰るに、吾即ち門に倚りて望む。暮れに出でて還らずんば吾即ち閭(りょ=村の門)に倚りて望む」とある。両親が他郷にいるわが子の帰りを待ち望む故事である。「業未だ成らず」は「偶成」の「少年老い易く学成り難し」と同旨で誰もが知る所、「老樹を揺す」の「老樹」は故郷の老親を思わせ、かつ、「風樹の嘆」(親に孝行しようと思った時には既に親はいないという嘆き)の故事につながっている。それらが自然にうまく詠み込まれている。
備考
この詩には大きく2つの解釈がある。1つは作者が故郷の日田(ひた)を出て福岡に遊学した時の作であるとするもの。この説では結句の「客心」が作者自身のことになる。2つめはこの詩が「桂林荘雑詠諸生に示す」の4連作のうち、その3の部分にあることを根拠に、師が塾生の立場になって心情を代詠したとする説。この説では「客心」は塾生となる。つまり詩全体の主語が作者か塾生かの違いが出てくる。いずれにしても若者の勉学の苦労と望郷の思いに揺れ動く心を歌っていることに変わりはない。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の情、成、驚の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
広瀬淡窓 1782~1856
江戸後期の学者・漢詩人・教育者
天明2年豊後(ぶんご=大分県)日田(ひた)の商人の家に生まれる。名は建、字は子基、淡窓と号す。天資は温厚で学を好み、12歳で七言律詩を賦した。16歳で福岡に出て松下筑陰に師事、のち亀井南溟(なんめい)に学んだ。病のため18歳で故郷に帰り、塾を開き「桂林荘」と称した。さらに発展させ「咸宜園(かんぎえん)」と名を変えた。大村益次郎をはじめ多数の門弟を教育した。安政3年11月没す。享年75。育英の功績により名字帯刀を許され、また正五位を贈られる。「遠思楼詩鈔(ししょう)」「淡窓詩話」などの著書がある。
