漢詩紹介
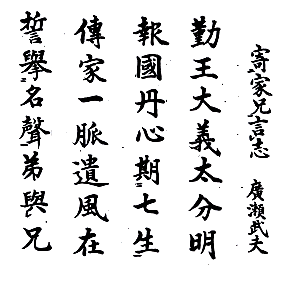
読み方
- 家兄に寄せて志を言う <広瀬 武夫>
- 勤王の大義 太だ分明
- 報国の丹心 七生を期す
- 伝家一脈 遺風在り
- 誓って名声を挙げん 弟と兄と
- かけいによせてこころざしをいう <ひろせ たけお>
- きんのうのたいぎ はなはだぶんめい
- ほうこくのたんしん しちしょうをきす
- でんかいちみゃく いふうあり
- ちかってめいせいをあげん ていとけいと
詩の意味
勤王の大義の大切さはすでに明白なことであり、国に報いる真心は(かの楠正成・正季=まさすえ=ら兄弟の遺訓のように)七度生まれ変わっても逆賊を滅ぼそうとする決意を固めることである。
我が家には代々(南朝の忠臣である)菊池家から変わらぬ家風が脈々と受け継がれているからこそ、この度の日露戦役では兄弟そろって勲功を挙げ、家名を挙げたいと誓うのである。
語句の意味
-
- 勤 王
- 天皇に忠義を尽くす
-
- 大 義
- 人の踏み行うべき大切な道
-
- 丹 心
- まごころ 赤心
-
- 期七生
- 七度生まれ変わっても固く心に決める
-
- 伝 家
- ここでは菊池家の末裔(まつえい)である広瀬家
-
- 一 脈
- 脈々と ひと筋に
-
- 遺 風
- 先祖から後世に伝わっている家風
鑑賞
700年受け継がれてなお輝く忠義の情
この詩は広瀬武夫が日露戦役に出征する際の決意を兄に対して述べたものである。武運をほしいままにし、天皇に報いたいという滅私奉公の人柄がそのまま表れている。この忠義の精神は楠正成兄弟の「七度人間に生まれて朝敵を滅ぼさん」と誓った真心を引き合いに出し、さらに先祖菊池家の末裔としての誇りを堅持して勤王の志を固めている。日露戦役ではまさに誓った通りの活躍があったから、この詩と人物が脚光を浴びている。
この詩に迫力を感じるのは、四字・三字のリズムである。四句とも揃っていて雄々しく軍艦の進行を思わせる調子がある。しかしその勢いの一方で、我々は広瀬中佐が対戦中に無残にも洋上で海の藻屑(もくず)となったことを知っているから、一層この詩に彼への追悼的意味を込めて吟唱するのである。
備考
この詩に対し当時戦艦「大島」の艦長であった兄勝比古は直ちに次の詩を返した。
勤王先考志 勤王は先考の志
決死男子情 死を決するは男子の情
風冷漢江月 風は冷ややかなり漢江の月
徧照弟与兄 徧(あまね)く照らす弟と兄と
(先考=先祖)(漢江=ソウルを流れる大河)
参考
作者は一時軍神とあがめられ、東京神田の万世橋駅前には銅像まで建てられたが今は撤去され、また戦後の歴史教育の中では日露戦争の記述は教科書の半ページほどであり、そこには広瀬中佐はもとより乃木将軍の名さえ出てこない。大分県竹田市には広瀬神社がある。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の明、生、兄の字が使われている。転句と結句の平仄が逆になっている拗体である。(すなわち平起式の前二句と仄起式の後二句を合わせた形)
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
広瀬武夫 1868~1904
明治時代の軍人・漢詩人
明治元年5月、大分県竹田町(竹田市)に生まれる。広瀬家は南朝の忠臣菊池家の後裔(こうえい)として代々岡藩に仕えた。明治24年海軍兵学校を卒業し少尉、28年に海軍大尉。5ヵ年に亘って露国に留学駐在。33年少佐に進む。37年の日露開戦当時は戦艦「朝日」の水雷長であった。旅順港閉塞(へいそく)隊長として「福井丸」を指揮して2回参加。同年黄海上で露軍の流弾に命中され散華(さんげ)した。享年37。同年中佐に昇級。正四位(しょうしい)。軍神と仰がれる。
