漢詩紹介
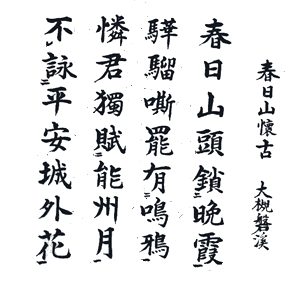
CD①収録 吟者:古賀千翔
2014年8月掲載
読み方
- 春日山懐古 <大槻 磐渓>
- 春日山頭 晩霞に鎖さる
- 驊鰡嘶き罷んで 鳴鴉有り
- 憐れむ君が独り 能州の月を賦して
- 平安城外の 花を詠ぜざりしを
- かすがやまかいこ <おおつき ばんけい>
- かすがさんとう ばんかにとざさる
- かりゅういななきやんで めいああり
- あわれむきみがひとり のうしゅうのつきをふして
- へいあんじょうがいの はなをえいぜざりしを
詩の意味
今、春日山の城跡は空しく夕靄(ゆうもや)に閉ざされて、当時、戦場を駆け回っていた名馬のいななく声も無く、ただ唖々(ああ)と鳴く鴉(からす)の声を聞くのみである。
謙信ほどの英雄にしても、北越の小天地にしか身の置き所が無く、能州の月の名詩を賦したにとどまり、さらには上洛して京都郊外の桜の花を吟詠することができなかったことは、かえすがえすも惜しむべきである。
語句の意味
-
- 春日山
- 新潟県上越市髙田の上杉謙信の居城のあった場所
-
- 晩 霞
- 夕もや
-
- 驊 鰡
- 栗毛の駿馬(しゅんめ)
-
- 能州月
- 謙信の詩「九月十三夜」中の「越山併得能州景」の句を指す
鑑賞
戦国大名上杉謙信にささげる無念の思い
この詩は作者が青年時代、昌平黌(しょうへいこう)を辞して東海・北陸・長崎まで周遊した途次(とじ)、越後の戦国大名上杉謙信の居城を訪ね、往時を懐古したものである。「晩霞に鎖さる」「鳴鴉」「城外の花」は磐渓の存在時を、「驊鰡嘶く」「能州の月を詠ず」は謙信の時代を表現している。それらが詩中にうまく溶け合って妙味を出している。また「月」は秋を、「花」は春を表すから、作者が春の夕もやの中で「そういえば謙信が能登を制圧したのは名月の秋だったなあ」と偲んでいる姿が浮かぶ。
転句の「憐れむ」についてその内容を少し探ってみたい。謙信は天下を取るほどの実力がありながら、信長との決戦を前に49歳で急逝(きゅうせい)し、上洛がかなわず、信長に勝ちを譲ったことに作者が同情したのであろう。武田信玄との川中島の戦いでは、いたずらに時間を費やしたことも悔やまれる。結局、地の利に恵まれない越後という日本の僻地(へきち)でしか軍才を発揮できなかったことと併せて考えれば、上杉びいきの磐渓の無念さが読み取れる。もしすべてのことが満たされたなら、平安京で花を詠ずるのは信長でなく謙信だったかもしれないのだから。
参考
戦の天才と言われていた謙信も病魔には勝てなかった。早い死を予期していたのか枕の下から辞世の言葉がみつかった。
一期の栄一盃の酒
四十九年一酔の間
生を知らずまた死を知らず
歳月ただこれ夢中の如し
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声六麻(ま)韻の霞、鴉、花の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
大槻磐渓 1801~1878
江戸時代末期の儒者
享和元年5月仙台藩医玄沢の次男として江戸木挽(こびき)町に生まれる。字は士広、号は磐渓、諱(いみな)は清嵩(きよたか)。幼い頃から鋭敏であった。昌平黌に学び、のち長崎に赴き蘭学を修行する。帰藩後西洋砲術や儒学に専念した。開国論者で親露排米説を唱えた。明治元年新政府に抵抗した奥羽諸藩挙兵の際に軍国文書司となり捕らえられ、終身禁錮(きんこ)に処せられたが4年4月に釈放され、5月に上京して本郷に隠棲した。同11年6月に没す。享年78。従五位を贈られる。
