漢詩紹介
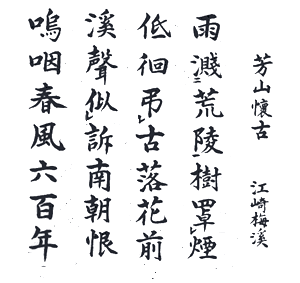
吟者:池田菖黎
2011年2月掲載[吟法改定版]
読み方
- 芳山懐古 <江崎 梅渓>
- 雨は荒陵に濺ぎ 樹は煙を罩む
- 低徊古を弔う 落花の前
- 溪声訴うるに似たり 南朝の恨み
- 嗚咽す 春風 六百年
- ほうざんかいこ <えさき ばいけい>
- あめはこうりょうにそそぎ じゅはけむりをこむ
- ていかいいにしえをとむろオ らっかのまえ
- けいせいうったうるににたり なんちょうのうらみ
- おえつす しゅんぷう ろっぴゃくねん
詩の意味
雨は荒れ果てた陵(みささぎ)に降り注いで、樹々には雲煙がたち込めている。南朝の昔を訪ねてきたが、落花の中、そのあたりを頭を垂れて行ったり来たりするのみである。
吉野川の流れの音は、当時の恨みの数々を訴えるように聞こえるし、吹いてくる春風は、過ぎ去った600年をむせび泣き続けているように思える。
語句の意味
-
- 荒 陵
- 荒れた後醍醐天皇のお墓
-
- 低 徊
- 頭を垂れて行ったり来たりする
-
- 溪 声
- 谷川の水音 ここでは吉野川の流れの音
-
- 嗚 咽
- むせび泣く
鑑賞
吉野川の波音に恨みの声が聞こえる
芳野を冠した詩はこれまで4題出ている。菅茶山、梁川星巌、藤井竹外、河野鉄兜(こうのてっとう)がそれで、いずれも奥深い御陵を訪ね、南朝の衰退と後醍醐天皇の無念を偲ぶものとなっている。この詩も同趣で、あるいは新鮮味がないと言えないこともないが、吉野川の流れる音は恨みを訴えているという擬人法というか象徴的表現はこの詩の良さであろう。吉野川がいくら近いといっても波音が聞こえるはずはない。こういう空想的表現は詩では許されることで、この地方の人は皆、川の流れが絶えることないように永遠に南朝を偲んでいると拡大解釈をすればよい。
参考
不屈の政治家・後醍醐天皇による建武(けんむ)の新政
後醍醐天皇が隠岐の島から脱出し、京に帰還したのは鎌倉幕府が滅亡した1333年であった。いよいよ念願の天皇親政に乗り出すことになり、年号を建武と改めた。政治体制の構想も終え、新宮殿の計画もできたが、鎌倉幕府を倒した足利氏以下の武士たちに十分な恩賞を与えなかったため、またたくまに新政府に反旗を翻す者が続出した。そのため思い通りの政治ができなくて、身の危険にもさらされ、2年を待たず天皇は吉野山に身を隠してしまった。南北朝時代の始まりでもある。それから6年後、天皇は吉野の黒木(くろき)御所で病魔に侵され不帰の人となった。52歳であった。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の煙、前、年の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
江崎梅渓 1888~1969
明治・大正・昭和の学者・漢詩人
尾張(愛知県)一宮市の生まれ。名は明允(めいいん)、通称明治郎、梅渓は号である。同地に機(はた)織り業を営んでいたが、子供に譲り隠居の身分になった。多年服部担風に師事し、詩・書・画を善くす。香草吟社を興し、その居を松韻荘という。清朝その他の中国の詩集を多数蒐集(しゅうしゅう)して人々から羨ましがられた。昭和44年没す。享年81。
