漢詩紹介
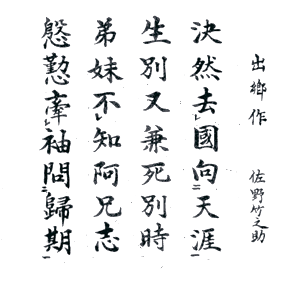
吟者:小坂永舟
2011年2月掲載[吟法改定版]
読み方
- 出郷の作 <佐野 竹之助>
- 決然国を去って 天涯に向こう
- 生別又兼ぬ 死別の時
- 弟妹は知らず 阿兄の志
- 慇懃袖を牽いて 帰期を問う
- しゅっきょうのさく <さの たけのすけ>
- けつぜんくにをさって てんがいにむこオ
- せいべつまたかぬ しべつのとき
- ていまいはしらず あけいのこころざし
- いんぎんそでをひいて ききをとオ
詩の意味
自分は井伊大老の暗殺を決行する為、故郷水戸を去る決心もつき、今、異郷に赴こうとしている。この生別はすなわち死別なのだ。
しかし年端もいかない弟や妹は兄の心も知らず、親しみをこめて袖を引いて、帰りはいつなのかと問うのが哀れである。
語句の意味
-
- 決 然
- 決心したさま
-
- 天 涯
- 空のはて 遠くに隔たった土地
-
- 阿 兄
- 兄さん 「阿」は親しんで呼ぶ時につける語
-
- 慇 懃
- ていねい 親しみを込めて
鑑賞
幕末の志士の心が揺れる家族のきずな
この詩は竹之助が大老井伊直弼を斃(たお)さんと水戸を出発する時の断腸の思いを賦したものである。前二句の激しい闘志、特に「天涯に向こう」は勢いがある。一般には「他国に向かう」とか「異郷に赴く」程度だろうが、「天涯」は果てしない遠い土地を意味するから、江戸のみならず黄泉の国まで示していると容易に察しはつく。さらに重ねるように「生別」と「死別」は同一なのだと言いきる。国を思って命を捧げる幕末の志士の生きざまがここにも表れている。その激しい調子の後で、四句目に兄さんの袖を愛らしく引く弟や妹の姿が静かに穏やかに詠われる。やはり決死の覚悟の最中にも家族を思う情が一筋彼の脳裏を横切ったのであろう。人間竹之助を知る一句である。激から静への音調の変化にいっそう断腸の思いが強調される。読者を神妙にさせるよい詩である
備考
出撃の竹之助の襦袢(じゅばん)の襟に数首の辞世の歌が記されていたという。そのうちの二首
○桜田の 花と屍(かばね)は 散らせども
なにたゆむべき 大和魂
○敷島の 錦の御旗 もちささげ
すめら御軍(みいくさ)の 魁(さきがけ)やせん
参考
桜田門外の変
1858年大老に就任した井伊直弼は朝廷・水戸藩・尊王攘夷派志士の反対を押し切って14代将軍に徳川慶福(よしとみ)を擁立、さらに無勅許(むちょっきょ=天皇の許可が無いこと)でアメリカと条約調印をした。それに反対する水戸浪士を中心とした尊王攘夷派の志士たちが1860年3月に愛宕山に集結し、井伊直弼を江戸城桜田門外において殺害した事件。浪士の多くは討死・自害・逃亡の後、死罪などで終わり、逃げのびたのはわずか2名であった。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声九佳(か)韻の涯と上平声四支(し)韻の時、期の字が通韻して使われている。ただ転句が二六同になっていないので変格である。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
佐野竹之助 1838~1860
明治末期の志士・藩士
水戸藩士佐野兵左衛門光誠の長男として天保9年に生まれた。名は光明、通称竹之助。資性豪宕(ごうとう=気性が雄大で小さなことにこだわらない)にして気節(くじけない意思と信念)を愛した。幼小より武を好み、居合術、砲術を究めた。安政の大獄で多くの志士が処刑されたことに憤慨し、大老井伊直弼を脱藩した水戸藩士ら同志18人で桜田門外において襲撃し、その首を挙げたが、同日重傷のため死去した。享年23。のち正五位を贈られる。
