漢詩紹介
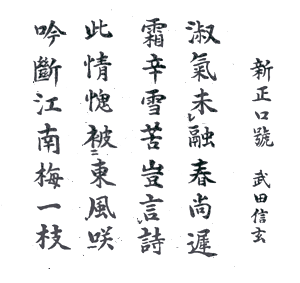
読み方
- 新正口号 <武田 信玄>
- 淑気未だ融けず 春尚遅し
- 霜辛雪苦 豈詩を言わんや
- 此の情愧ずらくは 東風に咲われんことを
- 吟断す江南の 梅一枝
- しんしょうこうごう <たけだ しんげん>
- しゅくきいまだとけず はるなおおそし
- そうしんせっく あにしをいわんや
- このじょうはずらくは とうふうにわらわれんことを
- ぎんだんすこうなんの うめいっし
詩の意味
新年になっても穏やかな気配はまだやってこず、ほんとうの春はほど遠いことだ。霜や雪に傷められた辛さ、厳しさが伴うとあっては、詩を作る気など起こりそうもない。
しかし、このような無風流な気持ちでは春風に笑われるであろう。先ずは江南のほとりで歌った人にあやかって梅一枝の詩を作ってみることにしよう。
語句の意味
-
- 新 正
- 新年に同じ
-
- 淑 気
- 穏やかな春の気 (正月のしとやかな気分)
-
- 融
- 和らぐ
-
- 豈
- どうして……であろうか いや……ないの意で反語を表す
-
- 咲
- 笑と同じ
-
- 吟 断
- 詩を作ること 「断」は前の動詞を強調する助字
鑑賞
遅い北国の春を待つ気持ち
作詩の場所も年代も不明。新年と言っても旧暦だから甲州はまだ雪の中であろう。立春の声を聞くころの作と思える。新年の詩と言えば大橋雲外の「迎新年」のように門松を立ててみんな正装をし、家族が輪になって屠蘇(とそ)を戴く場面が一般的だが、この詩はそういうイメージではない。「新正」も松のうちではなく1月を指すと考えた方が良い。つまりこの詩は新年を祝うものではなく、立春の感懐ぐらいだろう。
1句目の解釈だが、「淑気」を「正月の穏やかな気分」と取り、それがまだまだ解けないでいると訳すと「まだ正月気分が抜けきらないで」という方向に行きがちである。そうではなく「淑気」を「春の穏やかな気分」とし、「融」は「とける」でなく「和らぐ・通じる」の意で、「立春になっても穏やかな春の気配はやってこない」と理解したい。
4句目の着想についてよく話題になる。日本人だから梅の花の歌を借りるなら菅原道真公がいる。伝説によれば信玄は一時政務を顧みないほど作詩にふけったというエピソードがあるから、道真のことは百も承知だろう。であるのになぜ中国の六朝時代(三国時代の説もある)の人にあやかったのか。信玄に聞くしか方法がないが、このあたりを考えるのも面白い。
備考
「江南の梅一枝」は六朝時代の陸凱(りくがい)の詩に基づく。彼が北地(長安)の范曄(はんか)に贈った詩に「……江南有る所無し 聊=いささ=か一枝の春を贈る」(江南には何もないからせめて一枝の梅を折り、春のまだ来ぬ北地に贈ろう)があり、信玄はこの故事を借りて春を待つ心を詠んだ。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声四支(し)韻の遅、詩、枝の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
武田信玄 1521~1573
戦国時代の武将
甲斐源氏の末裔(まつえい)にして、甲斐(山梨県)領主・信虎の長子。名は晴信、後出家して信玄と称し法号を機山という。21歳で父に代わって甲斐の国を託された。政治軍略に手腕があり、信濃(長野県)から攻略をはじめ、越後(新潟県)の上杉謙信と戦うこと数回、雌雄が決しなかった。後北条軍の援助を得て上洛の途につき、徳川家康・織田信長軍をも破り、天正元年野田城(愛知県)を囲んだが、同年4月病のため没した。享年53。
