漢詩紹介
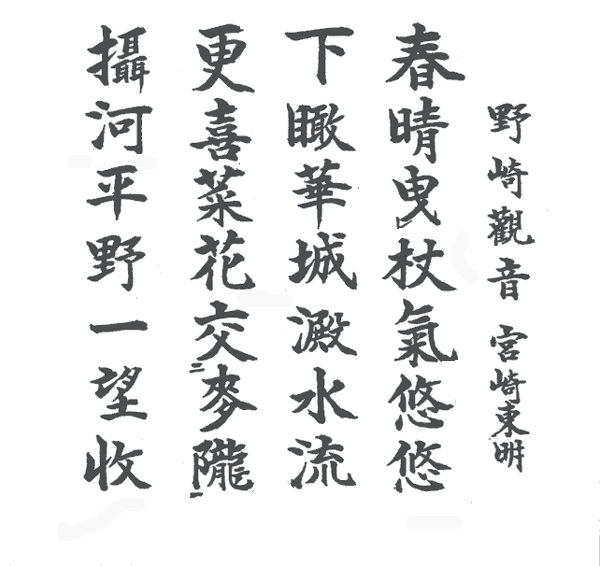
読み方
- 野崎観音 <宮崎 東明>
- 春晴杖を曳いて 気 悠悠
- 下瞰す華城 澱水の流れ
- 更に喜ぶ菜花 麦隴を交え
- 摂河の平野 一望に収まる
- のざきかんのん <みやざき とうめい>
- しゅんせいつえをひいて き ゆうゆう
- かかんすかじょう でんすいのながれ
- さらによろこぶさいか ばくろうをまじえ
- せっかのへいや いちぼうにおさまる
詩の意味
よく晴れた春の日は気ものどかに、杖を曳いて野崎観音にお参りした。境内から見下ろせば、遠く大阪城は霞み、淀川の流れも望まれる。
それに黄色く咲いた菜の花が青々と伸びる麦畑に交じって美しく、摂津と河内の平野が一目で眺められることは何と嬉しいことであろうか。
語句の意味
-
- 悠 悠
- ゆったりとのどかなさま
-
- 下 瞰
- 高いところから見おろす
-
- 華 城
- 大阪城
-
- 澱 水
- 淀川
-
- 麦 隴
- 麦畑
-
- 摂 河
- 摂津の国と河内の国
鑑賞
東明先生と訪れたい野崎観音
大東市にあり、桜と紅葉の名所でもある古刹(こさつ)野崎観音は先生のお宅からほど近い所にあったので折々参詣され、医院の患者やご自身の健康を願われたのではなかろうか。小高い丘の上にある境内の様子や、見事な眺望も手に取るようである。先生の人柄を感じる親しみ深い詩である。
備考
この詩は「林鳥」「月下有懐」とともに「宮崎東明詩集」第一巻に収録され、先生の喜寿記念として同観音の境内にある詩碑に刻まれている。
なお太刀掛呂山先生の賀詩に次のようなのがある。
念彼観音賽野崎 念彼(ねんぴ)観音野崎に賽(さい)し
題将傑句勒豊碑 将(も)って傑句を題して豊碑(ほうひ)を勒(ろく)す
他日隨縁若相過 他日隨縁(ずいえん)若(も)し相過ぎらば
菜花黄裡誦君詩 菜花黄裡(おうり)君が詩を誦(しょう)せん
念彼=あの世の平安を願う 賽す=感謝してお参りする 豊碑=立派な石碑 勒す=刻む
隨縁=縁あって 黄裡=黄色の中 誦=口ずさむ
参考
①もう一つ野崎観音を詠んだ詩(東明詩集巻七)
観音寺在野崎村 観音寺は在り野崎の村
救世大慈古今存 救世の大慈今古に存す
宝玉発揮無限力 宝玉発揮す無限の力
不燃不死是真尊 燃えず死せず是れ真に尊し
②野崎観音とは
正式名は「慈眼=じがん=寺」。奈良時代にインドから来朝した高僧が行基に「野崎は釈迦が初めて仏法を説いた鹿野苑に似ている」と語り、それを受けた行基が白樺で十一面観音を刻んで安置したのが始まりと伝えられている。平安時代に現在の地に移転された。鎌倉時代に本尊を除いて全焼したが、江戸時代の初め再興された。難病治癒(特に婦人病と子授けに御利益がある)の恩徳を受けるため、このころから「野崎参り」が始まった。
③野崎小唄(1番のみ)
野崎参りは屋形船で参ろ どこを向いても菜の花盛り 粋な日笠にゃ蝶々もとまる
呼んでみようか土手の人
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の悠、流、収の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治から昭和の医師・漢詩家・吟詠家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市福島区玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤沢黄坡、書を臼田岳洲、画を中国人方洛(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石、吟詩を真子西洲の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和23年、公益社団法人関西吟詩文化協会の前身・関西吟詩同好会において藤沢黄坡初代会長の没後、2代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年81。
