漢詩紹介
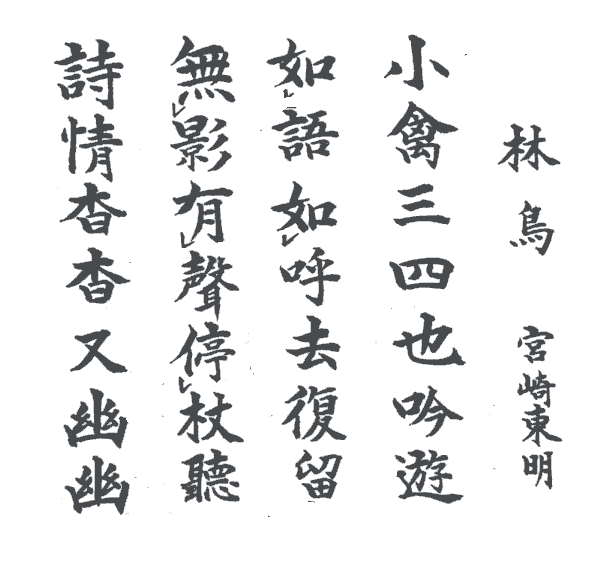
読み方
- 林 鳥 <宮崎 東明>
- 小禽三四 也吟遊
- 語るが如く呼ぶが如く 去り復留まる
- 影無く声有り 杖を停めて聴けば
- 詩情杳杳 又幽幽
- りんちょう <みやざき とうめい>
- しょうきんさんし またぎんゆう
- かたるがごとくよぶがごとく さりまたとどまる
- かげなくこえあり つえをとどめてきけば
- しじょうようよう またゆうゆう
詩の意味
(林の中を歩いていると)たくさんの小鳥のさえずりが聞こえてくる。親子で語り合っているのか、友を呼んでいるのか、こちらで鳴いているのかと思えば向こうの方でさえずっている。
姿は見えないが、鳴く声だけは木の間を通して聞こえてくる。杖を停めて小鳥の声を聞いていると奥深く静かな詩情が湧いてくる。
語句の意味
-
- 吟 遊
- さえずり遊んでいる
-
- 小 禽
- 小鳥
-
- 聴
- 耳を澄ませて聞く
-
- 杳 杳
- 奥深いさま
-
- 幽 幽
- 静かなさま
鑑賞
杜牧がお気に入りの東明先生
この詩は林の中でさえずる小鳥の声に奥深い詩情を催(もよお)されたものである。東明先生には散策の詩をよく見かける。健康のためか詩情を湧かすためか、そぞろ歩きがお好きなようで、初老のころのゆとりある生活と心情がうかがえる。散歩の途中に「杖を停める」語は「晩秋晴を弄す」にも「筇を停めて坐に見る」とあって、一つのスタイルになっている。あるいは杜牧の「山行」にある「車を停めて坐に愛す」がお気に入りなのかもしれない。四句目はさすが風流人である。鳥のさえずりにも奥深く物静かな世界を感じられ、それに似合う詩を作ろうとして首をひねっておられる姿が浮かぶ。
参考
「宮崎東明詩集」発刊の言葉(その一)
余、医業の余暇、漢詩を作ることを楽しみ、逍遥遊社(しょうようゆうしゃ)に入会し、故藤沢黄坡先生に師事すること30年。先生没後は東船山先生、故土屋竹雨先生、あるいは高橋藍川先生、その他社友の教えを受けて今日に至る。この間詩を作ること一千有余編、未だ上達の域に至らずなおなお勉学の途上にあり。
さて今を去る25年前、則ち昭和8年11月、逍遥遊社箕面観楓(みのうかんぷう)詩会席上揮毫(きごう)合作の後、余,偶々(たまたま)これを吟ずれば興さらに深からんことを発言すれば、黄坡先生曰く「然り」と。而して関西大学に真子(まなご)君という吟詩の上手な学生があるに依り、之を紹介するとのお言葉にて、その日は各々清遊をほしいままにして会を閉づ。(次号に続く)
漢詩の小知識
「また」と読む字あれこれ
-
- 也
- 「亦」にほぼ同じ。
-
- 亦
- 「モまた」といわれ、同類があることを表す。例「君も亦私と同じカメラをもっている」
-
- 復
- 「ふたたびのまた」と言われ、同じことが繰り返される場合に用いる。例「50になって復走り始めた」
-
- 又
- 「さらにまた」と言われ、その上にさらに加わることを表す。例「電車に乗り又船にも乗った」
-
- 還
- 「かえるまた」と言われ、同地点に帰ることを表す。例「災害地から無事帰還した」
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の遊、留、幽の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治から昭和の医師・漢詩家・吟詠家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市福島区玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤沢黄坡、書を臼田岳洲、画を中国人方洛(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石、吟詩を真子西洲の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和23年、公益社団法人関西吟詩文化協会の前身・関西吟詩同好会において藤沢黄坡初代会長の没後、2代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年81。
