漢詩紹介
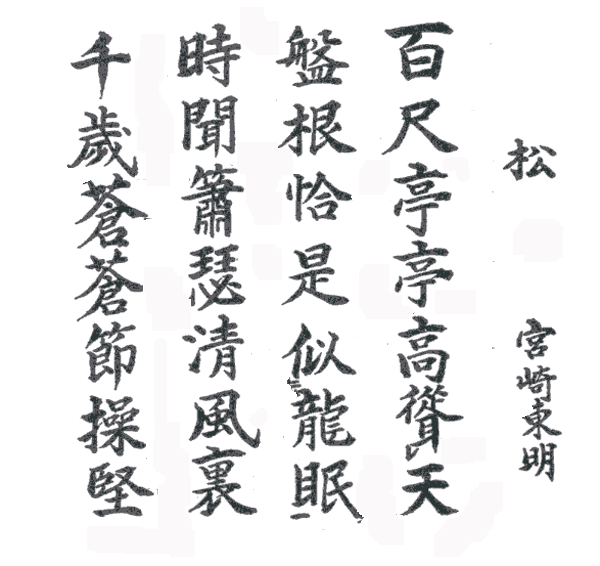
吟者:辰巳 快水
2010年1月掲載
読み方
- 松 <宮崎 東明>
- 百尺亭亭 高く天に聳え
- 盤根恰も是 龍の眠るに似たり
- 時に聞こゆ簫瑟 清風の裏
- 千歳蒼蒼として 節操堅し
- まつ <みやざき とうめい>
- ひゃくしゃくていてい たかくてんにそびえ
- ばんこんあたかもこれ りゅうのねむるににたり
- ときにきこゆしょうしつ せいふうのうち
- せんざいそうそうとして せっそうかたし
詩の意味
百尺もあるかのような松が天高く枝を広げて聳え立ち、根はちょうど龍が眠ってわだかまっているようである。
時として笛や琴の音のように吹いてくる清らかな風のうちに、春夏秋冬青々として、いつまでも変わらず節操の堅いことを思わせている。
語句の意味
-
- 亭 亭
- 高く聳え立つさま
-
- 盤 根
- わだかまっている木の根
-
- 簫 瑟
- 笛や琴
-
- 蒼 蒼
- 青々
鑑賞
松に託された長寿節操の姿
松は針葉樹で、竹、梅とともに寒に耐える故に「歳寒の三友」と言われる。作者が松の長寿、節操の堅いことを称えたもの。こういう詠物詩は必ずしもそれが比喩しているものを探らなくてもよいが、この詩の場合、明らかにある種の人物像が語られている。一句目は天に聳えるような近づき難い気高い人物、二句目は伏龍の如き風雲児を、三句目は松に風と楽器の音という組み合わせで風雅な人物の一面を、四句目はいつまでも若々しく、しかも節義ある高徳な君子を思わせる。「論語」の子罕(しかん)編にも「歳寒然る後に松柏の凋(しぼ)むに遅るるを知る」という有名な一文がある。辞書にも「歳寒松柏」という熟語があって、松と伯が長寿と節操の堅さを示すというのは昔から変わらない。東明先生は改めてこのことを呼びかけたかったのであろう。
なお、「歳寒の三友」の熟語は、現代では、衰えた世に(不遇な環境に)友とすべき3つのもの」という意味で使われる。
参考
「宮崎東明詩集」発刊の言葉(その二)
約1週間後、黄坡先生は真子武晴氏を同伴して拙宅(せったく)に来られたり。爾後吾々夫妻は毎週木曜日の午後拙宅に於いて真子氏の指導により、吟詩の稽古をすることになれり。暫(しばら)くして吟詩は健康上又社会教育上最もよきものなることを悟り、会を創立して大衆に広めんことを主張せり。ここにおいて昭和9年1月7日拙宅において小生夫妻に真子先生を加えて7人が発起人となり、吟詩会を創立し、その名を関西大学吟詩部より始まりたるにより「関西吟詩同好会」と称し、当時関西大学の漢文の教授藤沢黄坡先生を初代会長に仰ぎ、余は其の副会長となり、吟詩教本を発行して専(もっぱ)ら会の経営に努め、当時の内務大臣安達謙蔵氏を顧問に迎ふ。(次号に続く)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の天、眠、堅の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治から昭和の医師・漢詩家・吟詠家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市福島区玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤沢黄坡、書を臼田岳洲、画を中国人方洛(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石、吟詩を真子西洲の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和23年、公益社団法人関西吟詩文化協会の前身・関西吟詩同好会において藤沢黄坡初代会長の没後、2代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年81。
