漢詩紹介
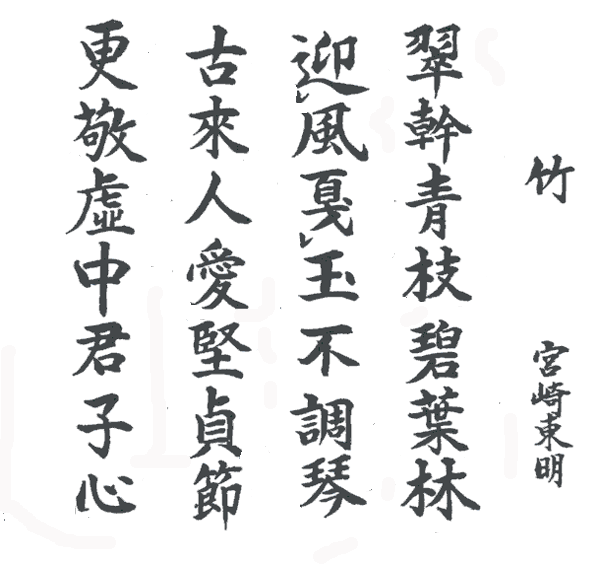
読み方
- 竹 <宮崎 東明>
- 翠幹青枝 碧葉の林
- 風を迎え玉を戛つ 不調の琴
- 古来人は愛す 堅貞の節
- 更に敬う虚中 君子の心
- たけ <みやざき とうめい>
- すいかんせいし へきようのはやし
- かぜをむかえたまをうつ ふちょうのこと
- こらいひとはあいす けんていのせつ
- さらにうやもオきょちゅう くんしのこころ
詩の意味
青々としてすくすく伸びる竹の林、その静かなたたずまいの中に吹く風は幹をならし、不規則な琴の音(ね)のような音(おと)を立てている。
竹は昔から貞節の堅いたとえに用いられ、人に愛され、さらに腹中何物もない清らかな君子の心にも比して敬愛されている。
語句の意味
-
- 翠 幹
- 青々とした幹
-
- 戛 玉
- 玉を軽く打つ
-
- 不調琴
- 調律の調わない琴の音
-
- 虚 中
- 腹中何もないこと
鑑賞
竹は三君子の1つ
竹・松・梅はともに寒に耐える故に「歳寒の三友」と言われる一方で、中国古典では、「三君子」ともいわれ、めでたいもの、優れたものとされている。竹のどこが優れているのか。まず、まっ直ぐに天に向かって伸びていること。人物で言うなら志がまっ直ぐで未来を志向し、強い意志を持つ人。次に節があること。それぞれの場面で節度がありけじめを尊ぶ人。二君に仕えたりするような不貞は絶対しない。3つ目は中が空洞なこと。これは虚心坦懐で、邪心を持たず心が清らかであることに通ずる。そう思いながら竹林を眺めると、改めて心が引き締まりそうである。
漢詩の小知識
「あお・みどり」の字の区別は
-
- 「青」
- 春の空の色 ブルー
-
- 「蒼」
- 少し濃い青色 濃いブルー
-
- 「緑」
- 黄と青の中間 薄いグリーン
-
- 「翠」
- もえぎ色 ネギの萌え出る色 薄いグリーン
-
- 「碧」
- 濃い青色 エメラルド色
参考
「宮崎東明詩集」発刊の言葉(その三)
爾後3年にして会員4万人を突破するの盛況となる。真子武晴先生は西洲(さいしゅう)と号し、宗師範となる。関西大学を卒業後、昭和16年大東亜戦争に応召、昭和20年ビルマにおいて戦死せらる、真に哀惜の極みなり。その後八木哲洲先生吟詩の指導に当たりしが、戦争のため一時会員四散し、会は衰微の状態となり、更に加ふるに昭和23年、会長藤沢黄坡先生御病死の悲しみを見るに至る。昭和24年5月、余第2代会長となり、八木哲洲先生を副会長兼宗師範に推薦し、会の再発足を計り、5年を経て漸く会員千名を数ふるに至る。然るに八木哲洲先生突然病死の悲しみに接す。爾後伊豆丸鷺洲氏を副会長に推薦し、三浦華洲氏を初め多くの本部理事師範並びに会員の御協力により現在(昭和34年)漸く会員5千名に達す。(次号に続く)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声十二侵(しん)韻の林、琴、心の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治から昭和の医師・漢詩家・吟詠家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市福島区玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤沢黄坡、書を臼田岳洲、画を中国人方洛(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石、吟詩を真子西洲の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和23年、公益社団法人関西吟詩文化協会の前身・関西吟詩同好会において藤沢黄坡初代会長の没後、2代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年81。
