漢詩紹介
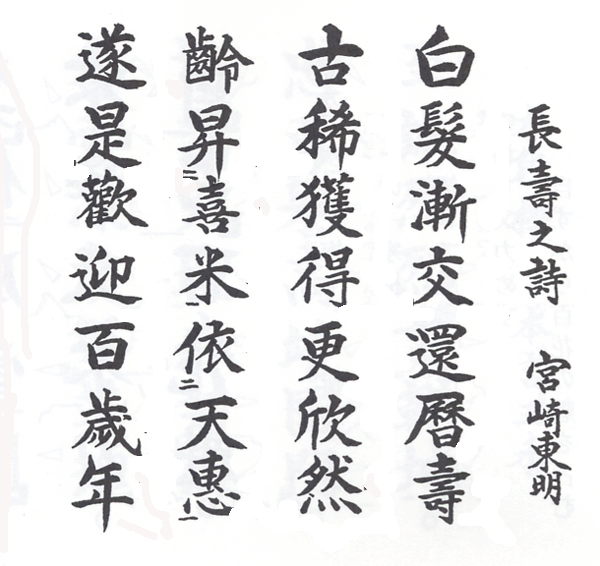
読み方
- 長寿之詩 <宮崎 東明>
- 白髪漸く交ゆ 還暦の寿
- 古稀獲得して 更に欣然
- 齢喜米に昇るは 天恵に依る
- 遂に是歓び迎う 百歳の年
- ちょうじゅのし <みやざき とうめい>
- はくはつようやくまじゆ かんれきのじゅ
- こきかくとくして さらにきんぜん
- よわいきべいにのぼるは てんけいによる
- ついにこれよろこびむこオ ひゃくさいのとし
詩の意味
還暦の年を迎えるころには頭には白髪がちらほら交じってきたが、いつの間にか70歳まで生きられて、一層嬉しい限りである。
喜寿米寿に達するのは天の恵みであって、さらに100歳を迎えることができるならば、本当に喜ばしいことである。
語句の意味
-
- 還 暦
- 60歳
-
- 古 稀
- 70歳
-
- 欣 然
- 喜ぶさま
-
- 喜 米
- 喜寿77歳 米寿88歳
-
- 天 恵
- 天の恵み
鑑賞
100歳以上にも異名がほしい。
本会の教本に長寿を詠う詩が意外と少ない。この詩は貴重な1詩である。詩中に年齢を表す還暦・古稀・喜寿・米寿の4つが出て、残るは傘寿・卆寿・白寿であるが、すべてを詠み込むと詩が成り立たなかったであろう。一読して理解できる。多くの人は、できれば100歳まで生きたいと思っているだろうから東明先生が代弁してくださったといえる。座右の詩としても叶う。平均寿命が上昇した平成のこの頃、100歳以上の人が万を数えるとか。105歳や110歳の異名がほしい。東明先生は81歳で逝かれたが当時としては長寿を保たれた方である。
備考
東明先生のもう一つの晩年に詠まれた詩
-
- 我達今年寿老人
- 我達す今年寿老人
-
- 毎朝自喜是天仁
- 毎朝自ら喜ぶ是れ天仁
-
- 余生幾歳若人問
- 余生幾歳若し人問はば
-
- 無慾此身唯任神
- 無慾の此の身唯神に任せん
漢詩の小知識
年齢の異名
- 志学=15歳
- 而立=30歳
- 不惑=40歳
- 知命=50歳
- 耳順=60歳
- 還暦=60歳
- 従心=70歳
- 古稀=70歳
- 喜寿=77歳
- 傘寿=80歳
- 杖朝=80歳
- 米寿=88歳
- 卆寿=90歳
- 白寿=99歳
参考
「宮崎東明詩集」発刊の言葉(その四)
本年(昭和34年)9月27日大阪中之島中央公会堂に於いて、恩師諸先生先輩並びにその他物故師範等の感謝の会を兼ね、創立25周年記念吟詩大会を盛大に開催するの運びとなる。この機会に大会準備委員会の希望に依り拙作の一部を発表、小冊子を刊行し記念品として大会当日に会員に分与することとなれり。何分にも突然の申し出にて掲載するところの詩篇を一々推敲(すいこう)するの暇なく、甚だ未熟者なれど、会員が漢詩を吟じまた漢詩を作る上に於いて、多少なりとも御参考になれば幸甚の至りなり。ここに詩集第1巻の発刊に当たり一言以て序となす。
昭和34年7月15日
於 五楽庵 宮崎東明 71歳 (終わり)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の然、年の字が使われている。起句は踏み落とし。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
宮崎東明 1889~1969
明治から昭和の医師・漢詩家・吟詠家
明治22年3月河内の国四条村(現在の大東市)に生まれる。名は喜太郎、東明は号。京都府立医学専門学校を卒業、大阪市福島区玉川町に医院を開く。医業の傍ら詩を藤沢黄坡、書を臼田岳洲、画を中国人方洛(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石、吟詩を真子西洲の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和23年、公益社団法人関西吟詩文化協会の前身・関西吟詩同好会において藤沢黄坡初代会長の没後、2代目会長に就任。昭和44年9月没す。享年81。
