漢詩紹介
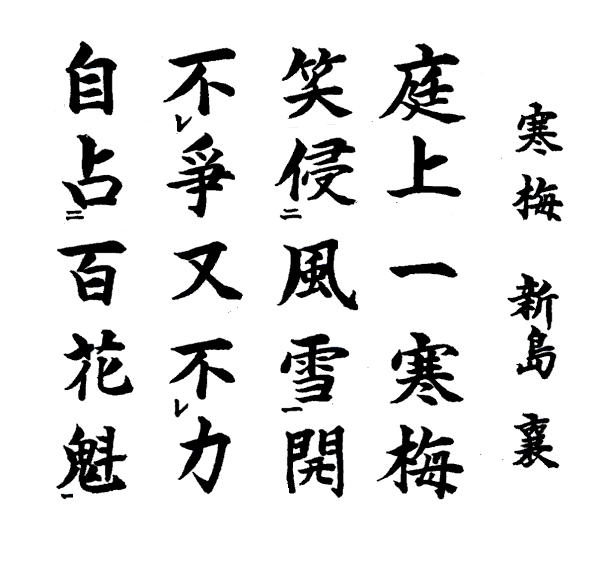
吟者:谷﨑奘皚
2021年8月掲載
読み方
- 寒 梅 <新島 㐮>
- 庭上の 一寒梅
- 笑って風雪を 侵して開く
- 争わず 又力めず
- 自ずから百花の 魁を占む
- かんばい <にいじま じょう>
- ていじょうの いちかんばい
- わらってふうせつを おかしてひらく
- あらそわず またつとめず
- おのずからひゃっかの さきがけをしむ
詩の意味
庭先にある一本の早咲きの梅が厳しい風や雪の寒さにもめげず笑うがごとくに開いている。
一番咲きを争うこともなく、また特に努力するでもないが、それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている。まことに謙虚な姿である。
語句の意味
-
- 庭 上
- 庭先
-
- 侵
- ものともしない めげず
-
- 不 力
- ことさらに励んで努力するでもなく
-
- 魁
- 先駆け 先んじる
鑑賞
学校・同志社こそ学問界の魁であろう
この詩も詠物詩であるが、人の生き方を教示する教訓詩ともなっている。厳しい環境の中で困難や試練に耐えて、しかも己の分を守りながら信念を遂げていく。その結果が先覚者と呼ばれる人になる。すなわち作者の体験がほとばしり出た作品である。
幕末の動乱で作者の出身地、上州(群馬県)も平穏ではなかった。未来に目覚めていく中、彼はキリスト教義こそ人々の心を安らかにすると考えた。まだ朱子学優先で、キリスト教は禁教であるという余波が残る明治初期に欧米思想を広めようとするのは、まさに風雪を侵すと同意であろう。学校設立の資金難、教師の確保、生徒の募集などの苦難も妻とともに無理をせず地道に解決していったのは、不争不力が信条であったからである。その結果同志社が創立された。学問界における魁に他ならない。
参考
中国にもある、寒梅を詠う詩
-
- 「梅花」
- (宋)王安石
-
- 牆角数枝梅
- 牆角(しょうかく)数枝の梅
-
- 凌寒独自開
- 寒を凌(しの)いで独り自から開く
-
- 遥知不是雪
- 遙かに知る是れ雪ならざるを
-
- 為有暗香来
- 暗香有りて来たるが為なり
牆角=垣根の角(かど)
承句の表現がよく似ているので、新島㐮はこの詩に感化・影響されたと思われる。
詩の形
仄起こり五言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の梅、開、魁の字が使われている。なお五言絶句では起句は韻を踏まないのが普通である。また転句は下三連になっていて作詩の原則に沿わないので古体詩に分類する説もある。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
新島 㐮 1843~1890
江戸末期から明治時代の宗教家・教育者
天保14年正月、上州(群馬県)安中藩の江戸一ッ橋邸で生まれた。父民治は藩の右筆(書記役)。幼児期から漢学を修め、蘭学は杉田玄白について学んだ。21歳の時聖書に触れて感激、翌年幕府の禁を犯して渡米し、神学・理学を学ぶ。明治4年、岩倉具視が大使として訪米した折には案内役として欧州にも赴いた。明治7年帰国後、キリスト教主義の学校を目指し、京都に同志社を開き、さらに大学にすべく奔走中病に倒れた。明治23年没す。享年48。
