漢詩紹介
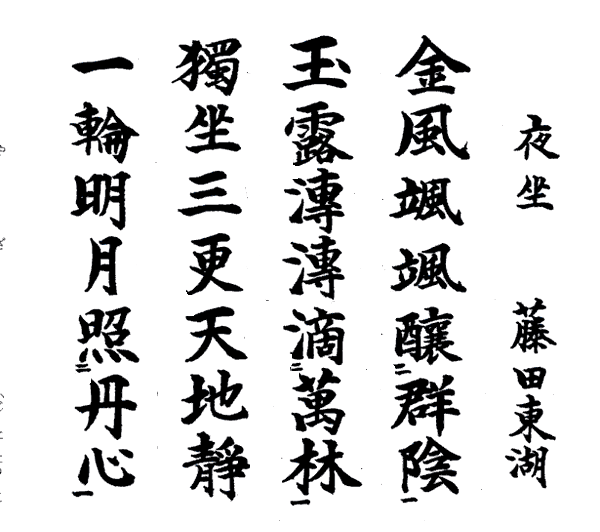
読み方
- 夜 坐 <藤田東湖>
- 金風颯颯として 群陰を醸し
- 玉露溥溥として 万林に滴る
- 独り坐すれば三更 天地静かなり
- 一輪の明月 丹心を照らす
- や ざ <ふじたとうこ>
- きんぷうさっさつとして ぐんいんをかもし
- ぎょくろたんたんとして ばんりんにしたたる
- ひとりざすればさんこう てんちしずかなり
- いちりんのめいげつ たんしんをてらす
詩の意味
サーと吹き抜ける秋風が梢(こずえ)を鳴らし、月の光による無数の陰と玉のような露は多く林全体にしたたっている。
この静寂の中に独り黙座すれば、真夜中の中天にかかる明月は、わがまごころを照らすかのように皎々(こうこう)と輝いている。
語句の意味
-
- 金 風
- 秋風
-
- 颯 颯
- 風の吹く音の形容「ささ」は謡曲高砂『相生の松風〝ささ〟の声ぞたのしむ』より
-
- 群 陰
- 多くの陰
-
- 溥 溥
- 露の多いさま
-
- 三 更
- 夜の12時前後
-
- 丹 心
- まごころ
鑑賞
さて、黙座して考え続けたことは何であったか
この詩は、東湖39歳のころのもので、当時水戸藩が外国船の接近に対し武器の生産と備蓄を盛んにしていることが幕府を脅かす政策と取られ、不快感を与えた結果になり、藩主斉昭とともに藩邸に蟄居(ちっきょ)させられていたのである。前二句は騒然たる物情を述べているが、比喩(ひゆ)が隠されているようでもある。「金風」は外国船がしきりに日本に近づいている不穏な情勢とも思えるし、「玉露」は各地で起こり始めた尊王攘夷派の面々の行動かもしれない。そうした世情の中で、彼は幽囚の身でありながら、どこまでも日本の進路は朝廷による政治より他にないと考えている。そのため今我々は何をすべきかと、ひとり秋の夜に明月を眺めながら悶々(もんもん)と問い続けている。国を思うことに対して一点の曇りもないのは自分だけであると信じ、黙座しているのであろう。
備考
1844年ころと言えば
-
- 1804
- ロシア船が長崎に来航
-
- 1808
- イギリス船が長崎に接岸
-
- 1811
- ロシア船が函館に寄港
-
- 1824
- イギリス漁船が鹿児島に上陸
-
- 1837
- アメリカ船「モリソン号」を浦賀で撃沈
-
- 1842
- アヘン戦争で日本に脅威が及ぶ
-
- 1844
- オランダ船が開国を要求
ペリー艦隊の浦賀寄港はその10年後である。
参考
同時期の作「志を言う」
- 俯思郷国仰思君 俯しては郷国を思い仰いでは君を思う
- 日夜憂愁南北分 日夜憂愁南北に分かる
- 惟喜閑来耽典籍 惟だ喜ぶ閑来典籍に耽るを
- 錦衣玉食本浮雲 錦衣玉食本浮雲
- 郷国=水戸 南北分=南は江戸幕府 北は水戸藩
- 閑来=暇である 錦衣玉食=贅沢な暮らし 本=元来
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十二侵(しん)韻の陰、林、心の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
藤田東湖 1806~1855
幕末期の水戸藩士・学者
尊王攘夷推進派の巨頭。名は彪(たけき)、字は斌卿(ひんけい)、東湖は号。幼名は武次郎、虎之介と称し、後誠之進の名を賜る。水戸藩儒官藤田幽谷の子で文武の修練に励み、父の死後一時「彰考館」の総裁代理となる。藩主斉昭を助け藩政改革に尽力。藩校「弘道館」を設立し、水戸学を振興しその中心人物となった。「弘道館記」は東湖の草案による。安政2年の大地震の時母親を助けようとして逃げ遅れ圧死した。享年50。「回天詩史」他著書多し。
