漢詩紹介
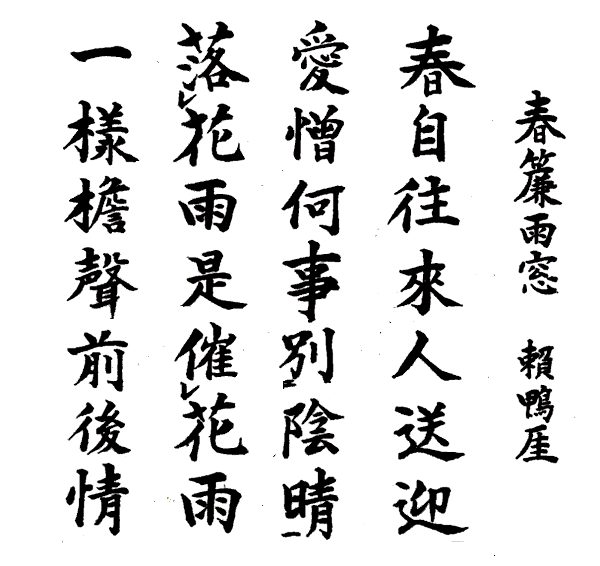
CD①収録 吟者:谷崎奘皚
2014年8月掲載
読み方
- 春簾雨窓 <頼 鴨厓>
- 春は自ずから往来し 人は送迎す
- 愛憎何事ぞ 陰晴を別つ
- 花を落とすの雨は是 花を催すの雨
- 一様の檐声 前後の情
- しゅんれんうそう <らい おうがい>
- はるはおのずからおうらいし ひとはそうげいす
- あいぞうなにごとぞ いんせいをわかつ
- はなをおとすのあめはこれ はなをもよおすのあめ
- いちようのえんせい ぜんごのじょう
詩の意味
春は自然にやってきて、いつともなく去っていく。我々はそれをそのまま自然に送り迎えすればよいのである。それなのに人は晴れたといっては喜び、曇りだといっては恨むように区別するのは何としたことだろう。
同じ雨でありながら花を散らす雨は、花を促し咲かせた雨でもある。同じ軒の雨だれの音も、聞く時によっては好ましい音、憎らしい音と、このように違った情を催させるのである。
語句の意味
-
- 春簾雨窓
- 簾(すだれ)越しに春雨を眺めながらの思い
-
- 愛 憎
- 喜んだり憎んだり
-
- 陰 晴
- 曇りと晴れ
-
- 催
- 促(うなが)す
-
- 檐 声
- 軒端にしたたる雨の音 「檐」は軒
-
- 前後情
- 花の咲く前と咲いた後の気持ち
鑑賞
自然は人に対し公平に害と恵みを与えている
窓の簾ごしに降りしきる雨を恨めしく眺め、人はこの雨が美しく咲いた花を散らせたといって憎み、又、半面考えるに、この雨によって花や実を育ててくれたのだと喜び楽しむのである。
人間の力では到底大自然をどうこうできるものではない。しかし人というものは身勝手なもので、つい自分の都合に合わせて考えるのであろうか。この詩の転句の「花を落とすの雨は是花を催すの雨」は、自然の恵みについて言い当てている名言である。
当時、世は尊皇か攘夷かで騒然としていた。攘夷派の鴨厓は何度も取り調べを受けた。幕府役人たちの言動は人により日によって異なる。わずかな情報を鵜呑(うの)みにし、精査しようともしない。そういう態度に激しく憤(いきどお)った日もあったが、素直に聞ける日もあった。だから自分もそうだが、役人たちもこのことをしっかり心に銘記して、常に全体を観ることのできる目と心を持ちたいものだと願っているようでもある。
備考
極刑に処せられた理由
確かに30歳ころは幕府を批判し勤皇攘夷派と交わっていた。しかし彼の指導役は梅田雲浜や梁川星巌であって、かれは先導役ではなかった。では極刑の理由は何であったのか。それは幕府が「梁川星巌方に参会(さんかい)いたし頼三樹三郎・池内陶所(いけうちとうしょ)・梅田雲浜ら右4人は反逆の四天王と自称いたし候」との情報を得て、それを鵜呑みにし、よく吟味せず処刑したのであった(国史大辞典より)。梅田雲浜は獄死し、梁川星巌は処刑の前に病死した。池内陶所は死刑から外れている。鴨厓の刑には不明な点が多い
参考
①作者を山陽の第三子とするのは後妻の理恵の子としての数えによるのであって、先妻淳子の子を加えれば四男
②獄中作の和歌
③江戸護送中の和歌
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の迎、晴、情の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
頼 鴨厓 1825~1859
幕末の詩人・儒者・志士
頼山陽の第三子として京都三本木町に生まれる。名は醇(じゅん)、字は子春(ししゅん)、通称は三樹または三樹三郎と称し、鴨厓、古狂生と号した。18歳の時江戸に遊学し昌平黌(しょうへいこう)にて学ぶ傍(かたわ)ら、佐藤一斎・梁川星巌らと交流精研する。勤王の志厚く京都に帰り、星巌、梅田雲浜らと尊皇攘夷の大策を画(かく)するも、安政の大獄に捕らわれ、吉田松陰、橋本左内らとともに安政6年10月小塚原で刑死す。その刑に臨むや従容(しょうよう)として一首賦す(B1-26号・獄中作)。享年35。
