漢詩紹介
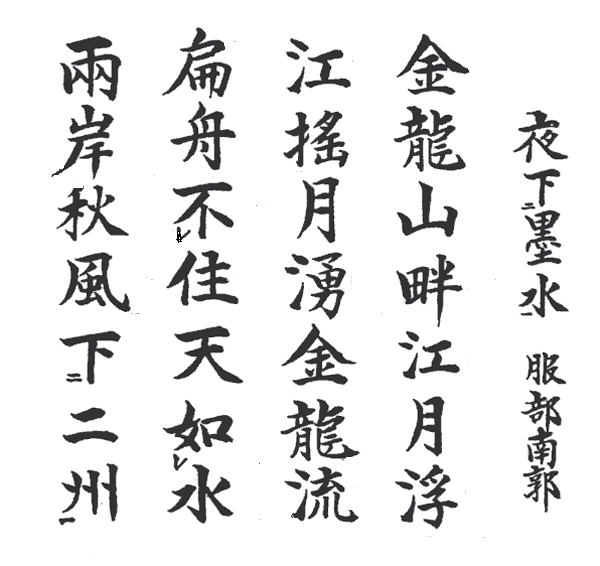
CD④収録 吟者:中谷淞苑
2016年2月掲載
読み方
- 夜墨水を下る <服部 南郭>
- 金龍山畔 江月浮かぶ
- 江揺らぎ月湧いて 金龍流る
- 扁舟住まらず 天水の如し
- 両岸の秋風 二州を下る
- よるぼくすいをくだる <はっとり なんかく>
- きんりゅうさんぱん こうげつうかぶ
- こうゆらぎつきわいて きんりゅうながる
- へんしゅうとどまらず てんみずのごとし
- りょうがんのしゅうふう にしゅうをくだる
詩の意味
金龍山のほとりを流れる隅田川に月影が浮かんでいる。水の流れに連れて月光の砕け散るさまは、ちょうど江中に月が湧いて金色の龍が流れてゆくようである。
私の乗る小舟は流れて留まることもなく、天と水が一つになったような美しい眺めの中を進み、武蔵と下総(しもふさ)の境のあたりを両岸の秋風に送られて下ってゆくのである。
語句の意味
-
- 墨 水
- 隅田川 墨田川とも書く
-
- 金龍山
- 金龍山浅草寺の山号
-
- 江 月
- 川の上を照らしている月
-
- 扁 舟
- 小舟
-
- 二 州
- 武蔵の国と下総の国(ここにかかるのが両国橋)
鑑賞
揚子江ほどにも雄大な隅田川の光景
秋の夜に隅田川に小舟を浮かべ、当時の武蔵野ののどかな風景を詠じた詩である。世に「墨江(ぼっこう)三絶」と評されている。南郭の詩は「擬古詩=ぎこし」(漢・魏の中国の古い時代、素朴で力強い詩を模範として作った詩のこと)で李白の「古風」と題された59篇の連作の影響であろうか。たとえば二句目は李白の「峨眉山月半輪の秋 影は平羌江の水に入って流る」や杜甫の「旅夜書懐」の「月湧いて大江流る」などが意識に上る。後半は「君を思えども見えず渝洲に下る」と隅田川を長江のように歌い、情景をよく似せている。このように擬古詩を勧めたのが南郭の師荻生徂徠(おぎゅうそらい)で、範とするところは「唐詩選」で、それを金科玉条としているので詩風が似てくるのである。
夜小舟に乗って隅田川を下るのは文人墨客(ぼっかく)の好むところであったらしく、多くの詩が残っている。たとえば永井荷風の「墨上春遊」には酒を携えて料亭に向かう墨江情緒が粋に歌われている。(参考「日本人の漢詩」石川忠久)
参考
他の「墨江三絶」の紹介
ひとつは高野蘭亭の「月夜三叉江に舟を泛かぶ」だが、本会に採用されているので省略する。平野金華を加え、3人とも徂徠の門下である。
早発深川 早(つと)に深川を発す 平野金華
月落人煙曙色分 月落ち人煙曙色分かる
長橋一半限星文 長橋一半星文を限る
連天忽下深川水 天に連なって忽ち下る深川の水
直向総州為白雲 直ちに総州に向かって白雲と為る
(意解)月が沈み家々の朝餉(あさげ)の煙が上り、あたりの景色もはっきりしてきた。振り仰ぐ大橋(永代橋)は天を半分に截(た)ち、星座を分けている。天に連なる深川の水を下っていくと、まっすぐ向こうには白雲の湧く総州である。
詩の形
平起こり七言絶句の形のようであるが、前半は同字重出と平仄が不揃いなので拗体とする。下平声十一尤(ゆう)韻の浮、流、州の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
服部南郭 1683~1759
江戸時代中期の儒者・漢詩人
名は元喬(もとたか)、字は子遷(しせん)、通称小右ヱ門(こうえもん)、南郭は号。他に周雪(しゅうせつ)、観翁(かんおう)の雅号がある。天和3年京都に生まれる。父の死により14歳で江戸に移り、荻生徂徠に師事し、のち塾を開いて子弟の教育に当たる。性格が温厚かつ磊落(らいらく)で、諸侯から招かれることが多々あった。舟を浮かべて待乳山(まつちやま=浅草寺=せんそうじの末寺にある小丘)のほとりに遊ぶことを好み、風流儒雅の道を開いた人といわれる。唐詩を研究しその普及を図った。「唐詩選国字解七巻」など著書も多い。宝暦9年没す。享年77。
