漢詩紹介
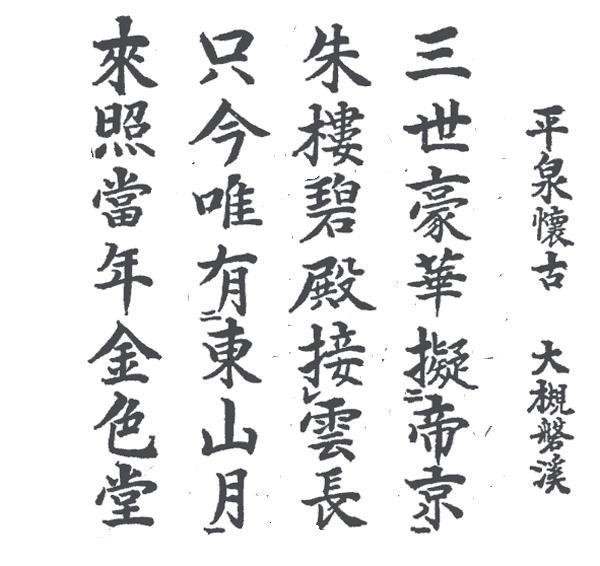
吟者:大取鷲照
2021年8月掲載
読み方
- 平泉懐古 <大槻 磐溪>
- 三世の豪華 帝京に擬す
- 朱楼碧殿 雲に接して長し
- 只今 唯 東山の月のみ有りて
- 来り照らす 当年の 金色堂
- ひらいずみかいこ <おおつき ばんけい>
- さんせいのごうか ていきょうにぎす
- しゅろうへきでん くもにせっしてながし
- ただいま ただ とうざんのつきのみありて
- きたりてらす とうねんの こんじきどう
詩の意味
藤原氏三代の繁栄は豪華を極め、当時の帝都京都に似せて朱塗りの楼台、碧色(へきしょく)の殿堂が見渡す限り高く聳えていた。
今はただ当時の豪華さは一場の夢となり、昔と変わらぬものは東山に上る月だけで、夜ごとに来たって当時の遺物である金色堂を照らしているのである。
語句の意味
-
- 平 泉
- 岩手県平泉にある 奥州藤原氏の居城地
-
- 帝 京
- 帝のいる京都
-
- 三 世
- 藤原清衡(きよひら)・秀衡(ひでひら)・基衡(もとひら)の3代 奥州の地を領した
-
- 金色堂
- 中尊寺の一仏堂 光堂とも
鑑賞
栄枯盛衰の平泉物語
この詩は題字通り奥州藤原氏の栄枯盛衰を詠んだものであるが、構成といい配字といい、これまでの懐古詩の形を踏襲している。前二句は当時の隆盛のさまを述べ、後の二句は現在目前の衰退した姿に加え、自然は昔のままであると結ぶ。さらに李白の「蘇台覧古」に類似している。たとえば転結句は「只今唯西江の月のみ有って 嘗て照らす呉王宮裏の人」をそのまま借用した配字である。ただ李白は当時の遺物は何もないというが、磐溪は「金色堂のみが残存している」と詠う。この金色堂とは?今でも誰の目をも引き留めないではおかない華やかな建物である。三間四方の母屋には覆い屋根がつくられて全部で8メートルの高さがある。内外部にはすべて金箔が貼られ、眩(まぶ)しいほどである。阿弥陀三尊が祭られ、清衡が藤原一族の繁栄を願ったものである。台座の下には藤原三代の遺骨(ミイラ)が安置されている。ここに藤原氏の栄華をしのぶ姿は後を絶たず、松尾芭蕉もその一人である。
備考
奥州三代の藤原氏の歴史
平安時代中期に奥州に力を持っていた豪族であり国守でもあった清原氏がいた。権力争いの内紛が続いていた。
- 1087
- 後(ご)三年の役(えき)の後、藤原清衡が平泉に政庁を開いた
- 1105
- 清衡が中尊寺を創建
- 1108
- 基衡が毛越寺(もうつうじ)を大規模に再建(庭園のみ現存す)
- 1124
- 清衡が中尊寺領内に金色堂を建立(こんりゅう)
- 1170
- 秀衡が無量光院を創設(現存しない)
こうして三代にわたってその後の出羽の国を実質領主として治め、栄華を極めたのである。ところが
- 1187
- 義経が平泉に逃れる
- 1189
-
頼朝と組んだ秀衡の子泰衡が義経を殺害
頼朝が泰衡を討ち藤原氏を滅ぼす
参考
「奥の細道」平泉の名句 松尾芭蕉
かねて耳驚かしたる二堂開帳す。経堂は三将の像を残し、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。……
五月雨(さみだれ)の 降り残してや 光堂
三代の栄華一睡の中にして大門の跡は一里こなたにあり。(中略)さても義臣すぐってこの城にこもり功名一時の叢(くさむら)となる。「国破れて山河在り。城春にして草青みたり」と笠うち敷きて時のうつるまで涙を落とし侍(はべ)りぬ。
夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の京と下平声七陽(よう)韻の長、堂の字が通韻として使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
大槻磐溪 1801~1878
江戸時代末期の儒者
享和元年5月仙台藩医玄沢の次男として江戸木挽(こびき)町に生まれる。字は士広、号は磐溪、諱(いみな)は清嵩(きよたか)。幼い頃から鋭敏であった。昌平黌(しょうへいこう)に学び、のち長崎に赴き蘭学を修行する。帰藩後西洋砲術や儒学に専念した。開国論者で親露排米説を唱えた。明治元年新政府に抵抗した奥羽諸藩挙兵の際に軍国文書司となり捕らえられ、終身禁錮(きんこ)に処せられたが4年4月に釈放され、5月に上京して本郷に隠棲した。同11年6月没す。享年78。従五位を贈られる。
