漢詩紹介
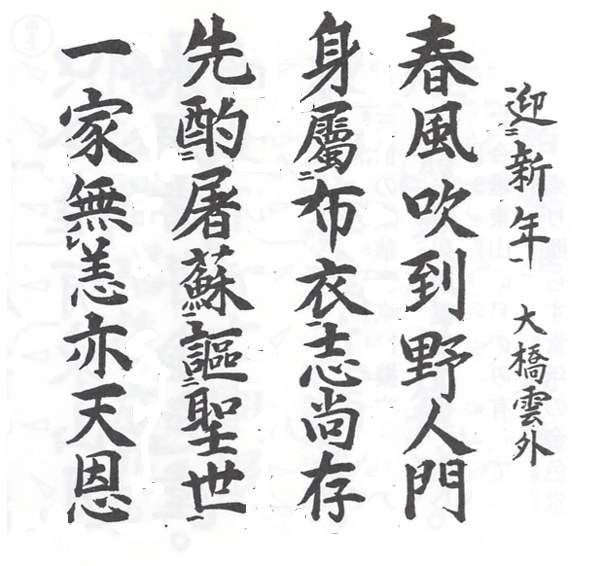
読み方
- 新年を迎う <大橋 雲外>
- 春風吹き到る 野人の門
- 身は布衣に属すれども 志尚存す
- 先ず屠蘇を酌んで 聖世を謳う
- 一家恙無きも 亦天恩
- しんねんをむこオ <おおはし うんがい>
- しゅんぷうふきいたる やじんのもん
- みはほいにしょくすれども こころざしなおそんす
- まずとそをくんで せいせいをうとオ
- いっかつつがなきも またてんおん
詩の意味
新年を迎えて、春風は我が家にも一様に吹いてきた。自分は官位なき庶民ではあるが志は存しているのである。
一家そろって新年の屠蘇を酌み交わし、聖世の有り難き御代に生まれたことを喜び、家族そろって元気でいることは全く天の恵みである。
語句の意味
-
- 野 人
- 政府の役人でなく世間一般の人
-
- 布 衣
- 正式には「ふい」 日本での慣用は「ほい」 粗末な衣服 官についていない庶民
-
- 謳
- 謳歌する 称(たた)える
-
- 聖 世
- 有り難くめでたく治まる世 天皇の治める世ともいう
鑑賞
名書家雲外も庶民であった
読んで字のごとく、一家揃って平穏に新年を迎えたことの喜びを詩にしたものである。作者は大阪市長の秘書室長というから貴人の部類であるが、詩中に「野人」とか「布衣」などの語を用い、庶民の目線で詠まれているのが嬉しい。そして何よりも一家恙無き事を願いとする、万人共通のありふれた思いが人々の共感を呼んで、吟詠家の間では新年の挨拶の場でこの詩が好んで吟じられるというのもうなずける。ただ一つ気になるのは「聖世」の語である。「広辞苑」には「優れた天子の治める世」とある。教本では「有り難いめでたい世」と解釈しているが、「天子の御治世(ごじせい)」の意味も含めて解釈したい。ともあれ四句とも穏やかな語句の連続で親しみのもてる作品である。
漢詩の小知識
弧平について
七言絶句の4字目と五言絶句の2字目は、ひとり平字となって仄字に挟まれることを禁ずる規則がある。この詩の場合、二四不同は守られている。どうすればよかったのか。「布衣」は固定した熟語だから変えられない。5字目の「志」を平字にすればよかった。理屈ではそうなるのだが……。
参考
「布衣之交」(ふいのまじわり)
中国の古文書「史記・藺相如(りんそうじょ)伝」にある言葉で、四字熟語として定着している。「布衣」は布製の一般庶民の服。転じて官位のない庶民。つまり、熟語の意味は身分や地位を離れての庶民的交友のこと。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声三元(げん)韻の門、存、恩の字が使われている。ただ承句の「衣」が弧平になっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
大橋雲外 1878~1961
明治から昭和の学者・書家
明治11年岡山県倉敷市に生まれる。名は富蔵、雲外は号。青年時代に中国に渡り、漢学・書道を研修。後年大阪に居住、書道の才能を認められ請(こ)われて大阪市長の秘書室長を長年勤める。中之島の「なにわ橋」、南の「戎(えびす)橋」の橋名標示は雲外師の揮毫(きごう)である。昭和36年8月没す。享年84。
