漢詩紹介
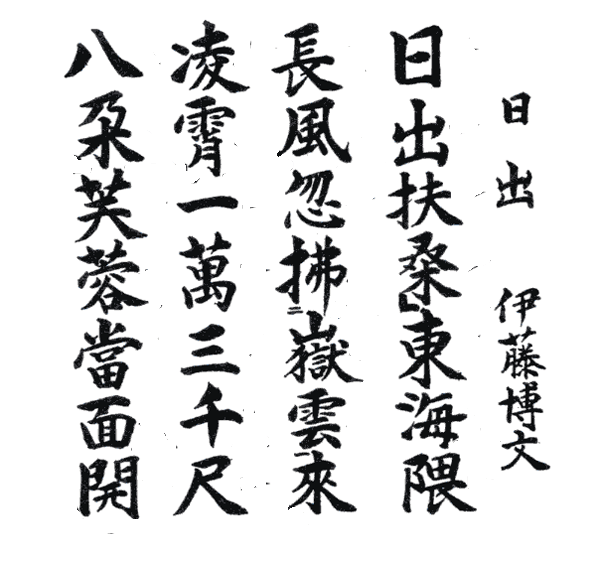
読み方
- 日出 <伊藤 博文>
- 日は出ず扶桑 東海の隈
- 長風忽ち 岳雲を払うて来る
- 凌霄 一万三千尺
- 八朶の芙蓉 当面に開く
- にっしゅつ <いとう はくぶん>
- ひはいずふそう とうかいのくま
- ちょうふうたちまち がくうんをはろオてきたる
- りょうしょう いちまんさんぜんじゃく
- はちだのふよう とうめんにひらく
詩の意味
朝日が東海の一隈に出て、今しも日本の夜明けである。遠くより吹き来る風がたちまち山の雲を吹き払ってゆく。
見れば天空高く、一万三千尺の霊峰が、八弁の蓮華(れんげ)の姿も麗(うるわ)しく顔前にパっと開いて浮かび出るのである。
語句の意味
-
- 扶 桑
- 日本の異名
-
- 隈
- 物のすみ 奥まったところ
-
- 凌 霄
- 空を凌(しの)いで高く聳える 「霄」は雲とか空
-
- 八 朶
- 「朶」は垂れ下がった枝またはそれに付く花 ここでは八つの花弁
-
- 芙 蓉
- 蓮の花 富士山の頂は八朶の蓮華のように剣峰(けんがみね)が八つあって火口を囲んでいるから蓮岳とか芙蓉峰といわれる
鑑賞
望遠と接写レンズで映す富士山
この詩は明治28年に清国から帰朝して作ったもので、朝日に輝く富士山の壮麗な姿を詠じ、朝日の昇るごとく、新興日本の真の姿を全世界の人に知ってもらいたいという意気と念願が表れている。やはり元旦の作だろう。富士山を詠った詩には本会では絶句に「富士山」(石川丈山)、「富岳」(乃木希典)、「甲斐客中」(荻生徂徠)がある。それらは富士の伝説をふまえた霊峰であったり、威容を誇る富士であったり、甲府ならではの姿などを詠っている。博文の富士はその姿を望遠と接写レンズで真の姿に迫ろうとしているという。いずれにしても博文の雄大な心意気に漲(みなぎ)る詩といえよう。「八朶の芙蓉」は詩語として定着している。
備考
古典にも通じていた伊藤博文
伊藤博文と言えば明治中期の、西洋文化、制度を導入した第一人者であるが、この詩句は多く古語が使われている。たとえば「扶桑」、中国から見て東の海中の日の出る所に生える神の木が本来の意味。そこから日本を指すようになった。王維の「送秘書晁監還日本」(秘書晁監日本に還るを送る)に「郷国扶桑外」とある。「朶」はしだれた枝に着いた花で、梅や山吹のような花をいうのであって、蓮のような単独の花弁は範囲に入らないという説があるが、花の延長線上にあるものと考えよう。「芙蓉」も中国の言葉。白居易「長恨歌」に「大液の芙蓉 未央の柳」と使用例がある。「凌霄」も難解語。「凌霄の志」(俗世を離れて別天地に遊ぶ願い)の熟語もあるが、相当漢詩文の素養を修めていた人と思われる。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の隈、来、開の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
伊藤博文 1841~1909
明治時代の政治家・漢詩人
長州山口藩士。山口県熊毛(くまげ)郡に生まれた。旧姓は林、萩藩士伊藤家の養子となる。幼名は利助(りすけ)、のち俊輔(しゅんすけ)、さらに博文と称し、春畝(しゅんほ)と号した。松下村塾に学び尊王攘夷運動に参加。維新後欧米を視察、西郷・木戸・大久保等の重臣の死後は政府の中心人物となり、明治18年内閣制度を創設して初代首相兼宮内大臣となった。21年枢密(すうみつ)院議長となり、翌年、明治憲法を制定した。38年初代韓国統監(とうかん)となり、43年韓国併合の推進のため満州巡遊の途中、ロシア大蔵大臣と会見する予定であったが、ハルピン駅にて安重根(あんじゅうこん)に暗殺された。享年69。
