漢詩紹介
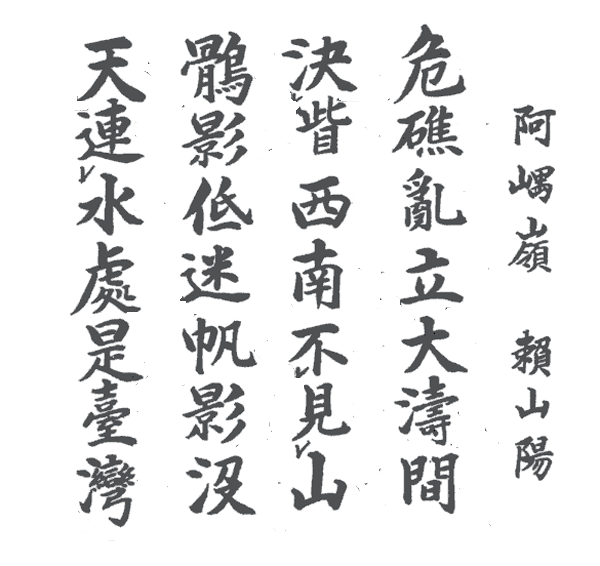
読み方
- 阿嵎嶺 <頼 山陽>
- 危礁乱立す 大濤の間
- 眥を決すれば 西南 山を見ず
- 鶻影は低迷し 帆影は没す
- 天 水に連なる処 是台湾
- あぐね <らい さんよう>
- きしょうらんりつす だいとうのかん
- まなじりをけっすれば せいなん やまをみず
- こつえいはていめいし はんえいはぼっす
- てん みずにつらなるところ これたいわん
詩の意味
奇岩怪石が波間に乱れ立っている。目を見張って西南を眺めると、海水が渺茫(びょうぼう)として山一つ見えない。
ただ隼(はやぶさ)の飛ぶ影が水面すれすれに旋回していて、先ほどまで見えていた白帆の影も、いつしか水平線の彼方に消えてしまった。天と水が一つに連なっているところ、恐らくあの辺りが台湾であろう。
語句の意味
-
- 阿嵎嶺
- 現在の阿久根市 鹿児島県の西海岸にある 湾口に奇岩が並立する
-
- 危 礁
- 「危」は高い 「礁」は波の動きで見え隠れする岩
-
- 大 濤
- 大波
-
- 決 眥
- 目を見張る
-
- 鶻 影
- 「鶻」は鳩属で体は青黒色で尾は短くよく囀(さえず)る ここでは隼の飛ぶ影
鑑賞
台湾は山陽の憧れの地か
藤井竹外の「望海」を思わせる雄大な海の光景である。近くの岩場から目を海に転じ、水平線に隠れていく舟を追い、そして見えないけれど台湾に視線が移る。まさに遠近法をうまく取り入れた詩となって、大画面を見るようである。
ところで最後に台湾を詠み込んだ意図はなんであろうか。日本の最南端なら沖縄諸島か石垣島あたりではないか。それを飛び越えたのはやはり、台湾はずいぶん遠くにある島だと言いたかったか。あるいは台湾は意外に近く、一足またげば大陸だってすぐそばだと快活なところをみせているのか。また旅好きな山陽だから、いつか訪れてみたい憧れの土地なのであろうか。いずれにしても「天草の洋に泊す」とともに名叙景詩である
備考
背景に蘇東坡の詩あり
蘇東坡が海南島に流された後、許されて北に還る時に作った絶句のうち後半2句を借用している。
澄邁(ちょうまい)駅の通潮閣 蘇東坡
余生老いんと欲す南海の村
帝巫陽(ふよう)をして我魂(がこん)を招かしむ
杳杳(ようよう)として天低(た)れ鶻(こつ)没する処
青山一髪是れ中原
蘇東坡の望むところは中原であるから陸地であるが、着想は同じである。
参考
➀頼山陽の九州の旅
文政元年(1818)39歳
- 3月
- 広島出発
- 4月
- 福岡県 博多
- 5月
- 福岡県 太宰府
- 5月~8月
- 長崎県 天草 出島
- 8月
- 熊本県
- 9月
- 鹿児島県 阿久根
- 10月
- 大分県 竹田
- 10月
- 大分県 竹田
- 11月
- 福岡県 日田
- 12月
- 大分県 耶馬渓(やばけい)
文政2年2月 広島帰郷
②阿久根市内にある牛の浜公園には、この詩を刻した石碑が建立されている。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十五刪(さん)韻の間、山、湾の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
頼 山陽 1780~1832
江戸後期の儒者・漢詩人・教育者
広島県竹原市の人で、安芸藩儒者、春水の長男として生まれた。名は襄(のぼる)、字は子成、号は山陽。18歳で江戸の昌平黌(しょうへいこう)学問所で学んだ。ただ素行に常軌を逸脱することが多く、最初の結婚は長く続かず家族を悩ませた。21歳で京都に走ったため、脱藩の罪で4年間自邸に幽閉された。しかしこの間読書にふけり、後の「日本外史」の案がなったといわれる。32歳のころから京都に定住し「山紫水明処(どころ)」という塾を開き子弟の育成と自分の学問に励んだ。子供に安政の大獄で処刑された鴨厓(おうがい=三樹三郎)がいる。享年53。
