漢詩紹介
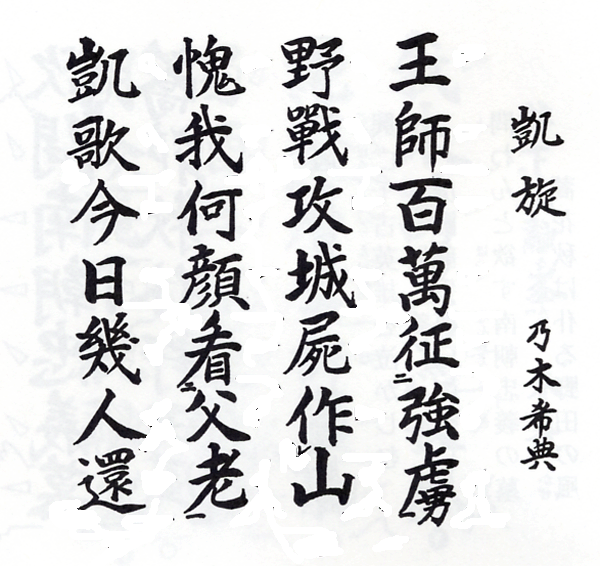
CD①掲載 吟者:内海快城
2014年9月掲載
読み方
- 凱 旋 <乃木 希典>
- 王師百万 強虜を征す
- 野戦攻城 屍 山を作す
- 愧ず我何の顔あって 父老に看えん
- 凱歌今日 幾人か還る
- がいせん <のぎ まれすけ>
- おうしひゃくまん きょうりょをせいす
- やせんこうじょう しかばね やまをなす
- はずわれなんのかんばせあって ふろうにまみえん
- がいかこんにち いくにんかかえる
詩の意味
皇軍百万は強虜ロシアをうち懲(こ)らすため満州に出征した。さすがに敵の備えは堅く、原野の戦いや要塞(ようさい)の攻略に戦死者の屍骸(しがい)は累々(るいるい)と山を成したのである。
幸いに勝利を収めて凱旋することになったものの、このような多数の将兵を死なせた自分は、故国に待つ兵士の父老に対してどの顔をさげて会うことができるだろうか。また勝ち戦(いくさ)の歌を歌いながら今日故郷に帰るのは、百万人中何人いるだろうか。
語句の意味
-
- 凱 旋
- 戦いに勝ち勝利の歌を歌いながら帰る
-
- 王 師
- 皇軍 「師」は軍隊
-
- 強 虜
- おごり高ぶった戎(えびす) 当時のロシア
-
- 愧
- 自分の良心に対してはずかしい
-
- 父 老
- 父親 「老」は年長者への敬称
-
- 還
- もとの所に帰る
鑑賞
凱旋を愧じた凱旋の歌
日露戦争に第三軍司令長官として満州に出征し、旅順攻略に挑み、わが子を始めとしてたくさんの部下を死なせた激しい戦いを振り返って、ポーツマス条約締結後の明治38年の暮れ、奉天から帰還する前に作られたという。講和の内容を聞くにつけ、戦勝したものの、払った犠牲の大きさを思い、凱歌を高らかに歌う気持ちになれず、心の底から悔やみ、心腸寸断の思いであったのだろう。従って詩題はむしろ「凱旋感有り」とか「凱旋を愧(は)ず」ぐらいが適している。
実際の東京凱旋は翌年の9月に行われた。将軍たちの最後尾に乃木大将は一人離れて馬車に乗り、胃をかばうように前かがみな姿勢で行進したといわれている。それは、自身も勝典(かつすけ)、保典(やすすけ)の2児をこの旅順戦で失い、悲痛な親の身であれば、とうてい馬車に乗って手を振る気分にはなれなかったのだろう。従ってその心情を探れば、凱旋といえども幾筋かの反戦感情を読み取ることができる。
備考
名文からの借用もまた妙なり
転句は「史記」の烏江の項とせりふが重なっている。紀元前の202年、漢楚攻防の4年の戦いで項羽は沛公に敗れ、故郷の手前の烏江の港まで帰った時に、故郷の人が「この舟に乗って帰郷してほしい」と勧めたのに、項羽は「天の我を亡ぼすに、我何ぞ渡ることを為さんや。且(か)つ籍(せき=項羽の名)江東の子弟8千人と江を渡りて西す。今一人の還るもの無し。縦(たと)ひ江東の父兄憐れみて我を王とすとも、我何の面目ありてか之に見(まみ)えん。縦ひ彼言はずとも籍独り心に愧ぢざらんや」とあるのによる。
結句は王翰の「涼州の詞」の最後「古来征戦幾人か回(かえ)る」と類似しているが、こういう表現はいくらもあるので、必ずしも王翰の借用とは断定しがたい。似ていることは確かである。
参考
旅順攻略(明治37年)
旅順は当時、清国内の都市であったが、ロシア連合艦隊の基地でもあった。旅順攻略は港内のロシア艦隊を潰滅(かいめつ)させる作戦である。しかし、乃木将軍は3度の正面攻撃を繰り返したものの、ロシア軍の守りは堅く作戦は失敗し、目標を二〇三高地に変え、大口砲の使用によりようやく攻略した。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十五刪(さん)韻の山、還の字が使われている。起句は踏み落としになっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
乃木希典 1849~1912
明治時代の陸軍軍人
長州藩(山口県)の江戸屋敷に生まれる。幼少期吉田松陰の叔父玉木文之進に学問を学び、また剣を栗栖(くるす)又助に学んだ。詩歌にも優れ、石林子(せきりんし)、石樵(せきしょう)とも号した。歩兵第十四連隊長心得として西南戦争に出征し、連隊旗を西郷軍に奪われる屈辱を嘗(な)めたが、日清戦争では第一旅団長として旅順を占領した。日露戦争では第三軍司令官に任命された。明治37年大将となる。明治天皇の御大葬当日静子夫人とともに殉死した。享年64。
