漢詩紹介
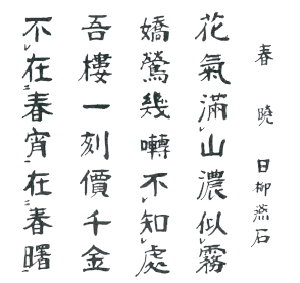
吟者:中谷 淞苑
2004年12月掲載
読み方
- 春 暁 <日柳 燕石>
- 花気山に満ちて 濃やかなること霧に似たり
- 嬌鶯幾囀 処を知らず
- 吾が楼一刻 価千金
- 春宵に在らず 春曙に在り
- しゅんぎょう <くさなぎ えんせき>
- かきやまにみちて こまやかなることきりににたり
- きょうおういくてん ところをしらず
- わがろういっこく あたいせんきん
- しゅんしょうにあらず しゅんしょにあり
詩の意味
花の香気は山に満ちて、いっぱいに霧が立ちこめているかのようである。鶯の声が美しくなまめかしくあちこちで聞こえてくるが、どこで鳴いているのだろう。
自分の住んでいるこの楼上からの眺めは「一刻価千金」ともいうべきであるが、それは春の宵ではなく、春の曙(あけぼの)をいうのではあるまいか。
語句の意味
-
- 春 暁
- 春の夜明け時(まだ暗いころ)
-
- 嬌 鶯
- なまめかしく美しい声の鶯
-
- 幾 囀
- あちこちで囀(さえず)っている
-
- 春 宵
- 春の夕暮れ時
-
- 春 曙
- 春の夜明け時(やや日が差し始めたころ)
鑑賞
敢えて蘇軾に挑(いど)んだ「春曙一刻値千金」
起句の花の香気が濃い霧のようであるという表現は、即座に印象として描けない。吉野山の桜のように桜花が山を覆い尽くしているさまなのであろう。そこに鶯が囀っている。まことに春らしい。それを、値(あたい)千金は宵ではなく曙であると歌った。ただ正面から蘇軾の詩を向こうに回すものだから、読者としては、どちらに値打ちがあるものなのかと斟酌(しんしゃく)を始める。収拾がつく話ではない。なにしろ蘇軾の「春宵一刻値千金 花有清香月有陰」は千年不動の名句であり、その詩意は万人の心に沁み込んでいる。それに対抗して蘇軾に待ったをかけた構図だが、やはり位負けの印象がある。また詩題の「春暁」にしても孟浩然の「春暁」と重なる。こちらは「春眠不覚暁 処処聞啼鳥」の名句が控えている。この2人の名詩人に敢えてかかわろうとした作者のユニークな発想は興味をそそられる。
それはさておき、この詩は自宅の「柳東軒=りゅうとうけん」での作という解説もあり、別荘「呑象楼=どんしょうろう」からの眺望だろうというのもあって定かでないが、日常の生活地から離れた方が似合う。山々の桜が朝日に映え始まる美しさに加え、愛嬌ある鶯の声が、伝統的な春の曙の情趣を味あわせてくれる。淡く美しく描かれた日本画を思わせる叙景詩である。
詩の形
仄起こり七言絶句のようであるが、仄韻を用いているので古詩である。韻は去声六御(りくぎょ)の処、曙と去声七遇(ぐう)韻の霧の字が通韻して使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
日柳燕石 1817~1868
江戸末期の志士・漢詩人
讃岐(さぬき=香川県)仲多度郡(なかたどぐん=現琴平町)榎井(えのい)に富豪の地主加島惣兵衛の1人息子として生まれた。名は政章、号が燕石。性格は豪放で、任侠の世界に親しみ榎井の大親分と称された。頼山陽の「日本外史」に啓発されて勤皇博徒(ばくと)となり、吉田松陰、高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允、西郷隆盛らと交わった。当時の尊王攘夷派の志士の高杉晋作を匿(かくま)って高松藩から投獄されたが、4年後の明治元年に釈放された。直後1868年、奥羽越列藩同盟への制圧軍に従軍し、同年8月越後の柏崎で陣中死した。享年52。
