漢詩紹介
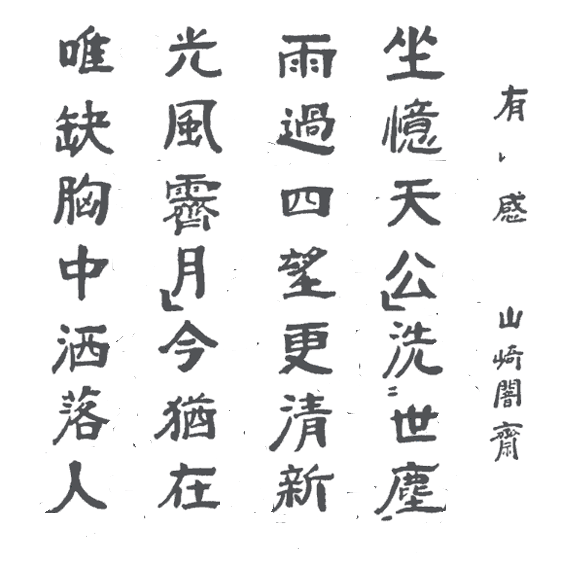
読み方
- 有 感 <山崎 闇斎>
- 坐ろに憶う天公の 世塵を洗うを
- 雨過ぎて四望 更に清新
- 光風霽月 今猶在り
- 唯欠く 胸中 洒落の人
- かんあり <やまざき あんさい>
- そぞろにおもオてんこうの せじんをあろオを
- あめすぎてしぼう さらにせいしん
- こうふうせいげつ いまなおあり
- ただかく きょうちゅう しゃらくのひと
詩の意味
なんとなしにお天道様が人間世界の塵をすっかり洗い清めてくださったかと思われるくらい、一雨過ぎた後のあたりの眺めは、なんと清らかで気持ちの良いことであろうか。
なるほど光風霽月という実景は今も昔も同じであるが、それに比べ世の中には、胸中のさっぱりした人物が欠けているのは、まことに残念である。
語句の意味
-
- 坐 憶
- 何となく考える
-
- 天 公
- 天 お天道(てんとう)様
-
- 四 望
- 四方 あたり
-
- 光風霽月
- 晴れた日のうららかな風と雨後の清らかな月 心中が高明でさっぱりと清らかな人に例える
-
- 洒落人
- 胸中がさっぱりして物事にこだわらない人
鑑賞
「洒落の人」とはどんな人
この詩の主題はどこにあるのか。1つは当時の世相から、権力拡大を専らにする幕府役人に向かっての詩とする。イギリス・イスパニア・ポルトガルなどの来航禁止とキリシタン弾圧が作者30歳ころまで連続して行われている。庶民は苦しんだ。そこで幕府に対し、もう少し大らかな政策を考える役人はいないのかと嘆(たん)じているようだ。2つめは、人の性格を話題にした詩ととる。宋の光風霽月に例えられる周惇頣(とんい)、あるいは自分自身のような、本音しか語らないさっぱりとした人物の少ないことを嘆じているのではないか。
作者の性格は【参考】にもあるように人の門地(もんち)や貴賤(きせん)には無頓着で、正しいものは先哲の教えであると説き、またふるまう。
こういう逸話もある。当時の会津候保科(ほしな)正之が闇斎(あんさい)に「先生も楽しみはありますか」と聞いたところ「1つは霊長類の人間に生まれたこと、2つは学問ができ古の聖賢と出会えること、3つは卑賎(ひせん)に生まれて侯家(大名)に生まれなかったこと」と答えて正之をうならせたという。いずれにしても、闇斎の、権貴に媚(こ)びない大丈夫の気概が看取される。(「日本漢詩=明治書院」)「洒落の人」とはやはり闇斎を指すと考えるのもおもしろい。
参考
闇斎のエピソード
闇斎は一時江戸に下った折、書籍商の隣に下宿し、本を借りては読んでいた。常陸=ひたち(茨城県)の笠間侯井上正利は学を好む人で、この書籍商に人の師たる人物を紹介してほしいと頼んでいた。主人は闇斎がふさわしいと思い、話したところ闇斎は毅然として「侯が道を問わんと欲すれば先ず自身が来るのが本筋ではないか」と言ったので、主人は世間知らずの男だと思い愕然(がくぜん)とした。それでも恐る恐る井上侯に話したところ、侯曰く「礼記に『礼は来たりて学ぶを聞き、行きて教うるを聞かず』とあるが、闇斎とやらは能く之を守れり」と讃えて、すぐに駕籠(かご)を命じて闇斎の宅を訪(と)うたという。この態度が評判となったのか、後、会津侯保科正之(2代将軍秀忠の子)の恩遇を得た。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の塵、新、人の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
山崎闇斎 1618~1682
江戸時代前期の儒者・神道(しんとう)学者・教育者
名は嘉(よし)、字は敬義(もりよし)・長吉、闇斎は号。近江(滋賀県)の生まれで、先祖は播磨(兵庫県)山崎村の人で地名を姓とした。父の代に京都にて鍼医(しんい)を営む。闇斎は幼い時から鋭敏であったが、気が荒く奇人であったので、父は一時僧籍に入れたが、学問好きの闇斎は還俗(げんぞく)して儒者として生きる決意をした。時に25歳。京都にて多数の子弟を教えた。天和2年没す。享年65。明治40年正四位を贈られる。
