漢詩紹介
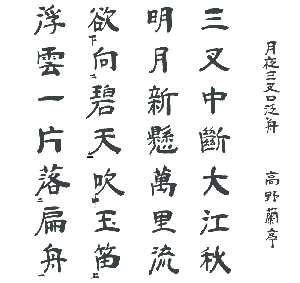
CD④収録 吟者:植田飭菖
2016年3月掲載
読み方
- 月夜三叉口に舟を泛かぶ <高野 蘭亭>
- 三叉中断す 大江の秋
- 明月新たに懸かる 万里の流れ
- 碧天に向かって 玉笛を吹かんと欲すれば
- 浮雲一片 扁舟に落つ
- げつやさんさこうにふねをうかぶ <たかの らんてい>
- さんさちゅうだんす たいこうのあき
- めいげつあらたにかかる ばんりのながれ
- へきてんにむかって ぎょくてきをふかんとほっすれば
- ふうんいっぺん へんしゅうにおつ
詩の意味
隅田川の河口近く、今戸(いまど)川が落ち込むあたりは中洲で川は三つに分かれ、この大河に秋の気配がたちこめ、そこに明月が昇り始め やがて中天にかかってその影を映し、大江の水は万里に遠く流れていく。
興に乗じて澄み切った碧い空に向かって笛を吹こうとすると、一ひらの雲が私の乗る小舟を迎えるかのように、その影を舟上におとした。
語句の意味
-
- 三 叉
- 隅田川下流の今の清洲橋(永代橋とも)附近の俗称 中洲が有り今戸川(江戸川とも)が落ち合うあたり水流が3つに分かれていたという観月の名所
-
- 大 江
- 大きな川 ここでは隅田川
-
- 扁 舟
- 小舟 「扁」はひらたい 小さい
鑑賞
隅田川を中国風に詠んだ幽玄詩
一、二句は三叉口あたりの月夜の光景。三、四句は笛を吹こうと思うと雲が舞い降りてきたというロマンチックな描写。「大江」「碧天」「玉笛」「浮雲」「扁舟」などの語は唐詩によく見かける語で、これらを用いて隅田川の景を中国風に表現しようとしたと思える。実際、隅田川は小さくはないが、利根川や荒川に比べれば「大江」というほどではなく、普通の川だ。現実に作者は隅田川に舟を浮かべているのだろうが、まるで黄河か長江に遊ぶ風情である。空想の世界と現実の世界が混在して区別がつかない。従って解釈も定まらない。
まず起句。「三叉口あたりで二手に分かれて流れていく」(邦人の漢詩文=明治書院)、「今戸川の流れが隅田川の流れを断ち切って三叉をなす」(日本漢詩=明治書院)。次に結句、「(笛の音に誘われてか)空に漂う雲のひとひらがふわりと小舟に落ちてきた」(邦人の漢詩文)(日本人の漢詩=石川忠久)(日本漢詩)、「天上から一ひらの雲がわが乗る小舟を迎えるかのように漂ってきた」(本会旧教本)、「一ひらの雲がわが乗る小舟を迎えるように浮かんでいる」(星野哲史)などさまざまで、解釈に苦しむ。実景表現というより、月夜の元で空想世界に入っている朦朧とした表現に味わいを求めるべきなのであろう。
参考
墨江三絶
この詩のほか、一つは服部南郭の「夜墨水を下る」だが、本会に採用されているので省略する。あと一つは平野金華の「早に深川を発す」であるが、これも「夜墨水を下る」の参考欄を参照されたい。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の秋、流、舟の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
高野蘭亭 1704~1757
江戸時代中期の儒者
江戸に生まれる。名は惟馨(これよし)、字は子式、蘭亭または東里と号す。荻生徂徠の門に入り、学識抜群であったが、17歳の時に失明した。徂徠の助言によって漢詩の道を志し、ついに服部南郭と互角の名声を得た。七言律詩を得意とした。生前自己の詩集の発行を許さなかったが、没後門人らが編集した「蘭亭先生遺稿」10巻がある。晩年鎌倉円覚寺のそばに庵を作り死所としたが、宝暦7年江戸において没す。詩作は万首に及ぶ。享年54。
