漢詩紹介
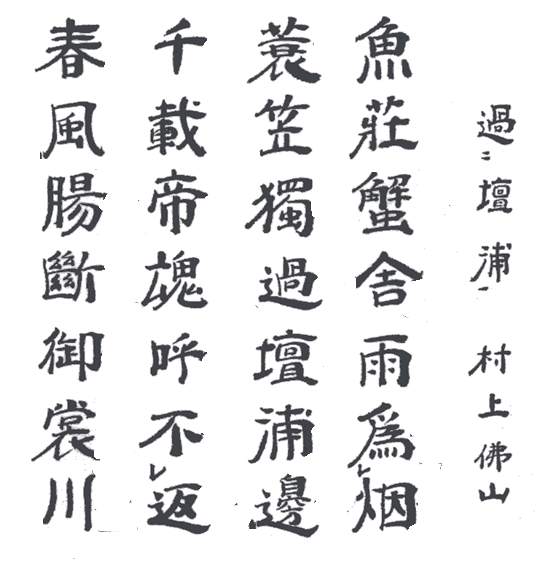
CD②収録 吟者:辰巳快水
2015年3月掲載
読み方
- 壇の浦を過ぐ <村上 仏山>
- 魚荘蟹舎 雨烟と為る
- 蓑笠独り過ぐ 壇の浦の辺
- 千載の帝魂 呼べども返らず
- 春風腸は断つ 御裳川
- だんのうらをすぐ <むらかみ ぶつざん>
- ぎょそうかいしゃ あめけむりとなる
- さりゅうひとりすぐ だんのうらのほとり
- せんざいのていこん よべどもかえらず
- しゅんぷうはらわたはたつ みもすそがわ
詩の意味
壇の浦のほとり、漁師の家が点々と、折からの雨に烟って見える。自分は今、雨の中を蓑(みの)と笠をつけてここを通っていく。
(源平合戦で平家が滅亡したのもここで、時の安徳天皇も御歳8歳で入水=じゅすい=され)早くも千年になろうか、いくらお呼びしても御魂(みたま)はお帰りにならないのである。いとけない御身で「今ぞ知る御裳川の流れには波の下にも都有りとは」と詠われたと聞いて、春風のふく御裳川のほとりに立って往時を偲べは、腸のちぎれるばかりの思いがする。
語句の意味
-
- 漁荘蟹舎
- 漁師の家
-
- 帝 魂
- 安徳帝の御魂
-
- 腸 断
- この上ない苦しみ悲しみ
-
- 御裳川
- 安徳天皇の御歌に詠まれた伊勢の五十鈴(いすず)川 転じて皇統をいう
鑑賞
御裳川の下に都はあったのか
600年前にあった壇の浦の合戦で、幼い安徳天皇が政治の流れに巻き込まれ入水せざる得なかった哀れな物語に同情して作られた詩である。前半の漁師の家、小雨の中、蓑と笠の作者など、一見わびしい背景が悲話の世界に誘う要因となっている。「呼べども返らず」は追悼の慣用句であるが、この場にもよく合う。幼帝が祖母の二位の尼に抱かれ「この水の下にも都があるからそこへ行きましょう」と誘導され、帝も「今ぞ知る御裳川の流れには波の下にも都ありとは」と詠んで素直に従ったという話は「源平盛衰記」にある。
また御裳川は伊勢の五十鈴川の別名で、この川は伊勢神宮のおひざ元だから皇室に縁が深い。尼は帝に対し、この潮の流れを御裳川とみなし、この水に身を委ねることが帝としての進む道なのです、という風な言葉で納得させたのではないか。その哀れな話を借りて壇の浦に流れる小川を地元の人が「御裳川」と命名したのではないかとの憶測もある。いずれにしても不憫の極みのような安徳天皇の末路である。
備考
源平合戦年表
-
- 1180 4月
- 以仁王(もちひとおう)が平氏を討伐せよとの令旨(れいじ)。
-
- 4
- 平清盛が孫の安徳天皇を擁立する。
-
- 10
- 源頼朝が鎌倉に入り陣容を固める。
-
- 1181 2
- 平清盛死す。
-
- 1184 2
- 一之谷の合戦で源義経が勝利する。
-
- 1185 2
- 屋島の合戦で源氏の勝利。
-
- 1185 3
- 壇の浦の合戦で平宗盛が大将の平家軍が全滅する。
参考
滅ぼされた平家の女官たちはどうなったのか
安徳天皇の母徳子は蘇生し、京都の寂光院で建礼門院の名で仏門に入った。一般の女官は各地に移住した。熊本県の五家荘、徳島県の祖谷山、岐阜県の白川村、石川県の奥能登などが平家落人の集落と呼ばれている。一方、贅沢な暮らしに慣れた貴族女性は山里の厳しい生活に耐えられず、里に下り適当な男性と結婚したり、遊女になったりしたといわれている。 (日本史の舞台裏全書=青春出版社)
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の烟、辺、川の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
村上仏山 1810~1879
幕末・明治の漢詩人・教育者
名は剛(つよし)、字は大有、晩年は潜蔵(せんぞう)と改める。遠祖は武田信玄。子孫が豊前(ぶぜん=福岡県)に移住後代々大庄屋を勤める。儒学で身を立てんと15歳で亀井昭陽に学び、のち京都に出て名士と交わる。脚疾を患い26歳で郷里に帰って以来、故郷を一歩も出ることなく、塾を開いて子弟に教えた。性格は温厚和平で孝行心が篤く、権勢利欲を望まなかったので教えを乞うものが多く、身は郷にあって名は天下にとどろいた。明治12年没す。享年70。
