漢詩紹介
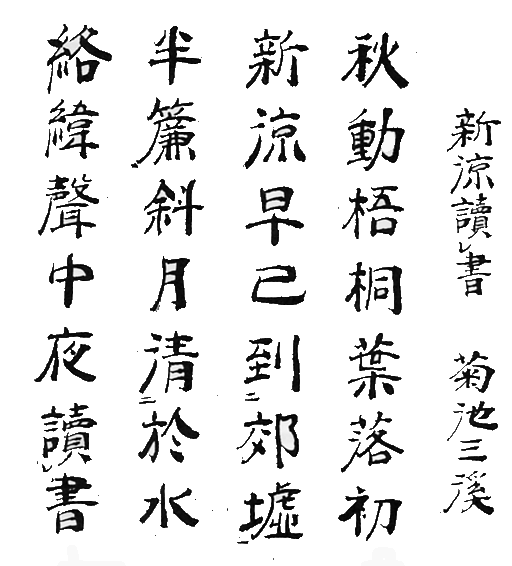
吟者:松尾佳恵
2011年3月掲載[吟法改定版]
読み方
- 新涼書を読む <菊池 三渓>
- 秋は動く梧桐 葉 落つるの初め
- 新涼早く已に 郊墟に到る
- 半簾の斜月 水よりも清し
- 絡緯声中 夜 書を読む
- しんりょうしょをよむ <きくち さんけい>
- あきはうごくごどう は おつるのはじめ
- しんりょうはやくすでに こうきょにいたる
- はんれんのしゃげつ みずよりもきよし
- らくいせいちゅう よる しょをよむ
詩の意味
秋の気配はすでに青桐の葉が落ち始める時に感じられ、新涼の候はすでに郊外の野に忍び寄っている。
半ば捲き上げた簾(すだれ)の間から斜めに差し込む月の光は、水よりも澄み切っており、静かなたたずまいの中に鳴く虫の声を聞きながら書を読むことは、最高の楽しみである。
語句の意味
-
- 新 涼
- 秋になっての初めての涼しさ
-
- 郊 墟
- 郊外の野
-
- 半 簾
- 半分おろした簾
-
- 絡 緯
- 秋の虫 こおろぎ
鑑賞
読書の秋到来
涼しげな秋の気配とともに読書のできる喜びを詠っている。「動」が効いている。この字は「ややもすれば」と読めるから、おもいがけない事態が気付かれないほどの速さで推移するさまを示し、「半簾」も季節感を表し、まだ暑い日もあろうから完全には捲き上げない配慮がある。ところがコオロギの声で秋を知った。すっかり安心して書物を引き出した作者の喜びを共感したい。
備考
読書の喜びと言えば、やはり菅茶山の絶句「冬夜読書」(A4-167)であろう。どちらも学者の読書に対する志が伝わってくる。
漢詩の小知識
比較形の表現の仕方
参考
石川忠久氏は「日本人の漢詩」の中で大正天皇の「秋夜読書」を挙げている。
秋夜漫漫意自如 秋の夜長を心静かに過ごす
西堂点滴雨声疎 西堂に雨だれの音が間遠(まどお)に聞こえる
座中偏覚多涼気 座もしだいに冷えてくる心地
一穂燈光繙古書 燈火一つ点けて古書を読む (繙=ひもとく)
これは秋の読書。菅茶山の詩に酷似している。大正天皇は1367首の漢詩を遺している詩人である。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声六魚(ぎょ)韻の初、墟、書の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
菊池三渓 1819~1891
幕末から明治の儒者・教育者
名は純(じゅん)、字は子顕(しけん)、通称純太郎、三溪は号。紀伊(和歌山県)の人。紀州藩に仕え、初め和歌山藩儒の仁伊田南陽に学び、江戸赤坂邸の明倫館教授となる。のち将軍家茂(いえもち)の侍講となり、維新後は一時警視庁御用係など勤めたが、晩年京都に移り漢学を講説した。詩文に巧みで戯文(ぎぶん)に名あり。著書に「国史略(こくしりゃく)」三編、「近事紀略(きんじきりゃく)」、「晴雪楼詩鈔(せいせつろうししょう)」、「三渓文鈔(さんけいぶんしょう)」などがある。明治24年10月没す。享年73。

