漢詩紹介
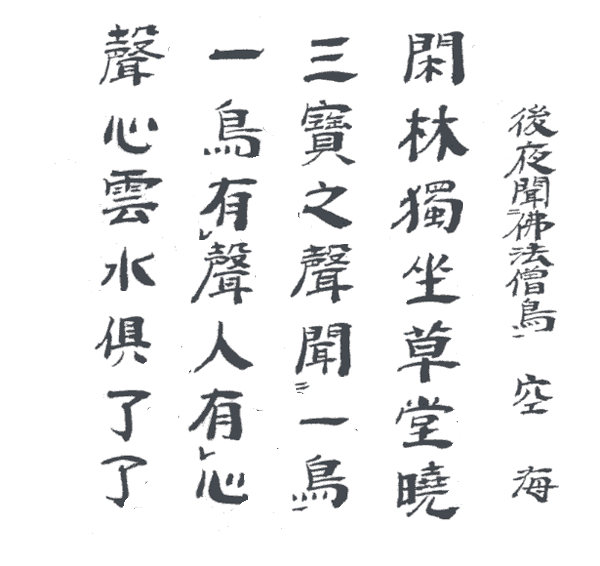
CD①掲載 吟者:塩路澄誠
2014年9月掲載
読み方
- 後夜仏法僧鳥を聞く <空 海>
- 閑林独坐す 草堂の暁
- 三宝之声は 一鳥に聞く
- 一鳥声有り 人心有り
- 声心雲水 倶に了了
- ごやぶっぽうそうちょうをきく <くうかい>
- かんりんどくざす そうどうのあかつき
- さんぼうのこえは いっちょうにきく
- いっちょうこえあり ひとこころあり
- せいしんうんすい ともにりょうりょう
詩の意味
高野山の静かな林中、暁の草堂に独り座して無我無想の境地にいる時、どこからともなくブッポーソーと鳴く一羽のこのはずくの声が聞こえる。
鳥は無心に鳴いているのであろうが、聞く人は心に感ずるものがある。鳥の声と人の心とが、さらに山中の雲と川の流れとが一つに融けあって、ここに仏の教えをはっきりと悟ることができた。
語句の意味
-
- 後 夜
- 仏教では一夜を初夜(そや)・中夜・後夜に分ける 後夜は午前5時ごろ
-
- 仏法僧鳥
- 木葉木菟(このはずく) むく鳥くらいの小型のみみずくで「ブッポーソー」と鳴く
-
- 三 宝
- 仏徒の三つの宝で仏宝(釈迦)・法宝(説教)・僧宝(修法者)
-
- 雲 水
- 雲と川の流れ
-
- 了 了
- 分明 あきらか
鑑賞
このはずくが悟らせた仏・法・僧の三つの宝
この詩は帰朝後に高野山で作られたもので、夜明けにこのはずくの鳴き声に仏の教えを悟ったことを詠んだ詩である。
仏教家の詩には内容的に通常の意解では表現しきれないことが多い。つまり僧侶の思想、また仏・法・僧の概念や悟りの真意などを認知しなければ結局空海の真意に届かない。たとえば、結句で了了と悟ったものは何か。「仏の教え」であろうが不十分な気がする。諸本の解説を例に挙げると「仏道の妙理」「一切真如の実相」「煩悩菩提の真理」「三毒三徳の大乗の妙理」などとあって、却って朦朧(もうろう)とする。「深い仏教の真理」とまとめると当たらずとも遠からずということで許していただこう。
このはずくは南方から来る渡り鳥で、霊鳥とされている。この鳥は夜には鳴かない。愛知県の鳳来山、東京都の御嶽(みたけ)、高尾山などでよく聞かれ、高野山には多く棲息していることからすれば高野山・仏道・空海と一本につながり、高僧の詩らしさがにじんでくる。
備考
空海の詩は25題ぐらいしか遺(のこ)されていないが、近体詩論から見れば、良寛の場合と同様、破格詩が多い。この詩も仄韻の使用、同字の多用、句末の字を次句に引き続く用法は中国詩にも見られるが、普通の作詩家は避けてゆくものであるので、この詩の場合、特別な境地に立脚し、特別な思いを表現しているとして、詩の規則が後回しになるものと理解しておこう。
詩の形
平起こり七言古詩の形であって、仄韻の上声十七篠(じょう)韻の暁、鳥、了の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
空海 774-835
平安時代初期の高僧 真言宗の開祖
讃岐の国(香川県)多度郡屏風ヶ浦の人。俗称は佐伯氏。幼名は真魚(まお)、諡(おくりな)は弘法大師。18歳で出家。延歴23年(804)31歳で遣唐使に従って唐に入り、恵果阿闍梨(けいかあじゃり)に会い、真言・秘密両部の法を受け、阿闍梨の位とさまざまな法具・仏典を授けられ、大同元年(806)帰国した。43歳で高野山に金剛峯寺(こんごうぶじ)を建立し、50歳で朝廷より京都の東寺を賜り真言宗の根本道場とした。諸国を歴遊して庶民を援(たす)けた。多数の著書がある。承和2年(835)3月没す。享年62。
