漢詩紹介
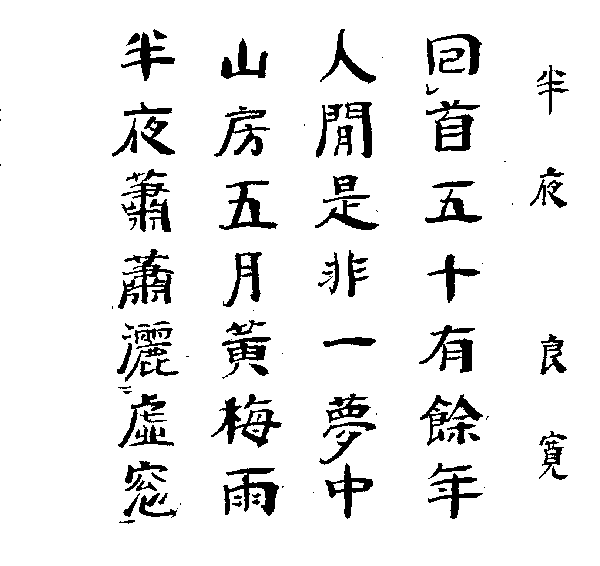
読み方
- 半 夜 <良 寛>
- 首を回らせば 五十 有余年
- 人間の是非は 一夢の中
- 山房五月 黄梅の雨
- 半夜 蕭蕭として 虚窓に灑ぐ
- はんや <りょうかん>
- こうべをめぐらせば ごじゅう ゆうよねん
- じんかんのぜひは いちむのうち
- さんぼうごがつ こうばいのあめ
- はんや しょうしょうとして きょそうにそそぐ
詩の意味
過ぎ去った五十余年の生涯を顧みると、人間社会のことは是も非も善も悪も、すべて夢の中のことのように感じられる。
この山の庵に一人座っていると、五月雨が真夜中の窓に寂しく降り注ぐのであった。
語句の意味
-
- 半 夜
- 夜なか
-
- 人 間
- 世の中 人間社会
-
- 山 房
- 山の庵 五合庵を指す
-
- 黄梅雨
- 梅の実が黄色に熟すころの雨 梅雨
-
- 蕭 蕭
- ものさびしいさま
-
- 虚 窓
- 誰もいない部屋または窓
鑑賞
悟り切った心情の中にある心の安定感
この詩は作者晩年の住まいである越後の五合庵での作。一般人には理解しがたいが、一種の諦観(ていかん)にも似た心境は、時代や性別の違いを越えて万人の共感を促すものがある。
もの寂しさを前面に出した隠者らしい詩となっている。「一夢」「半夜」「虚窓」などがそれで、極め付きは直接的表現の「蕭蕭」という叙景と同時に叙情を含んだ言葉である。この語がなくても十分寂しさは伝わってくるのに、それを強調したかったのであろう。ただこの詩の主題を作者の孤独な寂しさというふうにだけ理解するのは不十分である。彼の質素な暮らしぶりや孤独なわび住まいに同情してはいけない。彼の到達した心の安定は、狭くて質素な五合庵で初めて得られたもので、何十年にもわたって求め続けたものでもあるからだ。一般の人には会得(えとく)しがたい。作者の悟り切った心の安定感と幸福感を類推するのみである。
同じ僧侶の空海と比べてみると、その住む世界や、悟りの求め方に大きな違いがあることを知ることも、良寛詩の鑑賞要点である。
参考
①類似の作品
-
- 閃電光裏 六十年
- せんでんこうり ろくじゅうねん
-
- 世上栄枯 雲往還
- せじょうのえいこは くものおうかん
-
- 巌根欲穿 深夜雨
- がんこんうがたんとほっす しんやのあめ
-
- 灯火明滅 古窓前
- とうかめいめつす こそうのまえ
世上の栄枯とわび住まいの対照表現が一層隠者らしい。年齢、深夜、雨、窓が共通しているのが良寛らしさか。
②良寛の俳句
- 焚くほどは風が持て来る落葉かな
- 手拭いで年を隠すや盆踊り
- のっぽりと師走も知らず弥彦山(やひこやま)
詩の形
良寛の天衣無縫の性格の如く全く破格の詩である。平仄も度外視されている。仄起こり七言古詩の形であって、上平声一東(とう)韻の中の字と三江(こう)韻の窓の字が通韻して使われている。起句は踏み落としになっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
良 寛 1758~1831
江戸時代後期の僧侶
本姓は山本、幼名は栄蔵、字は曲(まがり)、出家して良寛または大愚と号した。越後(新潟県)出雲崎の人。家は代々神職と名主を兼ね、父泰雄は(越後俳壇で)以南と号した。良寛はその長子。成長して備中(岡山県)玉島(現倉敷市)の円通寺で国仙和尚に学び、後諸国を行脚して帰国し、国上山の五合庵に入り、40歳からここに住んだ。晩年には麓の乙子神社の庵に移り、天保2年1月、島崎の木村家(良寛庵)で貞心尼に看取られ没す。享年74。良寛は俳句、短歌、書の道にも通じていた。
