漢詩紹介
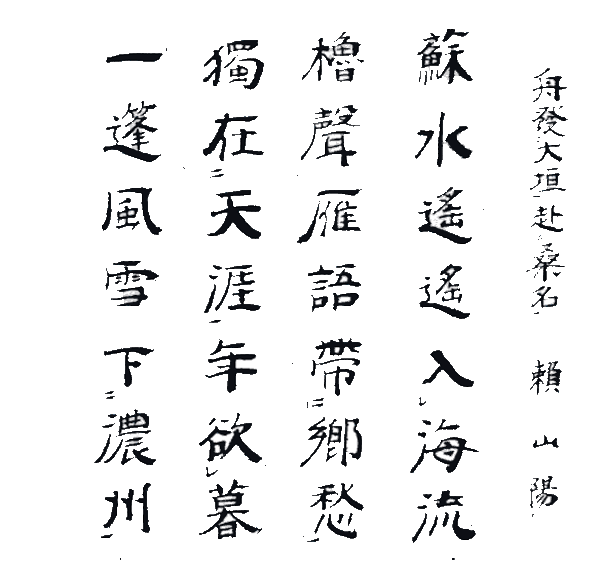
CD①掲載 吟者:奥山紅雋
2014年9月掲載
読み方
- 舟大垣を発して桑名に赴く
- <頼 山陽>
- 蘇水遥遥 海に入って流る
- 櫓声雁語 郷愁を帯ぶ
- 独り天涯に在って 年暮れんと欲す
- 一蓬の風雪 濃州を下る
- ふねおおがきをはっしてくわなにおもむく
- <らい さんよう>
- そすいようよう うみにいってながる
- ろせいがんご きょうしゅうをおぶ
- ひとりてんがいにあって としくれんとほっす
- いっぽうのふうせつ のうしゅうをくだる
詩の意味
木曽川の流れは、遥かに遠く海に注いでいる。この川を自分は今、船で下っているのであるが、時折り櫓の音や頭上を渡る雁の声を聞くと、故郷のことが思い出される。
今一人故郷を遠く離れたこの地にあって、今年もまた暮れようとしている。降りしきる風雪の中を一艘の蓬舟(とまぶね)に乗って、桑名に向かって美濃の国を下ってゆくのである。
語句の意味
-
- 大 垣
- 岐阜県大垣市 昔は木曽川船運の要所
-
- 桑 名
- 三重県桑名市 伊勢湾に面し昔は海運の要所
-
- 蘇 水
- 木曽川 岐蘇川とも書く
-
- 一 蓬
- 一艘のとま舟 「蓬」はとま 竹や茅で編んだもの
-
- 濃 州
- 美濃の国 今の岐阜県
鑑賞
木曽川を下りつつ描いた思いは、さて
山陽34歳の冬、詩友2人を伴い美濃、尾張、遠江(とおとうみ)、伊勢の各地を遊歴した時の作である。ただ鑑賞は諸本によりかなりの違いがある。
〔鑑賞その1〕舟上から思う郷愁詩
「郷愁」「天涯」の語が主題を表しており、櫓の音や雁の声を聞きながら、遠い故郷の広島を思っているというもの。
〔鑑賞その2〕江馬細香との別離を憂う詩
大垣では江馬蘭斎宅を訪れている。娘細香の詩稿の批正を頼まれた縁による。この時、山陽は細香の清楚な人柄と詩才に好感を抱いた。父の反対で結婚には至らなかったが、両人の交遊は山陽がなくなるまで続いた。以上の点を考慮すれば、細香との淡い交わりに未練を抱きつつ別れていくわびしさを込めたというもの。
〔鑑賞その3〕菅茶山に対する申し訳なさを詠んだ詩
山陽は当時、父と断絶状態であった。それを茶山の調停で父との対面が許された。しかも山陽と茶山の間にも円滑を欠くものがあり、謝罪と感謝を表すため茶山邸を訪ねるつもりだったが、茶山との間にしこりが残っていて東への旅路をとった。この申し訳なさと深い憂いが込められているというもの。
〔鑑賞その1〕が一般的であるが、2や3も捨てがたい。
備考
本当に木曽川を下ったのか
蘇水即ち木曽川の位置であるが、地図でも明らかなように大垣の近くを流れている川は揖斐川(いびがわ)であり、そのまま下ると桑名に着く。木曽川は50キロメートルも東を流れており、その川で舟に乗ったとは考えられない。確かに揖斐川は大垣市を離れると木曽川に合流しているが、桑名の手前では木曽川は東に、揖斐川は桑名の町の近くを流れて伊勢湾に注いでいる。どの解説書にも、この詩は木曽川を下った折の詩とあるが、地理上かなり無理がある。山陽が舟に乗ったのは揖斐川であり、下ったのも揖斐川であると考えられる。ではなぜ事実と違うことを詩語に入れたのか。おそらく詩的効果を狙って、有名度の高い木曽川の名を借りて詠んだのだろうと思われる。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であるが、転結句の平仄関係が原則外れであるので拗体である。下平声十一尤(ゆう)韻の流、愁、州の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
頼 山陽 1780~1832
江戸後期の儒者・漢詩人・教育者
広島県竹原市の人で、安芸藩儒者、春水の長男として生まれた。名は襄(のぼる)、字は子成、号は山陽。18歳で江戸の昌平黌(しょうへいこう)学問所で学んだ。ただ素行に常軌を逸脱することが多く、最初の結婚は長く続かず家族を悩ませた。21歳で京都に走ったため、脱藩の罪で4年間自宅に幽閉された。しかしこの間読書にふけり、後の「日本外史」の案がなったといわれる。32歳のころから京都に定住し「山紫水明処(どころ)」という塾を開き子弟の育成と自分の学問に励んだ。子供に安政の大獄で処刑された鴨厓(おうがい=三樹三郎)がいる。享年53。
