漢詩紹介
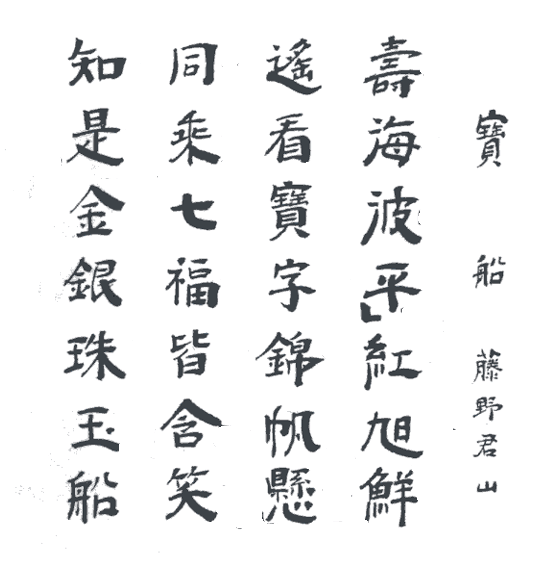
読み方
- 宝 船 <藤野 君山>
- 寿海波平らかにして 紅旭鮮やかなり
- 遥かに看る宝字 錦帆の懸るを
- 同乗の七福 皆笑を含む
- 知る是金銀 珠玉の船
- たからぶね <ふじの くんざん>
- じゅかいなみたいらかにして こうきょくあざやかなり
- はるかにみるほうじ きんぱんのかかるを
- どうじょうのしちふく みなえみをふくむ
- しるこれきんぎん しゅぎょくのふね
詩の意味
波平らかな大海原に、旭日が燦々として昇り、遥か彼方から宝の字を描いた錦の帆を上げて宝船がやってくる。
同乗するのは七福の神であり、皆安らかな笑みを浮かべている。金銀財宝を山のごとく積みこんでいる宝船である。
語句の意味
-
- 紅 旭
- 朝日 旭日
-
- 七 福
- 七柱の福の神 七福神(大黒天、恵比寿、毘沙門天=びしゃもんてん、弁財天、布袋=ほてい、福禄寿、寿老人)
-
- 金銀珠玉
- 金銀などの七宝
鑑賞
幸せは次第に近づいてくるもの
七福神を乗せた帆かけ船を描いた絵を見ての作である。「寿海」「紅旭」「宝字」「錦帆」「七福」「金銀珠玉」などのおめでたい語を散りばめて喜びを表現している。この詩の良さは、遠から近への動きを用いているところにある。1句目は何も見えない遠い海。2句目で宝の字を用いた帆かけ船が視野に入る。次第に近づくと七福神が笑いながら乗っているのが見えてくる。結句ではなんと金銀財宝を積んでいるではないか、という構成である。幸せが次第に近づいてくるという表現意図はこの詩の魅力である。昔からこの絵を正月2日に枕の下に入れて寝るといい夢を見るといわれて、江戸時代にはこの絵の版画を「お宝!」「お宝!」と売りあるく人がいた。文句なしのおめでたさを十分味わえば良い。
参考
七福神とは(三省堂国語辞典より)
- 大黒天=
- 頭巾をかぶり、右に打ち出の小槌を持ち、左に大きな袋を抱え、米俵の上に乗っている。台所の神と言われている。
- 恵比寿=
- 風折烏帽子(かざおりえぼし)に狩衣(かりぎぬ)・指貫(さしぬき)姿で、鯛を釣り上げている人。日本では商業の神として信仰される。
- 毘沙門天=
- 鎧兜(よろいかぶと)を身につけ、手には矛を持っている。財務の神。多聞天(たもんてん)とも。
- 弁財天=
- 音楽、弁舌、福徳、智恵の女神。宝冠をつけ琵琶を弾く美人。弁天様。
- 布 袋=
- 大きな袋を担ぎ、頬がふっくらとして、坊主頭で、太鼓腹をした僧。弥勒(みろく)菩薩の化身といわれ、背中にも大きな目がある。
- 福禄寿=
- 福運、俸禄、寿命の三徳を兼ね備える。背が低く頭が長くて髭(ひげ)が多い。杖に経巻を結び鶴を伴っている。
- 寿老人=
- 頭が長く白いひげを垂らし、杖をつき、うちわを持ち、鹿を連れている老人。長寿を授ける神。
七宝とは
七宝 7種類の宝で、次の如く経文(きょうもん)によって異なる。
- 法華經(ほっけきょう) =
- 金 銀 瑠璃(るり) 硨磲(しゃこ) 瑪瑙(めのう) 真珠 玫瑰(ばいかい)
- 般若經(はんにゃきょう)=
- 金 銀 瑠璃 硨磲 瑪瑙 琥珀(こはく) 珊瑚(さんご)
- 恆水經(こうすいきょう)=
- 金 銀 瑠璃 真珠 硨磲 明月珠(めいげつじゅ) 摩尼珠(まにじゅ)
- 阿彌陀經(あみだきょう)=
- 金 銀 瑠璃 玻璃(はり) 硨磲 赤珠(せきじゅ) 瑪瑙
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の鮮、懸、船の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
藤野君山 1863~1943
明治から昭和時代初期の役人・教育者
東京に生まれる。名は静輝(しずてる)、号は君山。日露戦争に従軍した後、演劇評論家として活躍した。乃木希典とも親交した。宮内庁式部職(しきぶしょく=皇室の祭典・儀式・雅楽・交際・狩猟などを司る)に勤務し、退官後各地を歴訪し、また大正天皇より賜った菊(千本菊)にちなんで私塾「賜菊園(しぎくえん)」を主宰して教育に献身した。昭和18年没す。享年80。
