漢詩紹介
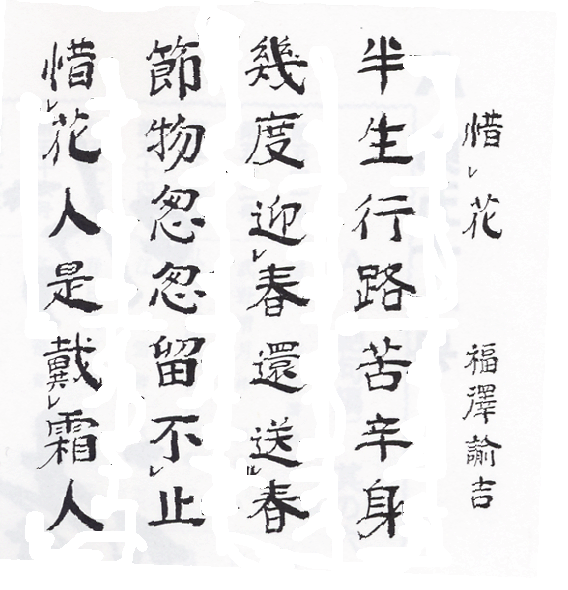
CD④収録 吟者:古賀千翔
2016年5月掲載
読み方
- 花を惜しむ <福沢 諭吉>
- 半生の行路 苦辛の身
- 幾度か春を迎え 還春を送る
- 節物は怱怱として 留むれども止まず
- 花を惜しむの人は是 霜を戴くの人
- はなをおしむ <ふくざわ ゆきち>
- はんせいのこうろ くしんのみ
- いくたびかはるをむかえ またはるをおくる
- せつぶつはそうそうとして とどむれどもやまず
- はなをおしむのひとはこれ しもをいただくのひと
詩の意味
今まで歩んできたあとを振り返ってみれば、苦辛の連続であった。その間、何回春が巡ってきたことだろう。
四季折々の景色の移り変わりは早く、引き止めることもできない。ようやく花を賞(め)で楽しむことのできる身になったが、すでに白髪の老人になってしまった。
語句の意味
-
- 行 路
- 人生行路
-
- 還
- 巡ってまた
-
- 節 物
- 四季折々の景色 ここでは春の花の咲く季節
-
- 怱 怱
- 日時があわただしく過ぎゆく
-
- 戴 霜
- 白髪まじり
鑑賞
苦辛多い半生とは
吉田松陰や坂本龍馬らが攘夷論を掲げて獅子奮迅しているころ、諭吉はすでに幕府から時代の先覚者として一目置かれ、欧米使節団に加わり、日本の舵取りを託された大人物である。大学の創設も苦辛の一つであろうが、明六社を興し、日本人を封建・儒教思想から四民平等・民権論思想に転換させる事業は、想像を絶する苦辛であったろう。いわば日本の価値観を黒から白に変えようとしたのである。そして無我夢中で生きてきた人生を振り返ったときは、すでに白髪であったという。
青春時代を惜しみ老境を嘆く詩は「代悲白頭翁」や李白の「秋浦の歌」など多数あり、主題としては新鮮味はないが、日本人の詩であるからこそ、身近な味わいがある。
備考
諭吉の経歴
- 1836 3歳
- 父を失う
- 1858 25歳
-
大阪の適塾(てきじゅく)の塾頭となる
江戸中津藩邸屋敷で蘭学を教え始める - 1860 27歳
- 渡米使節団員として咸臨丸(かんりんまる)で渡米
- 1862 29歳
- 訪欧使節団員としてヨーロッパを見聞
- 1867 34歳
- 軍艦購入交渉のため再び渡米
- 1868 35歳
- 鉄砲州の塾を芝新銭座(しばしんせんざ)に移し慶應義塾と称した のちの慶應義塾大学
- 1874 41歳
- 「明六社」を興し明六雑誌を発刊 封建思想を非難し啓蒙活動が活発になる
- 1885 52歳
- 「脱亜論」を発表し日清戦争を支持した
参考
幼年時代から奇才な少年
幼い頃、藩主の名が記されている紙を踏んで、兄にひどく叱られた。諭吉少年は紙を踏んだぐらいで叱られる道理がない、と考え、ならば神様の名のあるお札を踏んだらどんな天罰があるのかと思い、ひそかに実行してみたが何事も起こらなかった。次にそのお札を厠(かわや)へ持っていって捨ててみたが、それでも何も起こらなかった。因習、迷信を信じなくて、事実こそが信頼に足ると深く確信した。
「人物探訪・日本の歴史⑱明治の逸材」(暁教育図書)
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の身、春、人の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
福沢諭吉 1834~1901
幕末・明治時代の先覚的思想家・教育者
大分県中津藩の下級武士の子として大阪で生まれる。20歳で緒方洪庵の適塾で蘭学を学ぶ。27歳から幕府の使節として3度洋行。近代西洋文明に関する当代随一の知識人となった。明治元年慶応義塾を創設。以後教育と著作活動に専心。啓蒙思想家として功績を残した。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」で有名な「学問ノススメ」「西洋事情」「文明論之概略」などは代表作。明治34年2月没す。享年68。
