漢詩紹介
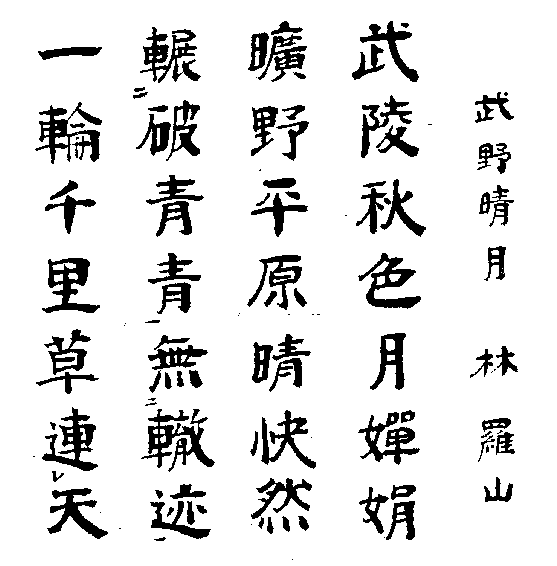
読み方
- 武野の晴月 <林 羅山>
- 武陵の秋色 月嬋娟
- 曠野平原 晴れて快然たり
- 青青を輾破するも 轍迹無し
- 一輪千里 草天に連なる
- ぶやのせいげつ <はやし らざん>
- ぶりょうのしゅうしょく つきせんけん
- こうやへいげん はれてかいぜんたり
- せいせいをてんぱするも てっせきなし
- いちりんせんり くさてんにつらなる
詩の意味
武蔵野は秋一色で、月の光もうるわしい。広々とした平野は明るく晴れわたり、気持ちが良い。
月は青い空をまるで車輪が巡るように渡っていくが、その跡を残さない。満月は千里彼方まで輝き、武蔵の草原もまた広大で、遠く天に連なっているほどに思われる。
語句の意味
-
- 武 野
- 武蔵野の原
-
- 武 陵
- 中国湖南省にあった郡名で武州ともいった 「武」の字が共通しているので武蔵の国に借用した
-
- 嬋 娟
- 姿態の品が良いさま あでやかな
-
- 快 然
- さっぱりとしていて気持ち良いさま
-
- 輾 破
- 車輪が巡る ここでは月の輪が巡る
-
- 轍 迹
- 車の輪だちの跡 ここでは月の輪だちの光の跡
鑑賞
一望千里秋月に照らされた武蔵野
武蔵野はふつう埼玉県川越市以南から東京都府中にいたる範囲をいうが、ここでは作者の別荘に近い上野あたりの風景だろう。一望千里秋月に照らされた武蔵野の広大な景観を髣髴(ほうふつ)とさせる。宇宙から眺めたような詠いっぷりに中国詩の趣きを感じる。想像の世界にいざなってくれる。
さすがに当代一流の知識人だけあって用語が難解である。たとえば「嬋娟」。「妖艶」とどう違うのだろう。「曠野」と「広野」では視界が違う。「曠野」は無限の広さを意味する。「輾破」は回転を表すが難語句だ。わだちの跡も一般的には「轍跡」と書くが、古典籍には「轍迹」の使用が多い。林羅山らしい詩風と言うべきか。
現在の武蔵野は都市化しており昔の面影はないが、当時は文人たちがよく訪れたところであった。
参考
武蔵野と言えば国木田独歩
この詩は明治中期の作家である国木田独歩を思い起こさせる。その代表作「武蔵野」という短編小説には次のような描写がある。 「楢の類だから黄葉する。黄葉するから落葉する。時雨がささやく。凩が叫ぶ。一陣の風小高い丘を襲へば、幾千万の木の葉高く天空に舞ふて、小鳥の群かの如く遠く飛び去る。木の葉落ち尽くせば、数十里の方域に亘る林が一時裸体になって、蒼ずんだ冬の空が高く此上に垂れ、武蔵野一面が一種の沈静に入る。空気が一段澄みわたる。……」 とあって、武蔵野は樹林地帯であることがわかる。田園と草原と樹林地帯を持つ広大な原野を想像しよう。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって下平声一先(せん)韻の娟、然、天の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
林 羅山 1583~1657
江戸時代初期の儒者
名は信勝、字は子信(ししん)、羅山は号。京都に生まれた。少年期に剃髪して道春と称した。成人して建仁寺に入り儒仏を学んだ。18歳の時還俗(げんぞく)し朱子学に志し、次いで藤原惺窩(せいか)に師事する。22歳の時幕府の顧問となり、家綱に至る4代に仕えて教学や諸制度に参画した。上野に別荘を建て家塾を開き、のち昌平黌(しょうへいこう)となる。羅山は世襲の大学頭(だいがくのかみ)林家の始祖となった。著書に「本朝編年録」「寛永諸家系図伝」その他多数ある。明暦3年正月没す。享年75。
